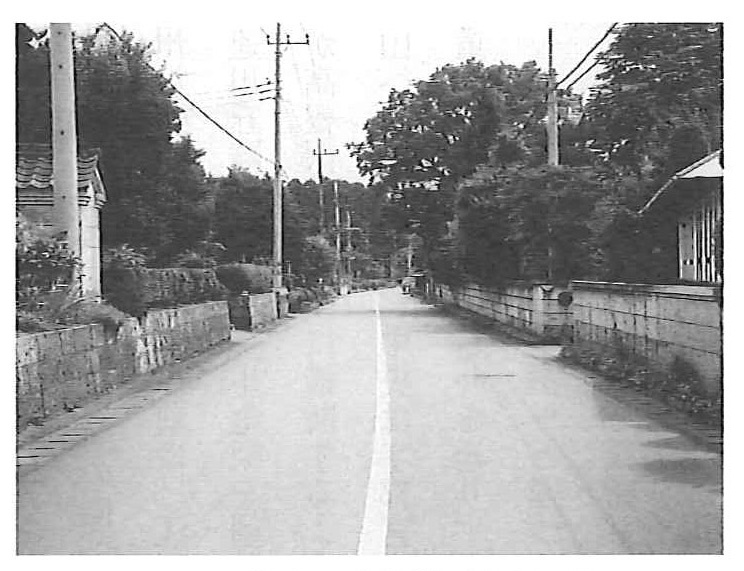高根沢町には、古くからの街道として、関街道・立街道(辰街道)などがある。奥州街道は、高根沢町地内は通じていないが、白沢―上阿久津―氏家―喜連川と近い位置で通過していた。関街道は、鬼怒川板戸河岸から高根沢町を横断するように石末原(関俣を通過した時期もあったという)―鴻野山―鹿子畑を通過し、奥州白河の関へと続いた。奥州街道と並行するように走り、脇街道としての役割を果たしたが、奥州街道が整備される以前は、江戸と奥州を結ぶ最大の動脈路であったという。また、立街道は高根沢町東部の喜連川丘陵沿いの桑窪―亀梨を通り鴻野山を北上して、喜連川に通じる街道であった。また烏山街道と称する街道が高根沢町を東西に横断するように三本通じている。北の道は宇都宮―宝積寺―石末―花岡―鴻野山―大金―鳥山へと続く道で、中央は宇都宮―岡本―宝積寺―鷺ノ谷―赤堀―金井―太田―台新田―福岡―烏山と続く。南の道は、宇都宮から石井を通り、上高根沢の台ノ原―吹上―廻谷を通過して、八ツ木からまた高根沢町の中柏崎を一部通り、塩田―烏山へと通ずる道である。このように、近世からの中心的な地域であった宇都宮と烏山を結ぶ街道が、高根沢町地内を横断し、物資輸送の道として機能し、高根沢町は宇都宮と烏山を結ぶ通過点としての位置にあった。こうした道を利用して、客の輸送のための客馬車や馬車引きなどによる荷馬車輸送が盛んに行われるようになる。
明治末期から大正時代にかけて、トテ馬車と称して乗合客馬車が宝積寺―鳥山間を運行していた。烏山発が午前七時頃・一〇時頃と午後二時頃の三回で片道四時間ほどかかり、乗車賃は一円程度であったという。当時としては、非常に高い乗車賃であった。後に二回の発着となったようで、烏山線が開通し宝積寺―鳥山間までの所要時間が約一時間となり料金が五〇銭であったため、乗合客馬車は鉄道に対抗できず廃業に追い込まれて行く。
明治時代に入ると幹線道路としての陸羽街道(現国道四号線)が、栃木県令三島通庸の手により明治一七年に整備され、高根沢町の西端を縦断し、鉄道とともに交通の中心的な役割を果たした。
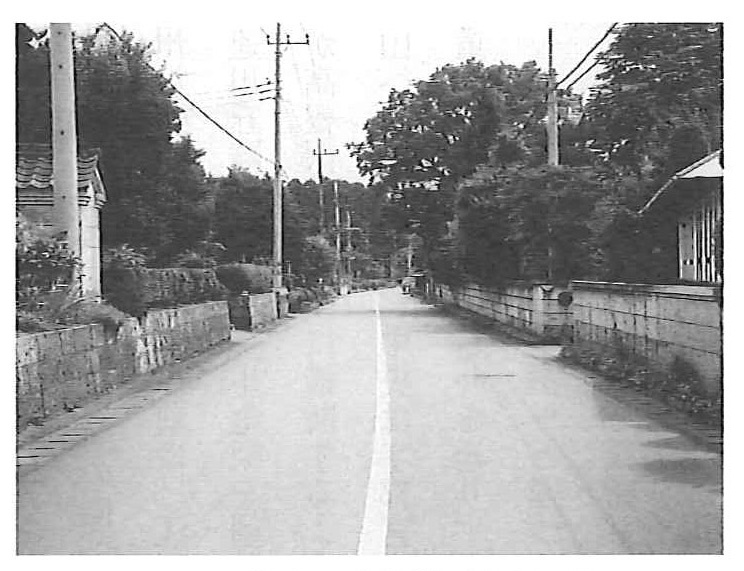
図1 現在の立街道(台新田)