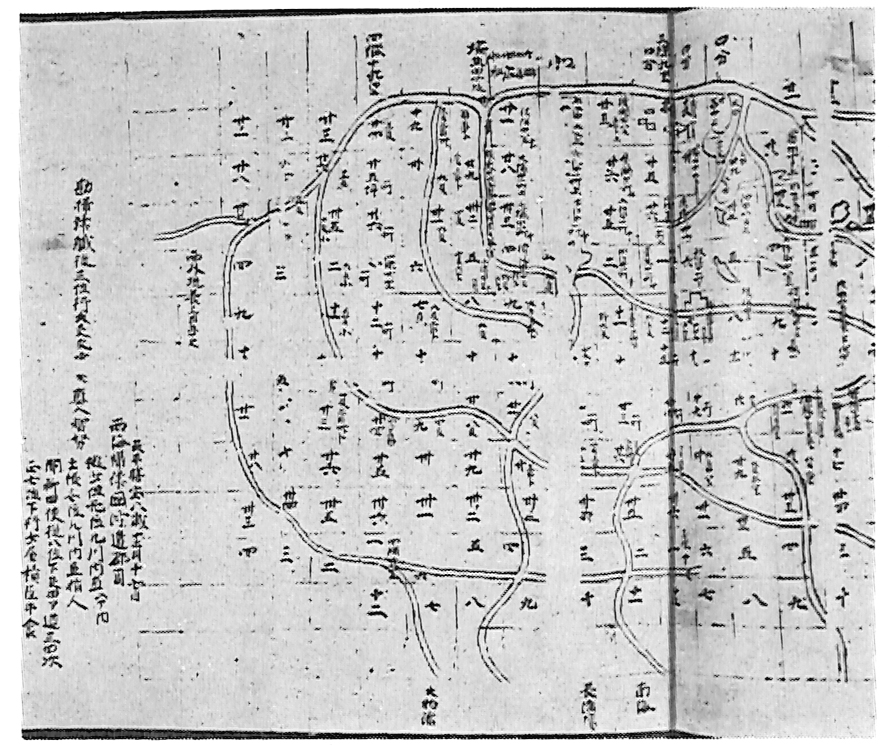以上、畿内地方の一般的な情勢について述べてきたのだが、宝塚地方でも、公地公民制が崩壊したあと、このような田堵が成長していたはずである。もっとも市域の史料からは田堵の名まえをみいだすことはできないが、現在の尼崎市内にあった東大寺領猪名荘で、ややのちの例ではあるが田堵の名まえや動きを知ることができる。すなわち天喜三年(一〇五五)のころ、猪名荘に秦成重という田堵がいた。成重は荘田九町歩を二年間にわたって隠田(おんでん)し、地子米(じしまい)九〇余石を未進した。そこで東大寺は地子米のかたとして成重の収穫直前の作田を差しおさえたところ、成重はそれをも無視して一五〇余束の稲を刈りとってしまうという事件が起きている。
九町歩以上を耕作する、といえばむろん大名田堵である。成重は、小名田堵や浪人を集めて、この田地を経営していたのであろう。その成重が、地子米を未進したばかりでなく、荘園領主の制札にも抵抗した理由はわからないが、しいて推測すれば、地子米の率に対する抵抗であったかもしれない。成重が請負っていた九町歩に対する二カ年の地子米が九〇石であったとすると、一段別一カ年五斗(これを五斗代という)ということになる。五斗代の地子は荘園によってめずらしくはないが、このころ、三斗代から五斗代に地子をひきあげて、田堵と荘園領主との間に紛争を起こした荘園も多い。天喜三年猪名荘では、成重のほかにさらに「村々田堵」らが、いろいろ口実をもうけていっせいに地子米を未進したといわれる。その背後には、地子率の問題があったのかもしれない。
それはともかく、こうした田堵の抵抗は、大きな立場からみれば、不安定な耕作権しかもたない田堵が、より安定した耕作権の獲得をめざすたたかいの一環であったといってよい。さまざまなたたかいを通じて、一二世紀に入ると、田堵は一般に名主(みょうしゅ)とよばれるようになり、耕作田地の占有権と耕作権は、より安定したものになる。