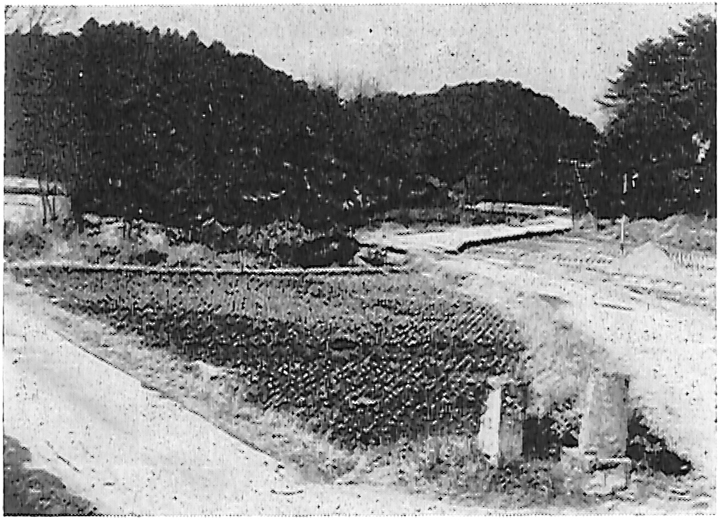さて以上のことから、このむらの実態と動向を要約してみよう。農地改革後自作農になったものを含めてこのむらの農家は、将来への希望にもえて農業経営に精をだした。しかしながら山林採草地の所有関係や経営耕地面積の規模は変わらなかったので、農業経営上の優劣は最初からあり、統計数値のうえでは昭和二十六年以降にそれがあらわれてきた。すなわち、農業経営基盤のしっかりした改革前からの旧自作農や、改革後の新自作農のうち経営耕地面積の比較的大きなものは、経営意欲の高揚によって生産力を高めてきたし、またそれによって農業収入をふやそうと努力した。他方、経営基盤の弱いものや農業経営に力を入れないものは、自己の経営を前進させることができず、経営耕地面積を減らすものもあらわれ、いわゆる農民層の両極への分化分解が進んだ。昭和三十一年八月現在で、このむらの農家を右にみた実情をもとにして分類してみると、(イ)雇用労働の多い富農とよぶことができる農家二戸、(ロ)中農の上層が八戸、(ハ)自家労働で手いっぱいの農業経営をする中農二七戸、(ニ)他の家に雇用されることの多い貧農であり、かつ農業労働者とみることのできるもの一四戸、(ホ)種々の雇われ労働をする農村労働者五戸、(ヘ)小商人四戸、(ト)職人一戸、(チ)不明一戸ということになるが、両極分化は(ハ)の層を分岐層として進行したのである。そして(ハ)層から(ロ)層へ、さらに(イ)層へ向って上昇しようとする農家にはふたつの類型をみるのである。そのひとつは旧地主自作農であり、改革過程においてもまた改革後においても、従来の経営基盤と社会的力をもとにして農業経営を前進せしめようとする農家群であり、これを旧自作上昇線上の農家とよぶことにする。他の類型は、改革前に小作地を多く耕作しており、改革後は自作ないし自小作農になって、新たな意欲をもち経営の前進を図る新自作上昇線上の農家である。このふたつの類型の農家は、同じ方向へ前進しようとしているのではあったが、それらの前進の仕方に異なった点があり、目標は同じでも異なったふたつの道を歩んでいた。
これらのふたつの道の相違に眼をくばりながら、農業経営をみていきたい。農業労働力として人を雇う農家は(イ)(ロ)(ハ)の各層にあるが、そのうち旧自作上昇線上の農家が多い。これらのものは伝統的な経営様式を維持し、米作と野菜作りを主としたが、この場合経営耕地面積二〇~二五反歩程度、雇用日数二〇〇~三〇〇日のところに経営前進の限界があり、そこで停滞したように思われる。新自作上昇線は、(ハ)層から、経営耕地面積でいえば七~一〇反層からでており、一〇~一五反層に向かって上昇し、昭和三十一年には二戸もしくは三戸がすでにこの層に到達した。新自作上昇線上の農家は、米作においても新しい技術をとり入れることに積極的であり、また有利な種類の作物や施設園芸作物あるいは酪農などに、このむらとしては最初にとりくんだ生産力的農家である。これらの農家は、家族ができるだけ手いっぱい働き、どうしても手がたりないときに人を雇うのであって、その雇用日数も年間二九日を越えることはなかった。そして家族の手があけば、手のたらない農家やその他の仕事に雇われて日当をかせぎ、たくましい生活力を発揮した。