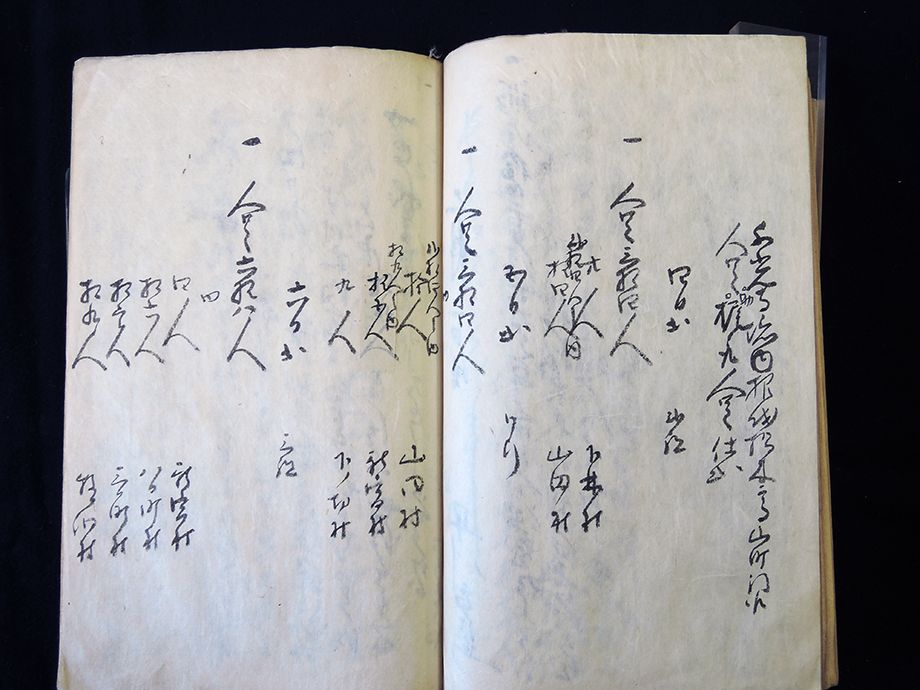
3-2-(3)-1 千光寺境内根伐り人足
千光寺境内根伐り松木高山町引取り
入足助梶取人足仕出し
四日分 弐組
一 人足三拾四人
廿 人 下林村
拾四人 山田村
五日分 同断
一 人足三拾四人
拾 人 山田村
拾五人 新宮村
九 人 下ノ切村
六日分 三組
一 人足六拾八人
内
四 人 新宮村
拾六人 八日町村
拾壱人 三ヶ町村
拾九人 牧ヶ洞村
拾三人 藤瀬村
五 人 福寄村
高当り分遠方ニ付き減
〆
右は中橋御普請ニ付き、入用木三福寺村地内字上野より引取り
人足の節、元方へ諮(はか)り差向け候間、則ち切口割の通り手馴れ候
人足相撰び、名主附添ひ、暁七ッ半時、右場所へ向け差出すべ
く候。尤も、賃銭の儀は追って沙汰有るべき条、其の意を得(う)べ
く候。此の廻状受印令(せ)しめ、早々相廻し、留村より返すべきも
の也。
未
十一月二日
其の処山内ニ於(お)いて根伐り申し候中橋御普請木山出し方入用ニ
付き、差遣はし置き候荢綱(おづな)急ニ入用ニ候間、明三日朝四ッ時分
迄遅滞無く差遣(さしつかわ)すべく候。
一兼(かね)て木取り申渡し置き候橋板長弐間の分出来合ひだけ残らず一
両日中差出すべく候。勿論残り候分も成丈ヶ(なるだけ)出精いたし、木取
り出来次第差送り申すべき者也。延引ニおゐては、差支(さしつか)えニ成
るべき条、心得違ひ致す間敷(まじ)きもの也。
未十一月二日 宮村
名主
組頭
(註)この部分は、御役所の工事担当役人から、橋板の木取りを任されている宮村の
名主・組頭あてに出された、製品出しの督促状の写しである。
一 人足百五拾七人
冬頭始め上り通り 西ノ一色迄□
右は昨朔日(ついたち)迄ニとの□□□□□□□□□□ニ付き、触人足差遣(さしつかわ)
し申すべき間、上触れ差出し候処、出し方丸一日滞り候ニ付き、
明三日出人足猪又□□の通り触れ出し候。尤も文書、例の通
り也。
早出
十一月三日 晴 斉藤弥右衛門
一中橋御普請木、千光寺より高山町へ引取り候ニ付き、桐生村役
人より敷木(しきぎ)の義願ひ出候間、新張村御林木の内より根伐り相渡
し候様、其の村役人・山見宛の免状、桐生村名主へ相渡し遣す。
早出
同 四日 晴 田近孫蔵
一千光寺境内ニて根伐り致し候木品、三福寺村の内字上野より高
山町一統ニて引取り候後、則ち高山町七組ニ割合ひ、其の組木
数五本ヅ々、今日より明後六日迄ニ引取り申すべく、右附添と
して□□□□□(人名)・奥田文右衛門・大池織右衛門、今日出役。
当榑木出し方延引差支(えんいんさしつか)え相成り候ニ付き□□□これ有る問、
明五日五ッ時迄、遅滞無く罷り出るべく候。不在ニ於(お)いては、
急度申付け候条、其の意を得べきもの也。
十一月四日 御普請所
宮村
名主
与頭
同 五日 晴 朝雨
早出
上村善助
一千光寺境内山樽木
附添として出役 斉藤弥右衛門
指田要蔵
田中唯右衛門
庄村岡右衛門
一大樽木、兼て組うけの通り郷組仕組共
午ノ中刻滞り無く着木いたし候事。
早出
同 六日 小雪 斉藤弥右衛門
一下保村千光寺境内ニおゐて根伐り桁木、其の外樽木、千秋万歳、
日出度御普請小屋場所至着の事。
一右置き込み方諸締り附添ひとして出役
早川市左衛門
小榑大助
長瀬□六郎
玉井兵左衛門
岩水栄蔵
宮村名主
新六
右のもの儀ハ、糺明の儀これ有るニ付き、御吟味中宿預り仰せ
付けられ候間、慎み置かせ申すべしと仰せ渡され、畏み奉り候。
川原町
宿
源右衛門 印
未
十一月六日
一千光寺境内木皆着し、御附添として同寺住僧、御普請小屋場所
へ罷り出候事。
早出
同 七日 晴 上村翁助
早出
同 八日 晴 田近孫蔵
早出
同 九日 雪 上村翁助
早出
同 十日 晴 早川市左衛門
早出
同十一日 晴 斉藤弥右衛門
早出
同十二日 晴 田近孫蔵
早出
同十三日 晴 上村翁助
相尋ねる条これ有り候間、明十四日遅滞無く罷り出るべきもの也。
高山
御普請所
新宮村
名主
早出
同十四日 雪 早川市左衛門
早出
同十五日 晴 斉藤弥右衛門
早出
同十六日 晴 田近孫蔵
早出
同十七日 雪 上村翁助
一宮村山内中橋御普請木根伐り方取締りとして、田近孫蔵出役。
早出
同十八日 早川市左衛門
早出
同十九日 斉藤弥右衛門
早出
同 廿日 田近孫蔵
朝雪 早出
同廿一日 夕晴 上村翁助
此の度中橋普請木数見立て、此の者共差出し候間、山見案内致
し、差出す様取計ふべきもの也。
高山
未十一月廿一日 御普請所
久々野組
大西組
早出
同廿二日 晴 斉藤弥右衛門
早出
同廿三日 晴 田近孫蔵
朝雪 早出
同廿四日 曇 上村翁助
早出
同廿五日 早川市左衛門
早出
同廿六日 晴 斉藤弥右衛門
早出
同廿七日 晴 田近孫蔵
一早川市左衛門・上村翁助今朝高山出立、夫々ニ立出致し候事。
同廿八日 晴 記載なし
早出
同廿九日 晴 斉藤弥右衛門
早出
十二月朔日 晴 田近孫蔵
早出
同 二日 晴 斉藤弥右衛門
早出
同 三日 同 田近孫蔵
早出
同 四日 同 斉藤弥右衛門
早出
同 五日 雪 田近孫蔵
早出
同 六日 晴 斉藤弥右衛門
一吉田村手伝人足弐人差出し候事
同 七日 晴 田近孫蔵
早出
同 八日 晴 斉藤弥右衛門
中橋普請入用木、其村ニて根伐り致し候分、早々差越し申すべ
く、此の書付相廻すべきもの也。
中橋
未十二月八日 御普請所
宮村
名 主
組 頭
世話人
早出
同 九日 晴 田近孫蔵
一升形岩切、昨八日迄ニ出来候旨、与頭福嶋屋宇兵衛届出の事。
早出
同 十日 晴 斉藤弥右衛門
一御郡代様中橋より升形岩場所見分御案内致し、斉藤・田近・早
川並びニ肝煎五人召され候。
早出
同十一日 田近孫蔵
一鍛冶橋両詰面枠、今朝迄出来ニ付き、普請小屋取払ひ申すべき
旨、右掛り□□作蔵申し出候事。
同十二日 晴 斉藤弥右衛門
同十三日 晴 田近孫蔵
覚
一檜
ひば 長三間 六寸角以上 四間分
是れハ橋板ニ用ひ候分
一同 長さ九尺 巾六寸以上 八間分
厚さ三寸
是れハ右同断
右は中橋普請入用木品承り取立て、来ル正月廿日頃高山着致さ
せ申すべく候。尤も、取立ての節、山内不届の儀これ無き様、山
見名主度々見廻り、急度締り致すべく候。此の書付請印令(せ)しめ、
相返すべきもの也。
中橋
未十二月十三日 御普請所
宮村山見
名主
与頭