この点では、一九世紀後半以降本格的に始まった考古学研究の中で、縄文文化など石器時代の研究が、歴史学の枠から離れた条件のもとに、遺跡・遺物の調査という実際的な認識を原点として出発したのに対し、古墳時代の研究が、既成の歴史学の体系を苗床として育てられたという根本的な相違があった。縄文文化を先住民であったアイヌ系の人びとの文化遺産とする仮説が、比較的抵抗なく一つの学説として受け入れられたのに反して、古墳の形成と分布を大和朝廷の成立過程と切り離して考察することができなかったのは、歴史意識において『古事記』、『日本書紀』を事実として扱わねばならなかったからである。文献資料の信憑性について厳密な考定を経ることなく、また天皇陵に治定された大規模な前方後円墳の実態を調査する機会も遠ざけられた結果、二〇世紀の中葉まで核心をつく研究は進展しなかった。
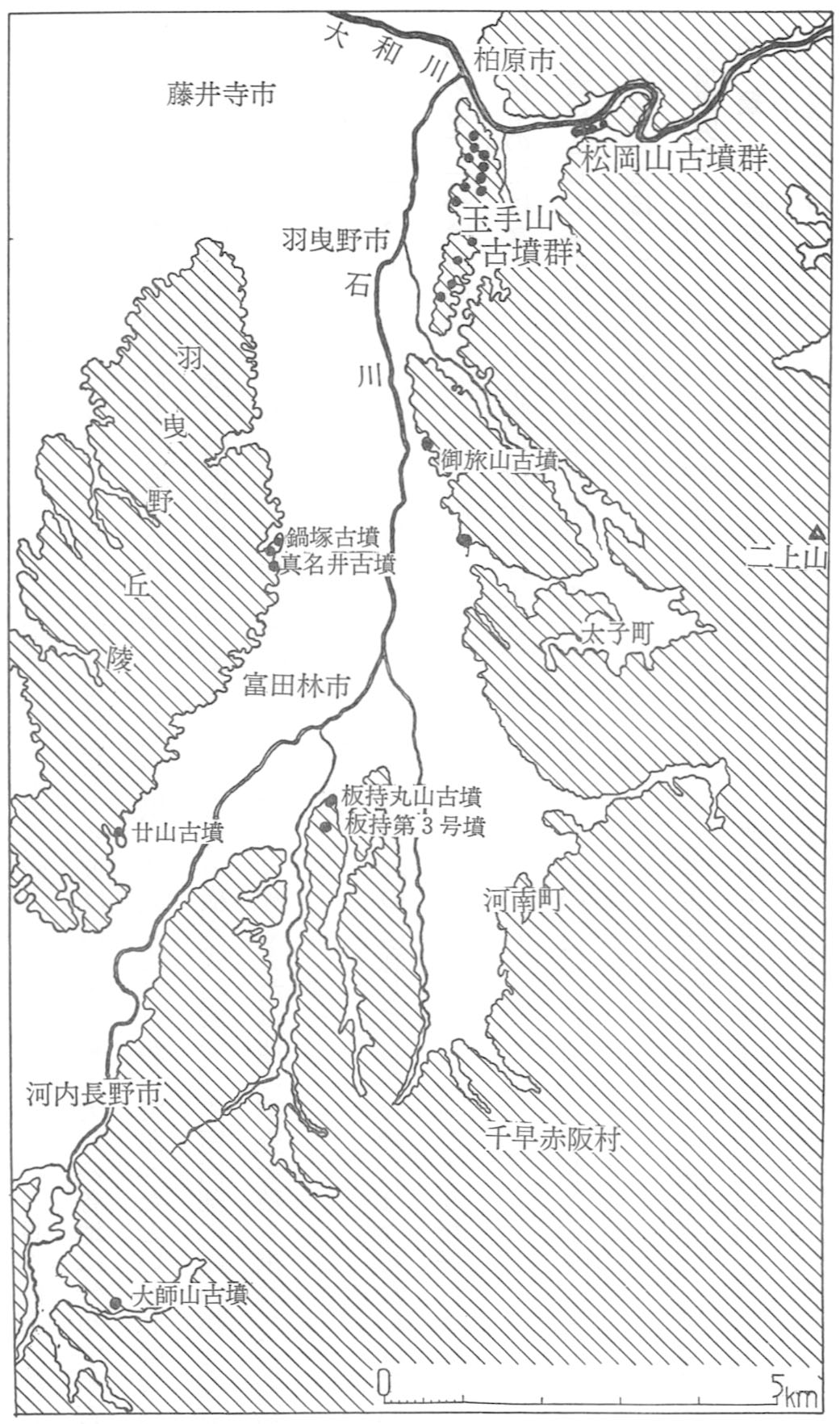
たとえば第二章で取り上げた高橋健自博士の『古墳と上代文化』の中で、「古墳と陵墓」の項に「陵墓は我が皇室祖宗の御奥津城であることは申すまでもない。而して古墳は我々日本民族祖先の奥津城であるから、上古における陵墓の制は古墳の構造型式の時代観に対して有力なる暗示が投ぜられ、古墳の研究は陵墓を調査し奉る上に必然の関鑰(かんやく)(筆者注、扉をあける鍵のこと)でなければならぬ」と指摘していて、当時の風潮をよく反映している。その結果、墳墓を営む集団の中においてさえも上下の身分を異にした階層が存在したことを前提として「皇室に於て或る型式の陵墓を営まれつつあった頃には、皇族ならぬ貴族も略同型式の墳墓をおこしたことは容易に首肯されるであろう」と言及した背景にはすでに強い先入観がある。陵墓の被葬者としての皇族と、古墳の被葬者としての貴族を、身分的に区別した社会的通念を学術研究に際しても打破することができなかったのである。