廿山古墳は真名井古墳から南南西に約三・五キロ離れて、廿山集落の入口にあたる羽曳野丘陵東縁に位置し、東方は甲田から錦織に連なる幅広い台地を介して石川を臨む標高一三二・七メートルの支脈上に営まれた前方後円墳である。全長約五〇メートル、後円部の直径約四〇メートル、同高さ六・五メートル、前方部の幅約二五メートル、同高さ三・五メートルの規模をもち、前方部は真名井古墳と反対に東を向いている。墳丘の表飾施設については後円部の西南斜面の一部に葺石があるのを認めたほか、雑木が繁茂していてまだよく分からないので、今後の調査で埴輪の有無を検討する必要がある(171)。
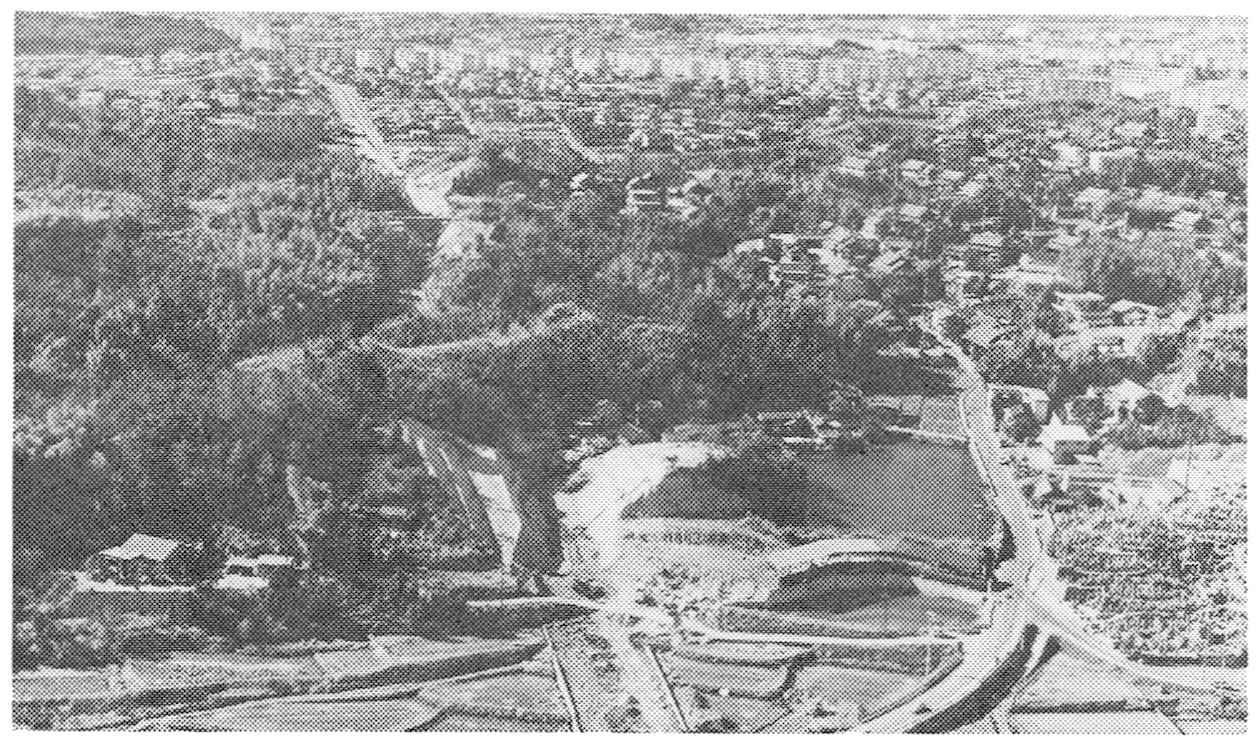
内部構造に関して梅原末治氏は概報の中で「塚穴(石槨)」があったという土地の所伝を記しているが、一九五五年ごろ、後円部盗掘孔の一部が開墾された際に精査したところ、黄褐色粘土質の地山の上には、同質の山土が広く堆積しているのみで、竪穴式石室が構築されていたことを推測させるような板石片の類は全く検出しなかった。前方部とは反対の方向にあたる後円部西側の斜面のかなり上部に、礫石を充填した排水溝の出口かと思われる遺構が認められたので、主体部の施設は全く破壊されてしまった可能性が強い。しかも石室が存在した手がかりは認められなかったから、本来この廿山古墳の主体部は排水溝をともなう粘土槨で、墳丘の長軸線に平行して長く営まれていたのではないかと考える。
出土した遺物として現存するものは九本の銅鏃にすぎないが、すべて「定形式」の中の有茎「定角有箆被式」という分類に属するもので、後藤守一氏は日本出土の銅鏃の中で最も複雑なものと表現したことがあり(後藤守一「原史時代の武器と武装」『考古学講座』一九二六年)、型式変遷からみて銅鏃の盛行した前期の終末の段階に位置づけられる。これと同形の銅鏃の出土例は少なく、わずかに神奈川県平塚市真土の大塚山古墳から出土した四三本の銅鏃の中に数例が含まれているにすぎない。大塚山古墳は円墳で粘土槨をもち、銅鏃のほかに神獣鏡一面、鉄刀、巴形銅器三個からなる前期末の古墳である。