つぎに氏は家形石棺の変化の動向を分析して、三つの画期があったとする。第一は「畿内に家形石棺が発生した段階」で、まず奈良盆地東部で二上山石材を用いて造られていた舟形石棺が、九州の刳抜式石棺の影響をうけて家形石棺に形態変化した時期である。これが前述の三輪型にあたり、二上山産ピンク凝灰岩の石棺として畿内に六例が存し、その中河内例としてはただ一例が藤井寺市沢田の長持山2号棺(279)にあるのみで、その他はことごとく奈良盆地東辺に分布しているという。第二は「畿内各地で家形石棺の製作が行なわれた段階」で、従来主座を占めてきた長持形石棺と交代した時期でもある。すなわちこれを六世紀代の「型」と称することができ、その背景として畿内各地域で豪族が分立した事情を挙げている。各地域で二上山白色凝灰岩を石材として用いる上で「明確に量的な差」があり、石材を採掘する際の規制の存在を想定している。
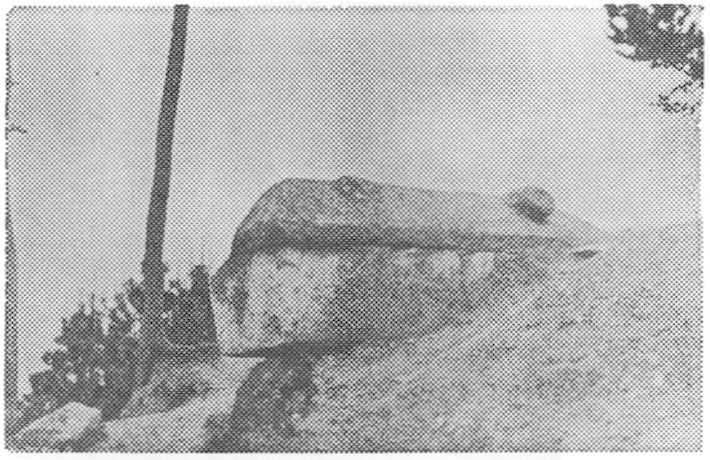
氏はこの問題についてつぎのように説明する。
この段階(六世紀)ではじめて、畿内各地域の有力豪族はそれぞれ石工集団を組織して独自の型式をとる家形石棺の製作を開始し、石棺の型式というかたちで氏族の個性を表現するようになったが、彼らの間にある、一つの政治的な秩序づけが石材の量的な差としてあらわれたと推定することができるのである。そして、二上山石材の利用で最も優位にあったのは南大和型であり、この「型」と同一型式の播磨型は、遠く竜山に石材産地を求めていたのである。(四三頁)