ところがここで、またまた急変がおきた。明応二年(一四九三)四月二二日、河内出陣中の将軍足利義材にかえて、香厳院清晃(こうごんいんせいこう)(のち義澄(よしずみ))をたてる政変がおきたのである。同時に畠山基家も赦免され、畠山政長に代って河内守護に任ぜられた。高屋城の攻防戦は、政変によって、攻守が逆転することになった(中世六六)。
政変の仕掛人は、管領細川政元であった。政元は義材と意見があわず、河内陣にも出陣していなかった。政元は前年あたりから政変の計画をねりはじめており、延徳四年(一四九二)正月には畠山基家の使者と接触したこともある(『雑事記』延徳四年正月二七日条)。そして義材の河内出陣後、政元の計画はいよいよ動きはじめ、いわゆる根回しもひそかにおこなわれた。高屋城攻撃がはじまる直前の三月二〇日には、政元の密使が越智氏のもとを訪れており、『大乗院寺社雑事記』は政変の一カ月も前に新将軍がたつという噂と、基家方越智・古市氏が大喜びであることを記している(『同』三月二一日条)。
政変の報が河内に伝わると、大きな混乱もなく、攻守が交代した。今は前将軍となった義材の命令をうけて出陣してきていた大名衆は、新将軍への奉公を誓い、将軍直属の奉公衆ともども撤退をはじめた。赤松政則は、細川政元と縁者になったばかりであったが、誉田城(高屋城か)に入って、直前まで敵であった畠山基家に協力することになった。
一転して攻撃をうける立場になった足利義材と畠山政長は、正覚寺の陣を固め、畠山尚順は藤井寺の陣を維持して、畠山基家や細川政元勢の攻撃に備えた。
閏四月のはじめ、細川政元の丹波守護代上原元秀(うえはらもとひで)らが、政長を討つため河内に下った。閏四月六日、七日の合戦で藤井寺の尚順は敗れて正覚寺に合流した。六日には富田林市域の廿山城も没落したことが、京都に報告されている(『後法興院政家記』明応二年閏四月一一日条)。前述の両軍の布陣の史料には廿山城は記されていないが、嶽山・金胎寺城の基家方に対抗するため、政長方の軍勢が籠っていたのであろう。同じころ、義材の河内親征を機に復活していた筒井氏ら大和の政長方国人も、あいついで自焼没落した。
こうして正覚寺の陣は孤立を深めた。閏四月二一日、政長たのみの根来寺衆ら紀伊勢は、堺付近で赤松政則の軍に敗れた。閏四月二五日、正覚寺の攻撃がはじまった。政長方は尚順をようやく没落させたものの、政長、河内守護代遊佐長直らは、切腹して果てた。なお足利義材は捕えられ、京都に送られた(中世六六)。
多数の大名勢力を動員しておこなわれた足利義材と畠山政長の河内出陣は、幕府からみれば不法に河内支配をつづけている畠山基家を討ち、幕府による秩序と、将軍の権威の回復を目ざしたものであったが、こうしてまったく逆の結果をもって終った。政長の死によって、畠山家の家督争いも、河内はじめ大和・山城でつづいてきた応仁の乱の延長戦も、いったん終止符をうった。なお、両畠山軍を撤退させたあと南山城を自治的におさめてきた山城国一揆も、明応の政変によって解体してしまった。
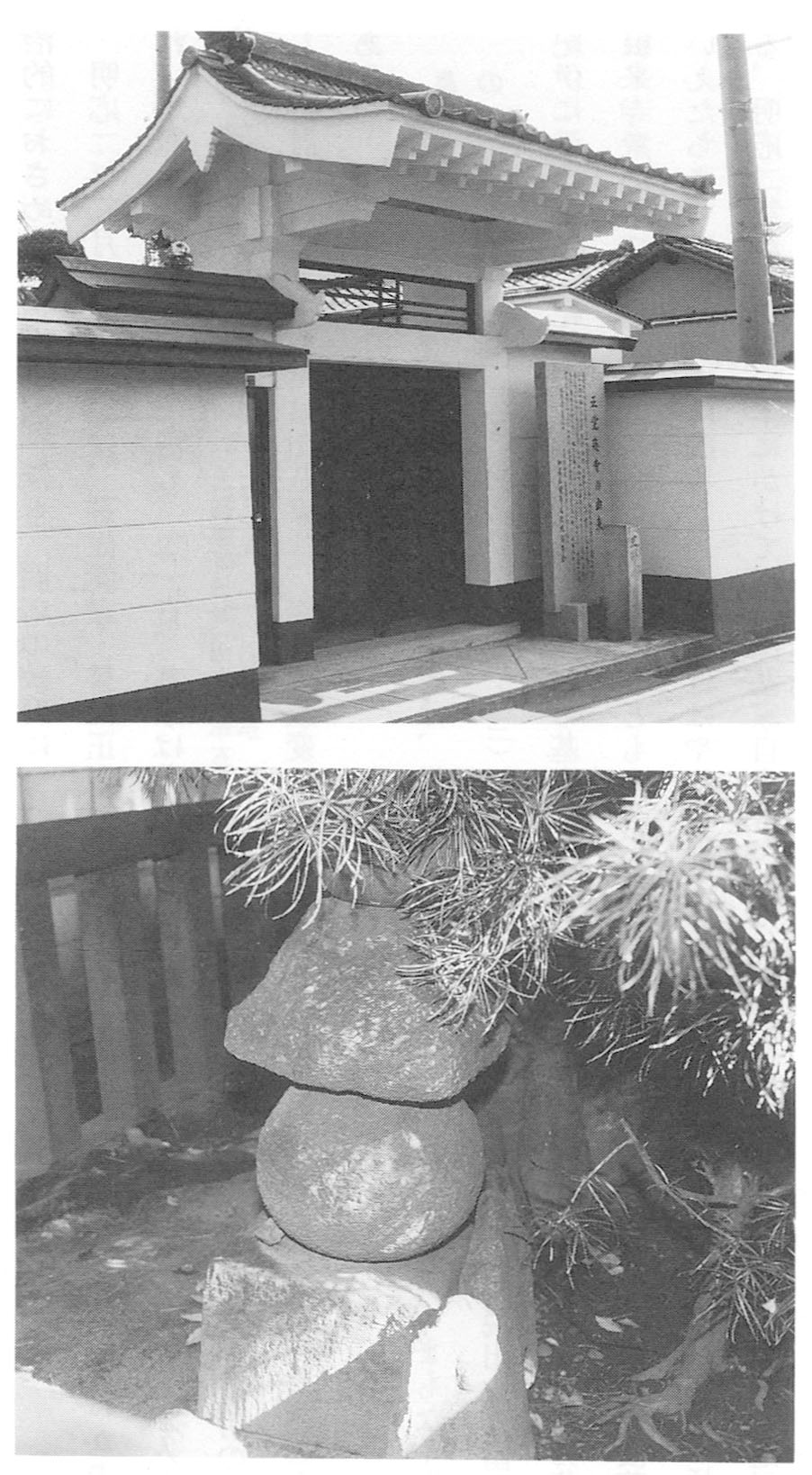
明応二年五月、畠山基家は、遊佐就家・誉田正康・甲斐庄氏ら有力被官など二〇〇〇人ばかりをひきつれ、華麗な行装をくんで上洛し、二一日、基家は幕府に出仕した。大和の越智氏も一〇〇〇余人をつれて上洛し、同時に幕府に出仕した(『蔭涼軒日録』明応二年五月一九・二一日条ほか)。事実上の南河内支配をつづけながら、幕府の敵、朝敵として追討されようとした畠山基家は、明応の政変によってその立場が逆転し、はれて河内守護となったのである。