1
慶応三年(一八六七)一〇月二二日、上総国山辺郡家之子村(東金市家之子)農、久保田長八の長男に生まれる。字(あざな)は重較と言い龍徳と号した。家は代々名主を勤め近隣に聞えた素封家である。
久保田家の当主は代々「長八」の名を襲ぐ習慣があったが(専蔵以後は襲名していない)、専蔵の父長八がどういう人物であったか、伝える資料がないので書きようがない。しかし、祖父長八については、久保田家の菩提寺たる家之子の妙宣寺にある墓碑に略伝が刻されているので、ほぼその経歴が分かる。それは、久保田市郎左衛門の名で文久元年(一八六一)七月に建てられたものだが、この市郎左衛門が専蔵の父で、後に長八を襲名したものと思われる。右の墓誌によって祖父長八のことを記してみると、彼は勤倹力行のすぐれた人物であったようで、久保田家を富有ならしめたのは、彼の力に負うところが多大であったといってもよさそうである。彼は武射郡本須賀村の小林弥次兵衛の子に生まれ、初名を荘五郎といったが、少年の頃将来を見込まれて、家之子村の久保田長八(専蔵の曽祖父)の養子となり、長八に実子がなかったために家を嗣ぐこととなり、高橋氏の娘を妻に迎えた。久保田家は農業のかたわら酒造業に従い、さらに製茶業まで手を伸ばしていたが、誠実で努力家の荘五郎はよく養父を助けて日夜懸命に家業にはげみ、家運をますます隆盛ならしめたのである。養父長八の死後は長八を襲名し、村名主をもつとめて村民をよく撫育した。彼はただ働き者というだけではなく、徳をもって人を信服せしめる力をもっていた。彼は妻との間に二男三女をもうけたが、家庭はきわめて円満であり、三、四〇人の使用人もよく信従していた。彼の墓誌に「君、天資易直方正ニシテ、家人ヲ導クヲ苟(いやし)クモセズ、家道雍睦(ようぼく)ナリ」と書かれてあるが、久保田家の立派な家風は彼によって築かれたといっても過言ではない。彼は万延元年(一八六〇)一二月一四日、病のため没した。行年六六歳であった。
さて、専蔵は妙宣寺内の墓碑銘によると、「資性剛毅ニシテ篤実、頗ル徳望ニ富ム」とあるとおり、なかなかすぐれた資質の持主であった。幼少の頃から学問好きで、土地の学者市川湫(しゅう)村に漢籍を学んだが、さらに本格的な勉強をしたいと考えた彼は、進んで東京遊学を志したのである。彼が上京した時期は不明であるが、明治の新機運に動かされ、青雲の志に燃えてのことだったろう。東京へ出た彼は碩学(せきがく)のほまれ高かった塩谷(しおのや)時敬について漢学を学ぶとともに、キリスト教牧師の木村熊二(島崎藤村の恩師)から英語を学び、また、小石川同人社に入り、その普通科を修了した。さらに大学南校(江戸幕府が神田一ツ橋に創立した開成所の後身で、東京帝国大学の前身)に入り、修学したという。
こうして学問を身につけた彼は、郷里に帰り妻を迎えることになった。妻となったのは山武郡福岡村鈴木孝太郎の二女とも子である。彼女のことは妙宣寺の専蔵ととも子の墓碑にしるされているが、一六歳で嫁いだとあるので、明治二一年(一八八八)に結婚したことになる(とも子は明治六年二月一〇日の生まれである)。この年専蔵は二二歳であった。とも子は「資性明朗ニシテ不撓(ふとう)、頗ル憐慈ニ富ム」(墓誌)というような女性で、いわば良妻賢母の典型のような人であったから、専蔵はよき同伴者を得たことになる。しかし、家業は酒造業・製茶業のほか養蚕までやっていたので繁忙をきわめ、使用人も五〇人位いたということだから、うら若いとも子の苦労も容易なものではなかったことであろう。
2
専蔵は家業に精励したこと勿論であるが、村のトップ的地位にある彼は公職にも力をつくさなければならなかった。明治二五年(一八九二)二六歳の彼は推されて区長の地位に就いたが、三一年(一八九八)には公平村村会議員に選ばれ、それから引続き四期その職を勤めることになった。人望の厚かった彼は、三二年(一八九九)五月には公平村長の重任を担うこととなり、三三年(一九〇〇)一二月まで村政にたずさわった。翌三四年(一九〇一)には、ふたたび区長となり、さらに郡会議員に選ばれ、かくて彼は約一〇年にわたって、地方政治の進展につくし、働きざかりの年齢を迎えたのである。
明治三六年(一九〇三)九月、千葉県会議員の選挙が行なわれるや、彼は衆望を担って憲政本党から立候補し、見事に当選の栄を得た。この時、同村の稗田由巳(別項参照)と肩をならべて同じ党から出て、二人ともに当選したのであるが、これはきわめてめずらしい事例であった。県会議員となった彼は教育問題に熱心に取り組んだ。特に東金町に県立高等女学校を設置する件については、積極的に行動し、実現のはこびに漕ぎつけたのである。こうして、四〇年(一九〇七)九月までその任を全うしたのである。
県会議員を退任後はしばらく家業に専心したが、大正二年(一九一三)になって、三度区長の職につき、公平小学校の校舎新築のため大いに尽力したことは、土地の人びとのよく知るところである。そのほか、所得税調査委員にも挙げられ、その議長を兼ねて働いたことも書き添えておきたい。
また、彼は財政金融の面にも明るく、山武銀行取締役・山東合資会社々長等民間企業にも関与してその手腕を発揮している。
区政から初まり、村政・郡政県政に携わること実に四〇年に垂々(なんなん)とする間、よく地方自治の振興を計り、地域の産業経済・教育文化・交通等の発展充実に努めた功績は誠に偉大なるものがある。
家庭人としての專蔵はよき妻にめぐまれ、二男三女をもうけ、長男勝弥は東京大学に学び卒業後教職の道をえらび、栄進して県立成東高等学校長となり、父の名を恥かしめることはなかったけれども、専蔵に取って不幸だったのは、妻とも子に先立たれたことであった。すなわち、とも子は大正一三年(一九二四)一二月一一日、五一歳をもって病没したのである。子どもたちも仕上がり、これから老後を楽しもうという時であったのに、かなしいことであった。専蔵にとっても深い痛手であったろう。
専蔵は剛毅な人であったが、反面、篤実で人情にあついところがあり、人の面倒もよく見たので人望があった。彼は妻に後れること五年、昭和四年(一九二九)六月一三日、享年六三歳で長逝した。
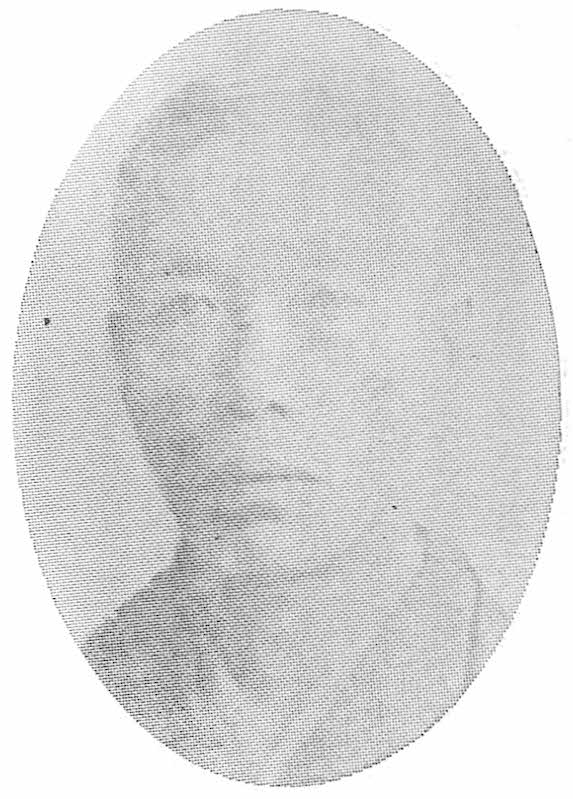
久保田専蔵
【参考資料】
久保田専蔵墓誌
(東金市家之子妙宣寺 久保田家墓地)
先考名ハ専蔵、字は重較、龍徳ト号ス。慶応三年(一八六七)十月二十二日、久保田長八ノ長男トシテ生ル。資性剛毅ニシテ篤実、頗ル徳望ニ富ム。学ヲ好ミ笈(きゅう)ヲ東都ニ負ヒ、塩谷(しおのや)塾ヲ卒ヘ、大学南校ニ学ブ。齢二十二歳ニシテ公平村長ニ就任、三十七歳ニシテ千葉県会議員ニ選バレ、県政ニ参与ス。町村制施行以来連続六回村会議員ニ選バレ、二十四年間孜々(しし)トシテ村治ニ尽ス。此ノ間、所得税調査委員・地租修正委員ニ挙ゲラレ、其ノ議長ヲモ兼ヌ。他面、山武銀行取締役・山東合資会社社長・日本薪炭株式会社社長ニ就ク。村政県政税政財界ニ活躍シ、功績見ルベキモノアリシハ世人ノ認ムル所ナリ。
配(はい)とも子トノ間ニ二男三女アリ。長男勝弥家ヲ嗣ギ、二男重威夭折、長女幾美(きみ)・次女志可(しか)・三女図和(とわ)ハ、ソレゾレ良縁ヲ得テ他家ニ嫁ス。趣味ハ読書詩作、中年ヨリ酒ヲ嗜ム。昭和四年(一九二九)六月十三日、病ヲ獲(え)テ逝ク。行年六十三歳也。
先妣(ひ)名ハとも子、明治六年(一八七三)二月十日、山武郡福岡村鈴木孝太郎ノ次女トシテ生ル。資性明朗ニシテ不撓(とう)、頗ル憐慈ニ富ム。齢(よわい)十六歳ニシテ先孝専蔵ノ配トナル。当時久保田家ハ故祖長久ノ営ム所ノ酒造業・製茶業及ビ大農業ニ従事シ、使用人ハ五十名ヲ超ユルコトアリ。家勢繁忙ヲ極ム。鶏鳴ニ起キ、深更ニ臥シ、真ニ帯ヲ解キテ寛(くつろ)グノ寸暇ナシ。然モ弱年婦女ノ身ヲ以テ其ノ大任ヲ完ウシ、加フルニ、数人ノ義弟数人ノ子女ノ教養看護ニ誠意ヲ以テ竭(つく)ス。其ノ精励其ノ辛酸、実ニ婦人ノ亀鑑トイフモ溢美(いつび)ノ言ニ非ルベシ。遊芸ヲ愛シ、三絃長唄ニ長ズ。
配専蔵ニ先ツコト数年、大正十三年(一九二四)十二月十一日、病ノタメ死ス。行年五十一歳也。
昭和十年(一九三五)六月
男勝弥建之