1
上総和算の発生地、東金市宿を中心とした地域には、板倉勝正(荒生)小安照隆(荒生)小川東庵(宿)川島良吉(西野)等の関流四和算家の頌徳碑が、それぞれの門弟達によって建立されている。しかし、その人たちの師たる関流七世植松是勝の碑はこの地にはなく、東京都金竜山浅草寺(せんそうじ)の境内に、幾度かの災厄を免かれ、百三十年の風雪に耐えて、最上流和算家会田安明の碑と相対して建っている。
この碑は「五瀬植松是勝先生明数碑」と呼ばれ、安政五年(一八五八)四月建てられ、撰文は藤良同、篆額(てんがく)並に書は中沢俊郷、刻は鈴木永年である。
撰文は漢文で記され、かなりの長文でもあるので、その内容を要約して述べると、
古今数学を説く人は多いが、最もこれを明らかにしたのは植松是勝先生である。先生は天才的な頭脳の持主で、幼少から数学を好み、関流六世日下(くさか)誠に学び、選ばれてその統を継承し、師を敬い師の姓をその号に用い、若くしてこの学の至宝と云われる「豁術一矩(かつじゅついっく)」及び「角術」の二書を著わし、しかもその公刊はしなかった。また、当時関流と相対した最上流会田安明の如きは取るに足らぬとし、最後に是勝晩年の長子に、師日下の通称貞八郎を命名したことを述べて撰文を終っているのである。
なお、碑陰には建碑の経緯について書き留め建碑の費用はすべて門下生が醵出したのであるが、その人数が多くて全てこれを挙げることが出来ないので、僅かに印可を受けた二七名の名を記したと、古川包教を筆頭に以下二六名の氏名が刻まれている。
これらの人達は、二・三のものを除き他は殆ど東金周辺の人々で、それぞれ名門豪家の子弟で、後年各地域で後進の指導や公共に尽力した人々であるので、参考のため左に記載する。
| (片貝)古川包教 | 子安義知 | 古川徳堯 | (片貝)猪野道教 |
| (川場)市東雅胤 | (北幸谷)鵜沢是一 | (家徳)佐藤邦寧 | (押堀)高宮泰徳 |
| (道塚)高橋清和 | 子安是房 | 古川勝明 | 布留川黎好 |
| 鈴木慶斎 | (真亀)桜井邦次 | 中村友清 | (荒生)板倉勝正 |
| (家之子)稗用是之 | 伊勢景寿 | 間崎義金 | 古川包幸 |
| 子安泰根 | 小高規保 | 古川勝継 | (薄島)馬島是保 |
| (家徳)安中道寧 | (匝瑳郡)渡辺知度 | (越中国)泊是規 |
是勝は寛政二年(一七九〇)上総国山辺郡真亀村(山武郡九十九里町真亀)農、中村覚左衛門の三男に生まれ、幼名を勝次郎、後に勝蔵とも云い晩年は英三郎と称し、是勝はその本名である。彼は五瀬という号を用いているが、これは彼の和算の師であった日下(くさか)誠いの本姓が五瀬氏であったので、それをもらって自己の号とするとともに、師日下への尊信を表明すると同時に、日下の直系の弟子たることを示したものと考えられる。なお、世間では是勝のことを「五瀬先生」と呼んでいた。
寛政一〇年(一八九八)九歳の時地頭妻木氏に伴われて江戸へ出て子守などしたと伝えられ、一旦帰国の後、一一歳の頃ふたたび出府し、妻木氏の若主人の供などしながら、数学を見覚えたと云われている。江戸麻布日ケ窪の関流六世日下塾に通い始めたのはこの頃と思われる。
文化八年(一八一一)二二歳の時、「豁術発明序」を著し、五瀬植松是勝子敬と署名したというから、その頃はすでに、山辺郡宿村(東金市宿)植松利右衛門の女ミヨと結婚して植松姓を名乗っていたことがわかる。
次いで「豁術一矩」を著わし、同年五月には、師日下誠から見題・陰題・伏題の免許状を授けられている。
文政三年(一八二〇)三一歳の時には、「角術新撰」を著わし、関流七世宗統植松是勝と記している。そして、郷里へ帰り家塾を開き、近隣の子弟を集めて教授に当たり、時には出稽古(出張教授)等も行ないながら、その前後合わせて約四〇年間この地にあって子弟の教育に当たったのである。
天保年間(一八三〇-四)は不幸が続き、養父母を相次いで亡くし、弘化三年(一八四八)には妻ミヨと死別したが、翌年後妻ナカ(大木氏)と結婚、嘉永元年(一八四八)五九歳で長男を儲け、先師日下誠の通称をそのまま貞八郎と名付けている。
安政五年(一八五八)六九歳の四月、明数碑は成り、文久二年(一八六三)四月一三日宿村で没した。享年七四歳、法名は久遠院円理日教と授けられ、宿村の共同墓地内に葬られている。
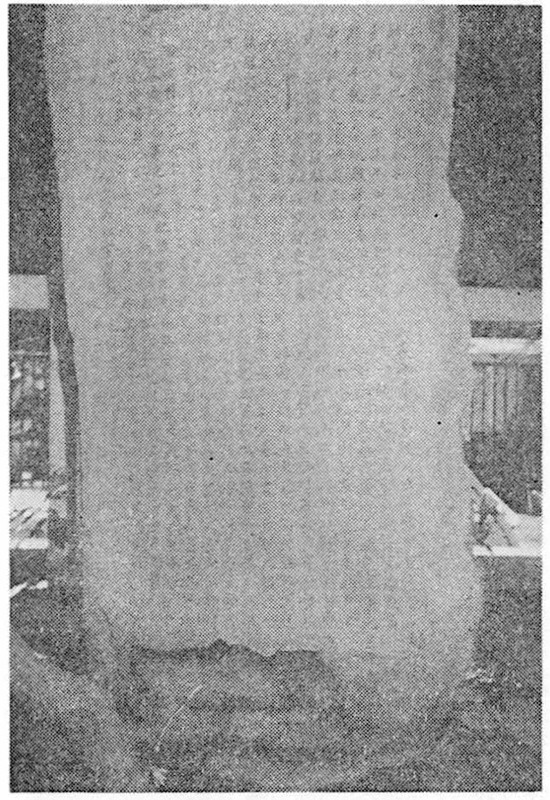
植松是勝明数碑(浅草寺)
2
是勝の明数碑が、郷里に建てられず、浅草寺の境内に建立された経緯については、藤良同の力があずかって大きかったようである。
良同は前名を布治帰一郎(「藤」は「布治」の音を一字に書きかえたものであろう。)と云い、上総国山辺郡片貝村中里(山武郡九十九里町片貝)の生まれで、古川包教の長子で、猪野道教の兄といわれている。漢学をよくし、出府して家塾を開いたが気の強い人で、むしろ経世家的な情熱の持主で聖堂の諸教授と意見を異にして常に争論をしていたと云う。古川姓を布治(藤)と換えた事情もわかるような気がする。彼は維新前後に流寓し、明治初年には東北で仕官していたというが、やがて郷里に帰り、明治二二年(一八八九)東金町北之幸谷の小川長右衛門(小川正義(別項)の父)が、菁莪義塾を開設するに当たり、迎えられて教鞭を執り、明治二八年(一八九五)七三歳で病没している。
明数碑の碑文は、前述のとおり藤良同が書いたものであるが、それは、碑文の文末に「嘗ツテ其ノ門ニ在リシヲ以テ、文ヲ予ニ請フ。因ツテ記ス」とあるので、良同が是勝の弟子であったことによることがわかるが、建碑にあたっては、良同の父古川包教の援助があったことを知らなければならない。もともと古川家は片貝(九十九里町)で城の内と称された名門の資産家で、その当主包教は学問もした人であって、是勝とも親しくしていたので、建碑については良同の蔭で相当の応援をしたらしいことが考えられる。本来ならば、碑は是勝の郷里に建てるはずのものであるが、是勝の家が無資産でその地位も高くないために、村の役人たちの了解が得られなかったという説もあるくらいだったから、やむなく江戸に建てたという事情だったらしい。しかし、天下の江戸の名刹浅草寺の境内に建碑するには、簡単には行かなかったであろう。この仕事の推進者であった良同は政治性もゆたかな男で、浅草花屋敷の開発人馬道六三郎とか、有名な侠客で浅草寺と関係の深かった新門辰五郎らとも昵懇(じっこん)であったといわれるから、そういう連中の力を利用して、建碑に漕ぎつけたものと想像される。
だいたい、植松是勝という人は、いわゆる学者気質の人で、名利を好まない、非社交的な性格だったらしく、それは弟子たちの記した文書にも、
「先生、性、名高の行を好まず、朋友小子に教授するのみ。著書上梓(じょうし)して世に公けにする事を許さず。」(「教学同門連名帳」)
とあるように、学究と教授一筋に生きていた人物である。したがって、建碑についてもあまり乗り気ではなかったらしいフシがある。碑文の中に、「先生、今茲(ことし)六十九、門人其ノ宝ヲ懐(いだ)キ海浜ニ老ユルヲ哀シミ、」と、建碑を企てた動機をのべてあるが、門人たちは今年(安政五年)六九歳を迎えた先生が、立派な宝物を持ちながら、このまま九十九里の僻地に埋もれてしまわれるのは堪えられぬほど哀しいのであると述べて、そして、さらに「百歳ノ後之レガ為メニ其ノ師ノ死センヨリハ、当年之レガ為メニ其ノ罪ヲ受クルノ愈(まさ)レルニ若(し)カザラン」と考えて、つまり、先生がたとえ海浜で百年の長寿を得られても、また、建碑などを好まない先生からどんな罪を受けようとも、自分たちは江戸の真ん中に立派な碑を創って、先生の業績を天下に顕彰したいのである、というふうに集議一致して、碑を建てることにしたのである、と書いている。すなわち、この碑は門人たちの深い師孝の情から生まれたものなのである。是勝もしあわせな人であったというべきであろう。
最後に、植松是勝は数学をどのようなものと考えていたかについて、述べておきたい。
「夫レ、数ハ天地ト共ニ開ケ、術ハ国家ト共ニ始マル。理学ノ最上ハ日用ノ第一是レナリ。身ヲ修メ家ヲ斉(ととの)フノ根本、数術ニ依ラズシテ何カアラン。」(「豁術発明序」)
これが彼の基本的な考えかたである。彼は「数術」という語を使っているが、それは実用第一主義の立場である。数術は修身斉家の根本であるとし、日用すなわち、生活の中に生かすべきものと考え、空理空論を排したのである。すなわち、生活に役立つ実用数学を目ざしていたのである。
当時の九十九里地域の庶民は、数理にはきわめて弱かった。のみならず、社会一般の風潮として、数学は銭勘定を教える卑しい学問として蔑視される傾向があった。したがって、和算家に対する風あたりも強かったのである。そういう雰囲気の中で、世人から白眼視されながら、敢然として生活に必須な和算を広めた是勝の功績はきわめて大きいものがあったのである。
附記
「東金市史・史料篇四」の第三十二篇学芸関係史料(三)Ⅳ、植松是勝・和算関係史料(一〇五〇-一〇六〇頁)を参照されたい。