一庵の生涯は不明なことが多い。彼は天保一〇年(一八三九)七月四五歳で東金で死んだことがわかっているが、それから逆算すると寛政七年(一七九五)の生まれである。生まれたところは仙台、名は群といい、字を輔仁と称した。父の名は分からないが、仙台では知られた医者であったという。母のことも兄弟のことも不詳である。一庵は痩(や)せた男であったらしく、後に「大廋(そう)生」と称したところを見ると、ひょろひょろと背の高い男だったのではなかったかと思われる。性格は狷介(けんかい)で相当激越なところがあり、したがって社交性に乏しく内攻的で協調性に乏しかったようだ。しかし、頭は相当によく思索的で文才もあった。父は医者であったが、一庵は医者となるのを好まず、儒者になることを望んでいた。そして、修学のため二〇歳を過ぎた頃、(文化一二年(一八一五)頃か)江戸へ遊学した。
江戸へ出た一庵は誰についてどういう学問をしたのであろうか。それについて、亀田綾瀬(りょうらい)の書いた「一庵先生墓碑銘」に、
「江戸ノ亀田梓(あずさ)ハ吾ガ師ノ胤(いん)ニシテ、師友ノ旧(よしみ)アリ。」
という一節があるので、綾瀬(梓はその名)の父たる亀田鵬斎(ほうさい)に師事したことが判明する。鵬斎は当時高名の儒者で折衷学派の泰斗(たいと)といわれた。折衷学派はいわば自由学派で朱子学とは反対の立場を取っていた。そして、例の寛政異学の禁にも反旗をひるがえし、鵬斎のごときもいわゆる寛政五鬼の一人として、幕府からは睨(にら)まれている存在だった。一庵がこの人についたことは興味がある。江戸へ出た一庵は「墓碑銘」に「豪気横溢(おういつ)シテ、毫亡推譲スル所無シ」とあるところから考えると、若気にはやって自負傲慢な風があったらしい。しかるに、鵬斎に対しては、流石の彼も降参したようだ。すなわち、「先子ニ贄謁(しえつ)シ、一見シテ意気投合シ、遂ニ下拝シテ弟子ト称ス。」(先子は死んだ父のこと。このばあい、亀田綾瀬(梓)が父の鵬斎をさしていう。なお、鵬斎は文政九年(一八二六)に死去している。)という風に直ちに弟子の礼をとったのである。鵬斎は奇行に富んだ反骨の人であったが、一庵も相似た性行の男であったことを思せわる。こうして、折衷学を修めた一庵はどの程度の学識をもっていたか、何冊かの著述を残しているけれどそれが伝わっていないので何ともいえない。しかし、綾瀬の記すところでは、経史百家の書に精通していたらしいから、相当のものであったようだ。鵬斎は詩人としても著名な人だったが、一庵も綾瀬が「気骨超脱シテ、気格高老」とその詩才をほめているので、詩人として一家を成していたかと思われる。
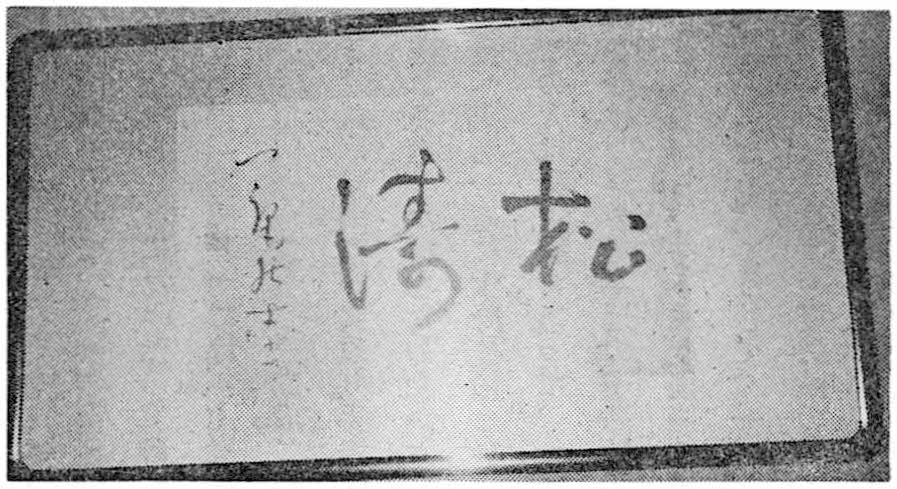
高橋一庵の書
ともかく、一庵は綾瀬のことばを借りれば、博大の学と俊邁の才を具有していたが、「意ヲ曲ゲテ人ニ従フヲ欲セズ」という孤潔の性格であったため、江戸でも目ぼしい地位を得るにいたらず、下総上総の間に流寓して、講学の業に従うようになり、やがて東金の地へ身を寄せることになったのである。それはいつごろのことであったろうか。「墓碑銘」には「上総ニ居ルコト十余年」とあるから、文政一〇年(一八二七)三二歳ごろのことだったのではないかと思われる。(亀田鵬斎が文政九年に死んでいるので、それが一庵の江戸を離れるきっかけをなしたかとも想像される)
東金へ来た一庵は大野豊治という人の世話を受けることになった。この人は素封家であって、一庵はその別荘に身を置いて豊治の庇護を受けながら、附近の子弟に学問を教えていた。「従遊益々多シ」とあるから、ある程度隆盛であったようだが、その具体的な状況は分からない。こうして、一〇年ほどの歳月を送っていたが、天保九年(一八三八)の夏病臥の身となり、翌一〇年七日一七日、四五歳の若さで、異郷でのさびしい死を遂げたのである。その最期にあたって、さすがに望郷の念押えがたいものがあったが、十年親しんだ鴇が嶺を愛することの深かった彼は本漸寺に骨を埋めてくれと遺言して永眠したのである。
一庵に妻子があったかどうか。あっても不思議ではないが、どうも独身で過ごしたらしく思われる。田波啓氏も「一庵には妻子がなく」(「東金文学散歩」)と書いている。それには、生活の問題もあったろうが、その性格にも素因があったかもしれない。孤愁の人というべきか。彼には「敬業堂詩文集」「南総十記」などの遺著があるといわれるが、残念ながら散佚して伝わっていない。敬業堂とは彼の書斎の名(別号)であろう。
一庵は臨終に、自分の墓誌を亀田鵬斎の子で生前親交のあった綾瀬に書いてくれるよう委嘱したが、その乞いを受けて綾瀬が執筆した「墓碑銘」が、彼の人物と生涯を伝える唯一の文献である。この碑文は、綾瀬の子鶯谷(おうこく)が編んだ「綾瀬先生遺文集」におさめられている。
一庵の墓碑は最福寺境内にさびしく建っている。
【参考資料】
一庵先生墓碑銘(原漢文)(東金・最福寺境内)
一庵、諱(いみな)ハ群、字(あざな)ハ輔仁、高橋氏、一庵ト号ス。仙台ノ人。父、謀ハ某、医ヲ善クスルヲ以テ名ヲ著ハス。
時ニ、一庵年己(すで)ニ長ジ、方技ヲ以テ家ヲ成スヲ喜バズ、儒術ヲ以テ世ニ見(あらわ)レント欲シ、経史百家ノ書ニ於テ、覧(み)ザルハ靡(な)ク、覧テ記セザルハ靡シ。其ノ貌清〓(ぼうせいく)①、衣ニ勝(た)ヘザルモノノ如シ。因ツテ、自ラ大廋(そう)生ト称ス。然レドモ、其ノ天ニ得ル所ノモノハ、孤狷崛強(こけんくっきょう)②ニシテ俗ト諧(とも)ニスル能ハズ。是ヲ以テ、屡(しばしば)困シ屡窮シ、終ニ屑々(せつせつ)トシテ人ニ随ツテ計ヲ作(な)サズ。
年二十余、家ヲ辞シテ西ノカタ江戸ニ遊ブ。時ニ、老師宿儒盟ヲ主(つかさど)リ世ニ当ル者数人。一庵華年盛気ヲ以テ臂(び)ヲ其ノ間ニ掉(ふる)ヒ、豪気横溢シテ、毫(ごう)モ推譲スル所無シ。嘗ツテ其ノ著ハス所ノ文十余編。先子③ニ贄謁(しえつ)④シ、一見シテ意気投合シ、遂ニ下拝シテ弟子ト称ス。是(ここ)ニ於テ、鋒鍔(ほうがく)⑤ヲ歛(おさ)メテ矜咳(きょうがく)⑥ヲ息(やす)メ、退イテ剔経(てききょう)ノ学⑦ヲ窮メ、卓然トシテ一家ノ言ヲ成ス。尤(もっと)モ思ヲ詩ニ鋭(あら)ハスコト始ヨリ終ニ至ル。格調屡(しばしば)変ジ、其ノ始ヤ、磊々(らいらい)落々、神王⑧気壮、尋常ノ詞藻ヲ以テ之レヲ例スルヲ得ズ。其ノ再変スルニ及ビテヤ、簡儼(かんげん)⑨ヲ以テ繁褥(はんじょく)⑩ヲ掃(はら)ヒ、雄渾(ゆうこん)ヲ以テ尖新ニ代フ。風骨超脱シテ気格高老、未ダ嘗ツテ風雅ノ幟(し)⑪ヲ奪ハザルナリ。其ノ学ノ博大ナルコト彼(か)ノ如ク、其ノ才ノ俊邁ナルコト此(かく)ノ如クニシテ、而カモ之レヲ用ニ施スヲ得ズ。己レ亦、意ヲ曲ゲテ人ニ従フヲ欲セズ。遂ニ去リテ両総ノ間ニ遊ビ、徒ヲ聚(あつ)メ経ヲ講ズ。
東金ノ大野豊治ハ学ヲ好ムノ士ナリ。乃チ之レヲ別荘ニ引ク。豊治贍給(せんきゅう)⑫シテ、子弟等ヲシテ従ツテ業ヲ受ケシム。
上総ニ居ルコト十余年、従遊益々、多シ。天保九年(一八三八)戊戍(つちのえいぬ)ノ夏、疾ニ遭(あ)ヒテ寝ヌ。自ラ其ノ起ツベカラザルヲ知リ、其ノ徒ニ謂(い)ヒテ曰ク、吾ガ志ハ古人ニ如(し)カザルニ非ズ、吾ガ才豈(あ)ニ今人ニ如カザランヤ。而シテ、此(ここ)ニ至リテ此(ここ)ニ死スルハ、命ナルカナ。故郷ノ路遼(はるか)ナリ。舁(か)キテ遺骸(いがい)ヲ帰(おく)ルモ及ブベカラズ。此ノ地ノ西、本漸ノ山ヲ吾甚ダ楽シム。卿等(けいら)、其レ是(ここ)ヲ以テ吾ヲ葬(ほうむ)レ。江戸ノ亀田梓ハ吾ガ師ノ胤ニシテ、師友ノ旧(よしみ)アリ。以テ墓誌ヲ勒(ろく)スルヲ請(ねがい)トナサン。此ノ外、吾又何ヲカ言ハンヤ、ト。乃チ、絶命ノ詞ヲ書シ、筆ヲ投ジテ逝ク。実ニ秋七月十七日ナリ。享年四十五。弟子等謹ンデ遺嘱ニ従ヒシト云フ。
其ノ平生ノ著述ハ、敬業堂詩文集・南総十記等数十篇アリ。豊治将(まさ)ニ理(おさ)メテ之レヲ木ニ袞(のぼ)セントス。交情始終渝(かわ)ラザルモノト謂(い)フベシ。嗟乎(ああ)、世固(もとよ)り其ノ具有リテ其ノ用ニ及バス、寿考碩大⑬ニ宜シクシテ、又克タザル者アリ。一庵ノ如キ、有為(ゆうい)ノ年ヲ以テ、卒(にわか)ニ夭(よう)ス、哀シイカナ。乃チ、系(つな)グニ銘ヲ以テス。銘ニ曰ク、嗟乎(ああ)、大廋生学博ク神(しん)清ク、其ノ遇ニ悴(やつ)レテ其ノ名ニ栄エタリ。
天保十年(一八三九)歳次己亥(つちのとい)秋七月
江戸 綾瀬(りょうらい)亀田梓(あずさ)撰
友人 海若寺大永書並篆額(てんがく)
注 ①やせてすんなりとしていること
②孤独で意地っぱりで、しかも屈しない強さのあること
③亡父
④進物をもってお目にかかること
⑤刀剣のこと
⑥誇らしい気持
⑦剔は解きわける意経典解釈の学
⑧精神がゆたかなこと
⑨かざりけはないが、きびしいこと
⑩複雑でわずらわしいこと
⑪目じるし
⑫経済的な面倒を見ること
⑬長老や勢力のある者