1
日勇は僧名(顕本法華宗)であり、存道はその号である。僧侶としては本義院日勇と称していた。彼は儒者としても名を知られていたので、儒学者日勇とも呼ばれていた。
日勇は東金市松之郷の本松寺(別項参照)の第一七代の住職をしていたが、生まれは東金ではない。江戸初期の宝永二年(一七〇五)尾張の名古屋で生まれている。そして、幼い時に名古屋の常徳寺という寺に入り、僧侶としての道を歩むことになった。この寺について、「名古屋市史」には、左のように書かれている。
「常徳寺は宝珠山と号す。中区新栄町四丁目の南側に在り。境内は千四百十七坪四合二勺(徳川時代に二千二百七十七坪二分有り。除地なりき。)京都妙満寺の末寺なり。もと清須(きよす)の土田に在り、慶長六年(一六〇一)常楽院日経の建立なり。其の後、日経法難に由りて、其の弟子正善院日寿(寛永四年(一六二七)五月七日加賀本覚寺に寂す。)を開基となす。(但し、今、日経を開基となし、日寿を初世となす。)慶長十五年(一六一〇)今の地に移る。」(九七五頁)
この寺は現在は名を常楽寺と改め、場所も名古屋市千種区城山町に移っており、顕本法華宗に属している。さて、この寺が常楽院日経によって創立されたことに注意すべきである。日経は有名な不受不施派の傑僧で、東上総に関係の深い人である。彼は上総国南谷木一松で生まれたといわれ、大沼田の檀林で修行し、南横川(大網白里町)に方墳寺を建て、七里法華の地域の法華宗が鈍化して真言宗化する傾向があったのを折伏(しゃくぶく)して、純粋の姿にもどそうと懸命に努力したのであったが、慶長四年(一五九九)顕本法華宗の本山たる京都妙満寺の住職となって上京し、同六年名古屋にこの常徳寺を創立したのである。その寺へ入山した日勇は初世日経との縁が出来、延いては東上総との関係をもつようになるのである。彼は時の住持(一二代)明照院日貴の下で仏弟子としての修業にはげみ、後に同時の塔中(たっちゅう)忠善院の第七世をついだという。彼は元来、頭脳が明晰で博覧強記の学問好きであったから、師の日貴は仏学の蘊奥(うんおう)をきわめさせようとして、日経と縁の深い東上総の宮谷檀林に学ばせることにしたという。常楽寺の由緒書に「右ハ修学ノ為メ隠居仕リ候」(原漢文)と書かれてあるそうだが、それは宮谷檀林への遊学のため寺を退いたことを意味している。こうして、日勇は遠くわが上総の地へ遷ることになったのであるが、それが何時のことであったかは不明である。ともかく、彼は宮谷檀林において、その頃の学長日受の指導を受けたのである。
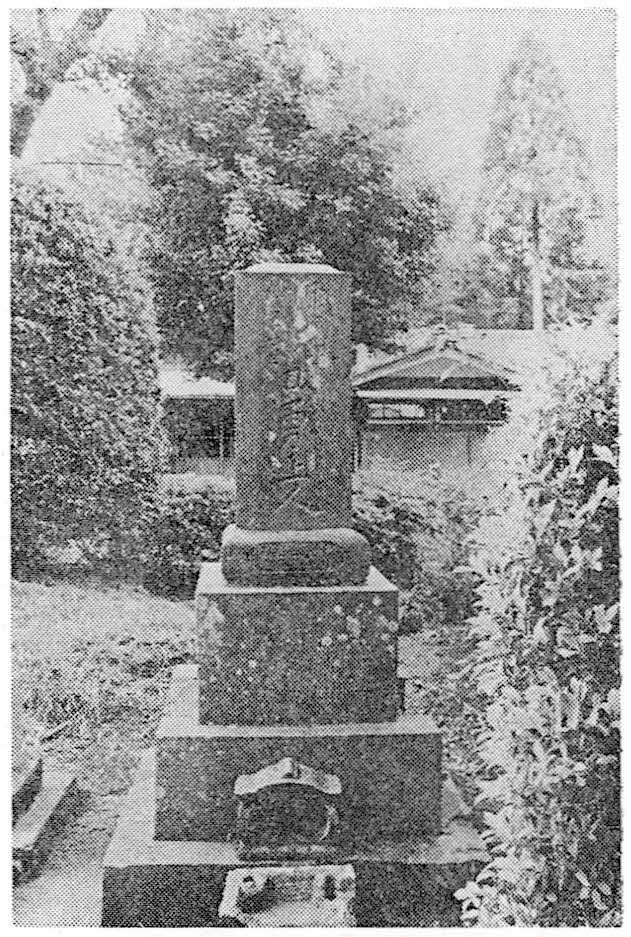
存道日勇墓碑(本松寺)
さて、その後の日勇の動向について、「公平村郷土資料草案」(A)には、次のように記してある。
「享保年中(一七一六-一七三五)笈(きゅう)ヲ負ウテ江都ニ遊ビ、湯島聖堂ニ学ブ。業成ルニ及ンデ、上京シ本山(顕本法華宗の本山京都の妙満寺)ニ入リテ其ノ第百九世ヲ継ギ、後、郷(松之郷をさしている)ニ帰リ、師僧ノ後ヲ受ケテ本松寺ニ住職タリ。実ニ当山第十七世トス。」(「東金市史・史料篇一」二九四頁)
また、長谷川義一著「什門教学伝統誌」(B)という書を見ると、
「後、宮谷第七十七世の能化(のうけ)となり、東金在松之郷本松寺第十七世を経て、妙満寺第百九世に列す。(中略)本松寺に住した師(日勇のこと)は湯島昌平黌(こう)に儒を講じたと伝へ、今でも松之郷では存道様と言われて、徳を慕はれてゐる。」(一三九-一四一頁)
日勇の人生コースを知るためには、今のところこの二つの記述しかない(筆者の寡聞によるとは思うが)。まず、湯島聖堂すなわち昌平黌へ入った年代だが、享保年中というと、日勇の年齢巾(はば)では一二歳から三一歳までになる。それは、宮谷檀林の業を卒えた後であるか。それとも宮谷第七七代の能化(学頭)となったのより前であるか後であるか。(Bに昌平黌で儒を講じたとあるのは、教師として教えたということであろう。)次に、妙満寺の第百九世になったのは、松之郷の本松寺の第一七代となったのより前であるか、後であるか。Bでは前となっているが、Aでは後のように書いている。(なお、中村孝也氏の「上総宮谷檀林資料(2)」によると、宮谷の能化となったのは宝暦三年(一七五三)十一月から同四年十月までであったとしている。)しかし、日勇はその晩年は本松寺で過したようであるから、本松寺づとめは前後二度あったとも考えられる。
ともかく、日勇の人生コースを正確にきめがたいが、宮谷檀林で仏学を修得し、さらに昌平黌で儒学を研鑽、宮谷の能化となり、顕本法華最高の地位というべき妙満寺の管長に就任し、また、松之郷の本松寺住職として静かな晩年を過したことは確かなことである。日勇のことを顕本法華宗では、受門の三傑の一人と称している。受門とは前述の宮谷檀林の学長だった日受の門下ということである。日受は江戸の生まれで、壮年のころ浅草本立寺で出家し、宮谷檀林で修行し、後に同檀林第五九世の能化となった。その後、品川本光寺の第二六世を継いだが、寛保二年(一七四二)五一歳の時、妙満寺第九二世となり、本望を達成した。間もなく退任して、品川本光寺に隠居した。世に品川日受と称されている。この人は剛直で高邁な傑僧で学問も深く、多くの門弟から敬仰されていた。「本迹自鏡編」(二巻)「本迹異論傍観書」(五巻)等著書も多い。彼は同宗の人たちから、「宗家之驥龍(きりゅう)」とか「教門之偉人」とか賛えられていたというから、その偉材のほどが推測される。この日受は安永五年(一七七六)七月二二日、八五歳の長寿をもって入寂した。彼の門下で日勇は傑出した人物であったが、彼と拮抗する英才がほかに二人あった。本理院日孝と永昌院日芳である。この三人がいわゆる受門の三傑なのである。日孝は宮谷の能化第百七世となり、さらに上総長南の長円寺第一五世となり、ついに妙満寺第百三六世にまでなった人で、寛政四年(一七九二)一〇月に入寂している(行年不明)。この人は長南日孝と呼ばれ、長南地方では有名である。日芳は宮谷の能化第百九世となり、東金の本漸寺第一九世を経て、栄誉ある妙満寺第百三七世、つまり日孝の次の管長に昇任している。世に閑亮日芳といわれた人である。寛政九年(一七九七)七月六七歳で死去している。したがって生年は享保一六年(一七三一)で、日勇より二六年も若いことになる。日孝の享年は分からないが、おそらく日芳と大差はなかったであろうから、両人とも日勇からずっと後輩ということになろう。日勇・日孝・日芳の三人が三傑と称されたのは、いずれも学徳ともにすぐれていたからであろうが、三人ともそろって本山妙満寺管長の最高位にのぼったことによるものと思われる。
2
日勇の特異性の第一は、僧侶でありながら儒学を究めた碩学であたっことだろう。彼の師日受も学殖が深く「如実事観録」その他の著述を残し、相当の論客でもあった。その影響を受けたところもあろうが、日勇は「弁断鬼神二教合璧論」(五巻)「儒仏心性論衡」(一巻)「易学原正」(三巻)「蒲鞭折疑論」(一巻)「牛頭決難字考」(一巻)等の著述を残している。この中、「弁断鬼神二教合璧論」は、宝暦四年(一七五四)五〇歳の時の述作で、新井白石の鬼神論を論駁したものである。日勇は、仏教と儒教とはその根源は一つであって、互いに協調融和すべきものであると考えていた。すなわち、彼は本作の序文で「夫れ、仏と儒と心源維(こ)れ同じく、教迹(せき)維れ異なり。若し其の心に達する時は、則も一理渾(こん)然たり」と言っているのである。当時、儒者たちは仏教を嫌い、これを排撃しようとする傾向が強かった。日勇はそれに対して、大乗的な立場から二教調和論を唱えていたのである。次に、「蒲鞭折疑論」はそれより四年前の寛延三年(一七五〇)四六歳の時の著であるが、これはその前年に、浄家玄翁大淑なる人物が「土器揉轡(じゅうひ)録」という書を著して、顕本法華宗を罵詈(ばり)したのに対して、反撃を加えてこれを論破したものである。これらの著述のあることによって、日勇が単なる僧侶ではなく、仏教学者としても、堂々たる存在であったことを示しているのである。
このように、日勇は立派な学僧であったが、おのれを高うして人に誇るような姿勢は持っていなかった。むしろ、庶民的な人情家の面をゆたかにそなえていた。そして、僧侶にありがちな、迷妄な観念論を振りまわすようなところがなく、リアリスティックな物の考えかたをもっていた。そのため、民衆に親しまれるところがあった。彼について、松之郷地方に伝えられている、次のような有名な話がある。
この地方にはいろいろと迷信が多いが、その中に「さんりんぼう」(三隣亡)というのは、いわゆる民間暦の凶日で、亥の日・寅の日・午の日(月によってちがいがある)に家の普請をすると火事がおこって近隣三軒を焼き亡ぼしてしまうから、その日に普請はしないほうがよいとされていた。ある年のこと、日勇は本松寺の本堂の屋根普請を計画した。それが、盆を控えていたので、ぜひとも早く取りかかる必要があったが、予定した日があいにく「さんりんぼう」にあたっていた。すると、屋根屋らは延期してくれといってきた。そこで、日勇は思案して、「『さんりんぼう』の日には、『さんりんぼう』さまがお通りになるのであるが、それはお通りの時間がきまっているのであって、お通りの時に仕事をやめてつつしんでいれば、何のお咎めもない。わたしがちゃんとお通りの時間を見ているから、安心して仕事をしていなさい。」と彼らに申しわたした。とにかく、えらい名僧知識のいうことだから、屋根屋も和尚のいうとおりにした。日勇は時々屋外へ出て仔細らしく空の一角をながめて、うまく刻限をはかり、午前に一回、「今、『さんりんぼう』様のお通りだから休みなさい」といって一同を休ませてお茶を飲ませ、午後になるともう一度休ませ、「今、『さんりんぼう』さまのお帰りですよ」と告げたのである。こんなやりかたで、うまく屋根屋らを納得させ、無事に普請を完了したというのである。
この話は何か子供だましのような感じもするが、迷信深い職人たちの心理を逆に利用した、たくみな教法といえよう。一休式な頓知だといえば、それまでだが、こういう仕方で迷信のばからしさをそれとなく教え込んで、合理的な生活指導をした、日勇の明智は敬服に価すると思う。彼が民衆から「存道さま」と尊ばれ慕われたというのも、まことにもっともである。「里俗、今日ニナリテモ、博識ナル人ヲ見レバ、即チ曰ク『存道様ノ如シ』ト。難解ノ事アレバ、即チ曰ク、『存道様ニ聞ケ』ト。以テ其ノ非凡ノ才ヲ有セル名僧ナリシ事ヲ知ランカ。」(「公平村郷土資料草案」東金市史・史料篇一。九五頁)こんな風に、日勇は何でも知っている知恵の神様のような尊信を受けていたのである。昔の名僧は民衆とともに生きることに生き甲斐を見出していた。碩学日勇はまた民衆の友でもあったのである。
日勇は宝暦一〇年(一七六〇)一二月二二日入寂した。行年五六歳であった。