本寺に経二寸程の水晶の玉が秘蔵されている。これは日泰が高弟日行に与えたと伝えられ、日行は本寺の住職となったので、これを寺宝とし残したということだ。里人は、これを「産の玉」と称して崇めているが、その縁起は左のとおりである。
「当山二世大僧都日行は、嘗て福俵本福寺に閉居す。一日、本福寺より当寺に還るや大雪道を埋む。時に途上一婦人の嬰児を抱くに逢ふ。形容衰弱恰(あたか)も分娩せるものに似たり。僧に乞ひて傾刻(けいこく)赤子を委す、僧諾して児を抱く、其重きこと巨石の如く、其冷きこと凝雪に似たり。僧忍耐して暫時読経せり。婦謝して云ふ、師の済度により、妾既に苦みを脱すと。即ち其の児を取りてこれを懐にし、僧に贈るに一玉を以てし、忽然形影を失ふ。故にこれを産の玉と称す。「(「山武郡 郷土誌」一七三-一七四頁)※
この玉は気象の変化によって清濁の色を呈するという。もちろん、右の伝説をそのまま信ずるわけにはゆかないが、土地の女性たちは昔からお産のお守りとして信仰の対象としてきている。
本寺の境内は凡そ六〇〇〇平方メートル、往昔盛時の面影はないが、寺内には赤人像・閻魔像(共に東金市指定文化財)や寺宝水晶玉・古記録も多く残り、附近には、山辺赤人塚・鹿渡(かのと)神社・雄蛇ケ池等の名勝・旧跡等が多く散在し、西行法師の口碑もあり、細井広沢や高山彦九郎は、それぞれこの地を訪れて、その紀行文を残している。特に近時は、散策の格好の地として、ここを訪れる都人士の数は多いという。
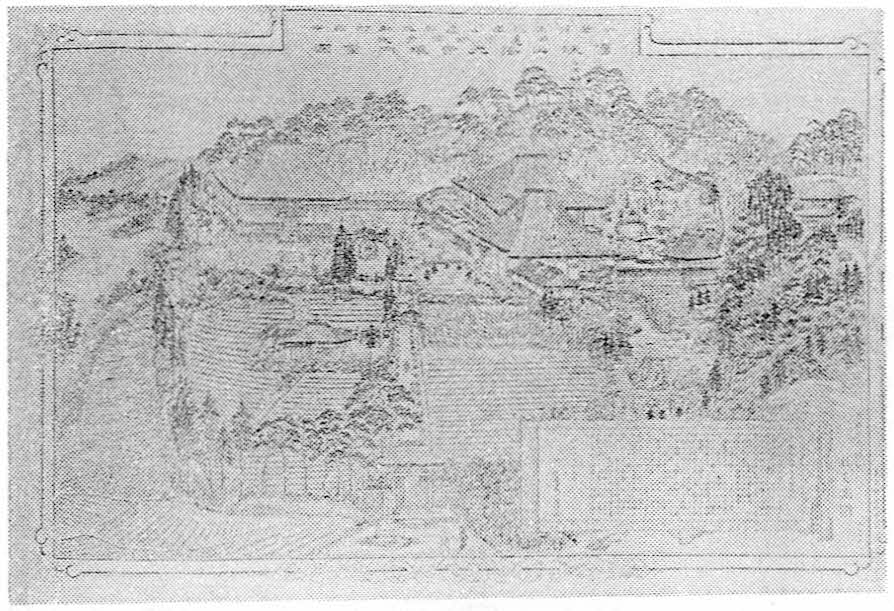
明治20年代の法光寺絵図
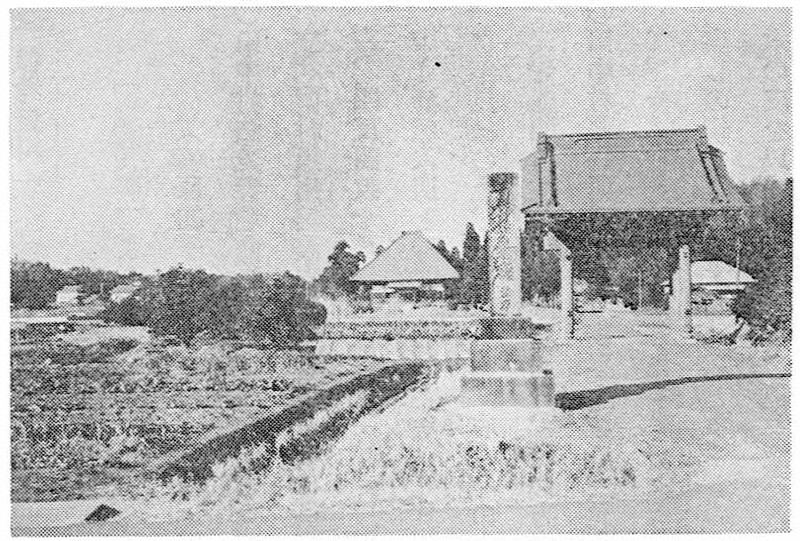
法光寺遠望
※「山武郡郷土誌」のこの文は、おそらく「上総国誌」(巻之六)の記述を借りたものと思われる。同書には、日行は「本国(上総)市原郡八幡郷ノ産ナリ」と書き添え、また、この玉に対する考え方を左のようにのべているので、参考のため掲出しておく。
「按ズルニ、彼、詭怪(きかい)ノ説ヲ為ス。固ヨリ信ズルニ足ラズ。憶フニ、其ノ玉タル、日泰ヨリ日行ニ伝フルモノカ。恐ラクハ、後世ノ浮屠(ふと)氏(僧侶のこと)其ノ物ニ仮(か)リテ道徳ヲ鳴ラスモノニ似ルカ。然リ而シテ、世間稀ニ珠玉無キニ非ズ。故ニ、記シテ以テ其ノ玉ヲ江湖ニ鳴ラスコト爾(しか)リ。」(原漢文)
参考資料
「見聞記」より
(篠原初子家文書・筆者不明・安政五(一八五八)午年初執筆)
○田中村法光寺境内の儀は、日泰上人御開基にて、長享元(一四八七)未年御建立。同村黒川美濃守の子兵部、後に彦三郎と称す。同人屋敷地の内、四反四畝十八歩、右代地同村井戸川筋上畠にて渡る。酒井越中守清伝入道と号す。右領主なり。其の後、元禄十一(一六九八)寅年同村三ケ年見様(ためし)の上、五給に分郷、右替地の上畠の分大沢様に成り、法光寺表門外左の方大沢様の分、右の方榊原様の分なり。
○田中村桜井新五郎事、嘉平太屋舗、元真言宗西法寺の跡の由にて、今に古石石碑等掘り出す事折々なり。白無采素焼物、近来掘出しの物。但し、本名祝瓶(いわべ)と申すものにて、神を祭る器なり。桜木の皮を以て柄勺を造り、酒を汲み入ると云ふ。然れども、西法寺境内に神器之れ有るも如何。骨坪(つぼ)(壺)に之れ有るべきなり。
○田中村宝珠山法光寺、元真言宗正源寺と云ふ。日行聖師にて改め、日蓮宗と相成り、泰師御開基とは相成り居るなり。今、境内の本正坊は大成なり。正源寺の跡なりと云ふ。法光寺御朱印十八石、余は境内続き、池土手下より行師の御墓廻り一園なり。新五郎脇曲松の塚は八幡宮なり。是れ亦、境内なりと云ふ。