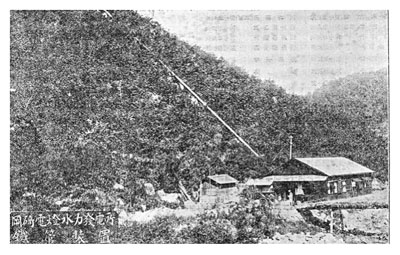(いわづはつでんしょ)
【近代】
岩津発電所は東加茂郡と額田郡の境を流れる郡界川の流れを利用する水力発電所で、岡崎電灯第一発電所、または所在地から滝脇発電所とも呼ばれる。明治30(1897)年7月に運転を開始し、岡崎電灯にとって最初の発電所であるとともに、中部地方で最初に成功した水力発電所であった。発電所の上流には、名勝二畳ヶ滝があり、その上流から取水し、約1.3kmの水路により、有効落差55mを得て50kWを発電した。その後同33年12月に増設されて102kWとなり、現在は140kWで中部電力では最少で最古の発電所である。起こされた電気は、岡崎町までの約16kmを、2000ボルトの電線路で送電された。この送電距離は、それまで近隣にしか送電できなかった水力発電の可能性を大きく高めるものであり、完成すると電力関係者が相次いで視察に訪れた。建設を担当したのは、水力技師大岡正(1855~1909)であった。大岡は、わが国2番目の水力発電所である箱根湯本の湯本発電所(25kW)をはじめ、熱海、豊橋、郡上八幡などで水力発電事業に携わった水力発電のパイオニアである。矢作川水系では、明治35年田代川に小原発電所(現川下発電所)を建設している。岩津発電所の建設に際しては地元の要請を受け入れ、郡界川の両側に道路の建設や改修を行った。このため、それまで、数軒しかなかった水車動力を利用するガラ紡工場が、次々と川沿いに建設された。大正15(1926)年に火災が起きたため建替えられ、現在の発電所建屋はコンクリートづくりで、当初のものではない。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻456ページ、12巻144ページ
→ 岡崎電灯