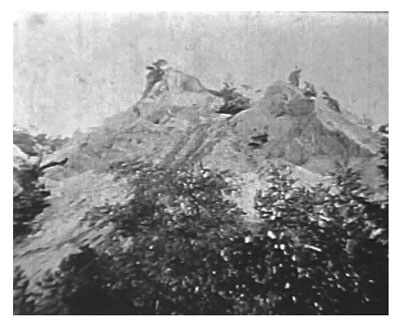(さなげやま)
【自然】
猿投山は、三河高原西端の豊田市北西部に位置する標高629.0mの山塊(山塊の最高点は632m)である。北西側を猿投山北断層、南東側を猿投-境川断層にそれぞれ規制され、両断層によってポップアップする形で周囲の東海層群からなる丘陵から突出した形を成している。山麓には猿投神社を擁しその山容は古くから信仰の対象とされてきた。猿投山は白亜紀後期の領家帯新期花崗岩類伊奈川花崗岩からなるとされ、これらは猿投みかげと称する石材として利用されてきた。また南麓で産出する、結晶の球状模様から菊石とよばれる球状花崗岩が国指定天然記念物とされている。
『新修豊田市史』関係箇所:23巻48ページ
【近世】
猿投村にある猿投寺社中の山。周辺の村の要求により猿投寺社中は周辺村が山に入ることを認めるようになった。宝永4(1707)年一色村(藤岡地区)に対して山中の場所を定めて下草を刈ることを認めた。いつからかは未詳であるが、飯野村・迫村(ともに藤岡地区)が山の利用料を納めることで入山を認められている。一方、享保元(1716)~2年に広見村(保見地区)と猿投山の境論が起こったが、幕府の裁許では広見村の主張は退けられ、広見村・八草村・大畑村(いずれも保見地区)は入会を禁じられた。元文元(1736)年の山の利用料の規定は猿投村民に対するものと思われ、年齢と男女別に定められている。こうした日常的な下草・小枝の利用のほかに、材木が伐り出されることもあり、文化末から文政初頭にかけて、川島村(安城市)の材木商人が御用材の不足を補うために、猿投山から1280本伐り出したことが確認できる。
『新修豊田市史』関係箇所:3巻179・254・281・464・678ページ、7巻181ページ、8巻173ページ
【近代】
近世までの猿投山登山は霊場をめぐる参拝が中心であり、文化5(1808)年に描かれた「白鳳山勝景図」にも登山する人々が描かれている。ところが、近代以降、山は名古屋から近い観光地として開発された。大正2(1913)年に営業を開始した尾三自動車株式会社は自社のバスを利用して名古屋から猿投神社まで観光客を運び、猿投山一帯の観光旅行を誘致した。そして、大碓命の陵墓や猿投神社などをめぐる登山、砂の上を滑るサンドスキーなどが行われた(写真:サンドスキー場)。昭和10(1935)年頃の名古屋から猿投への日帰り旅行案内では、名古屋-猿投間の尾三バスの所要時間が1時間25分、猿投登山の所要時間が約4時間と記されている。そして、不世出の紅葉狩りの名所でハイキングや写真撮影、写生などに適した山であるとして広告されている。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻607ページ、11巻323ページ