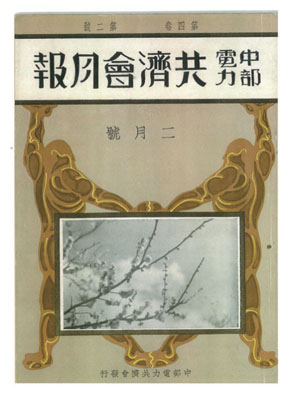(ちゅうぶでんりょく)
【近代】
中部電力は、昭和5(1930)年8月に、岡崎電灯、東邦電力の豊橋区域、多治見にあった中部電力(旧多治見電灯所)の3社が統合して成立した会社である。岡崎に本社をおいた中部電力は、三河地域・岐阜県の東濃地区を供給区域とし、矢作川水系、豊川水系などに水力発電所14か所、1万4624kW、火力発電所2か所、1万1200kWをもって設立された。岡崎電灯の供給区域は、東邦電力の名古屋地区と豊橋地区の間に存在していたので、かねて電力供給体制の問題点といわれていた。昭和4年12月、東邦電力系の三河水力電気の越戸発電所が完成し、岡崎電灯への電力供給(4600kW)が始まると、両社の連係が深まり合併の機運が高まった。まず昭和5年2月に東邦電力主体に中部電力が設立され、同年8月25日に多治見町に本社を置く中部電力と岡崎電灯とを統合して三河地域全体を供給する中部電力が成立した。新社長には岡崎電灯社長の杉浦銀蔵が就いた。発足後の紡績工場やレーヨン工場の進出などによって需要が増大しため、昭和9年11月に阿摺発電所(4000kW)、昭和10年7月に明知川発電所(1000kW)など水力開発を積極的に進めた。また、岡崎電灯時代から受電していた水窪川水力電気を昭和9年2月に譲り受け、天竜電気を昭和11年2月に合併した。中部電力は発足当初、岡崎電灯系の会社という色彩が強かったが、東邦電力と緊密な関係を保ち、電力の需給地点も6か所に及び、東邦電力の影響力が次第に強まった。昭和12年8月、電力統合の気運が高まる中で両社は合併し、発足から7年で中部電力は解散した。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻689ページ
→ 岡崎電灯