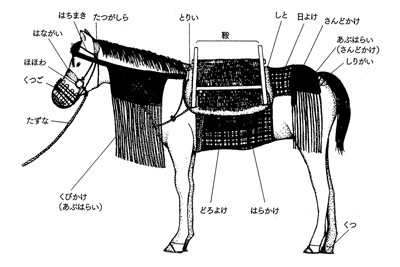(ちゅうま)
【近世】
信濃国において発達した馬による荷物の輸送方法。宿駅伝馬制のもとでは宿駅の人馬を利用する場合は原則として1宿ごとに替えなければならなかった。この原則は五街道だけでなく脇街道も準じていて、人馬継ぎ立ての利用料だけでなく、問屋場の口銭(手数料)も徴収された。しかし、信濃国や甲斐国で成長した信州中馬は宿場の継立場で馬の付け替えをしない付け通しで商品荷物を運搬していた。信州中馬は初め自己の生産した品物を城下町などに運搬していたが、寛文年間(1661~73)より商人が取り扱う荷物を運搬する馬稼ぎを行うようになったとされる。信州中馬の活動は17世紀後半には伊那郡を中心に諏訪・筑摩・安曇等の信濃国西南部の諸郡の百姓の間でも行われ、活動範囲は信濃国を越えて尾張・三河・美濃、17世紀末には甲斐から江戸・駿河・相模に進出し、18世紀に入ると宿場の継ぎ立て荷物を凌駕し、また宿場の利益を損ねることとなり、宿場の維持にも影響を及ぼした。明和元(1764)年12月に、幕府評定所は街道ごとに信州中馬が扱う荷物の品目を定め、そのほかの荷物は宿継ぎとし、宿場に手数料である口銭を納める裁定を下した。これによって信州中馬稼ぎの慣行は公認された。ただ、飯田から三河国に向かう伊那街道(三州街道・飯田街道)や足助街道については取扱商品荷物の指定や宿場の口銭徴収の対象外となり、これ以降、規制のない伊那街道沿いの飯田以南の浪合・平谷・根羽での馬稼ぎが盛んに行われ、三河国の馬稼ぎ(三州馬稼ぎ)との間で争論が起こるようになった。文化13(1816)年8月、信濃国伊那郡62か村の信州中馬稼ぎ仲間と津具村等の馬稼ぎとが争い、文政3(1820)年8月の裁許により、信州中馬の勝利となった。市域の村々は、直接この争いには関わらなかったが、文政4年には伊那街道沿いの明川・連谷など6か村や矢作川沿いの樫尾(西樫尾)村など9か村が、武節町村など11か村に準じて裁許を遵守する旨の請書を提出している。ところが、文政3年の裁許では市域を通る伊那街道は対象外の扱いであり、明川村などは名古屋・岡崎・足助との馬稼ぎが可能であったが、武節11か村は、名古屋・岡崎・足助との馬稼ぎを差し止められてしまった。三河地域の産物の運搬や自分荷物の運搬は文政3年の裁許で公認されたものの、活動は停滞し、武節11か村の助馬保有の減少を招いた。天保12(1841)年に武節11か村は伊那街道における自村の馬稼ぎの復活を求めて信州中馬62か村へ訴え出た。同年は天保の改革の経済政策により、株仲間や問屋組合が物価高騰の原因であるとしてこれらを解散させ、自由取引を許可していた。内済の結果は、条件付きではあるが、信州中馬の駄賃稼ぎに差し障りない範囲で岡崎・名古屋の信州中馬の付け残し荷物は明川村と同様に運搬が可能となり、武節11か村の三州馬稼ぎは復活した。
『新修豊田市史』関係箇所:3巻444ページ