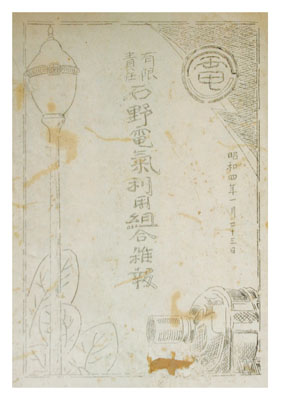(でんきりようくみあい)
【近代】
電気利用組合は、民営の電気事業が手を出さないような山間僻地で、電気の供給を行った産業組合組織(現在の農業協同組合の前身)で、地方への電気の普及に大きな役割を果たした。当初は、既存の電気事業を圧迫するとして主管官庁の逓信省は反対したが、農業者の熱心な働きかけにより、民営の電力会社が供給しない地域で電気の普及をはかるとの趣旨のもと、大正11(1922)年5月に逓信省電気局長の通牒「産業組合ノ施設スル電気工作物ニ関スル件」が出され、一定の要件を充たせば電気供給ができるようになった。通牒に先立ち、大正10年4月に産業組合法が改正され、産業組合の活動分野が大幅に拡大される。これによって、電気利用組合は急速に拡大をみた。昭和3(1928)年時点で、全国に158組合あったが、このうち愛知県は23組合で第1位であり、特に西三河地方では大正12年開業の深田電気利用組合(藤岡村)をはじめ16組合が設立され、全国で最も電気利用組合が集積した地域となった。地域別には藤岡村で5か所、小原村で3か所、猿投村で2か所など西加茂郡で11か所あり、東加茂郡でも阿摺村、松平村などに5か所が設置された(写真:『有限責任石野電気利用組合雑報』)。西三河に電気利用組合の集積した要因としては、①中核的電気事業者である岡崎電灯は、小原村、藤岡村、下山村等山間部は供給区域に組み込まず、また供給区域であっても幹線から離れた山間地への電気供給に消極的であったこと、②山間地域でも養蚕業が発達し、養蚕作業、特に熟繭の移し替えを行う上蔟作業に電灯が強く求められたこと、③農村社会の安定に向けて行政当局が積極的に支援したことである。
『新修豊田市史』関係箇所:4巻577ページ、12巻167ページ、11号65ページ