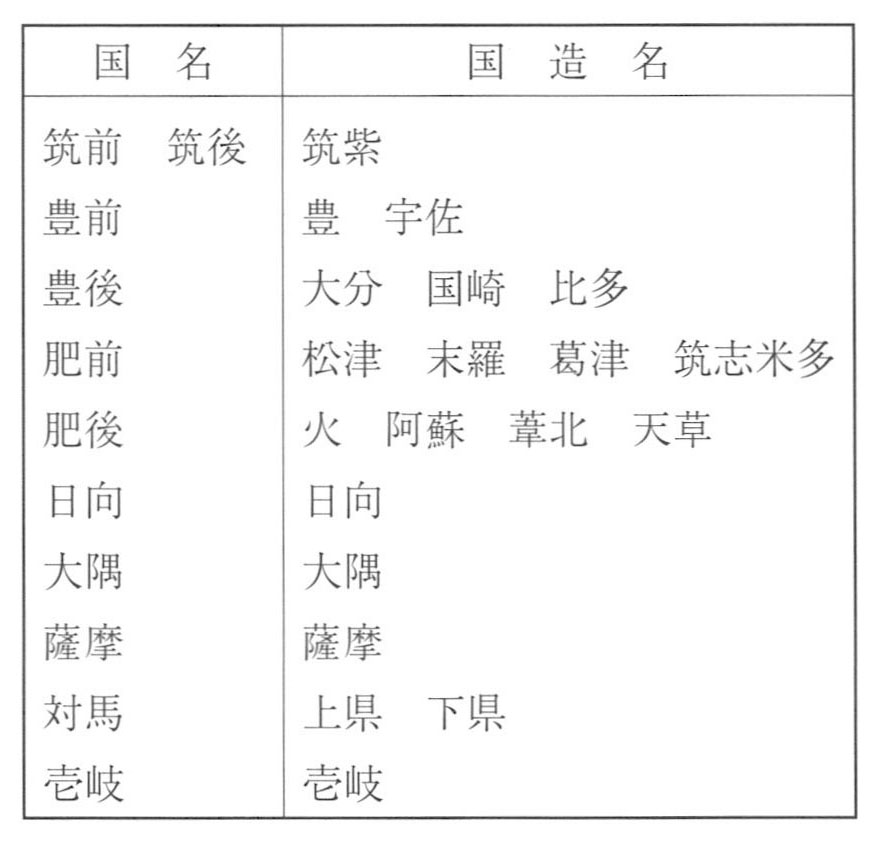国造制文献史料にみえる「国造」は、大きく①大化前代の国造(旧国造)、②律令制下の国造(新国造)に分類することができる1。一般的には前者を「国造制」と呼んでいる。
国造制の成立を示す史料として、
「自其余七十七王者、悉別賜国国之国造、亦、和気及稲置・県主也」 (『古事記』景行天皇条)
「其(それ)より余(ほか)の七十七の王(みこ)は、悉(ことごと)く国々(くにぐに)の国造(くにのみやつこ)と、亦(また)、和気(わけ)と稲置(いなき)・県主(あがたぬし)とに別(わ)け賜(たま)ひき」
「定賜大国小国之国造、亦、定賜国々之堺及大県・小県之県主也」 (『古事記』成務天皇条)
「大(おほ)き国・小(ちひさ)き国の国造(くにのみやつこ)を定(さだ)め賜(たま)ひ、亦(また)、国々の堺(さかひ)と大き県(あがた)・小き県の県主(あがたぬし)とを定め賜ひき」
とあり、『国造本紀』にも景行・成務両天皇朝において国造任命記事が集中する。しかし、『古事記』のこの箇所に関して信憑性が問われていることから史実とは言えない。
その他の史料として『隋書』倭国伝には
「有軍尼一百二十人。猶中国牧宰。八十戸置一伊尼糞。如今里長也。十伊尼翼属一軍尼」 (『隋書』倭国伝)
「軍尼(くに)一百二十人有り。猶(な)ほ中国の牧宰のごとし。八十戸に一伊尼冀(いなき)を置く。今の里長の如きなり。十伊尼冀一軍尼に属す」
とあり、ここにいう「軍尼」(クニ)を国造、「伊尼冀」(イナキ)を稲置と解釈すると、国造-稲置制が七世紀の初め頃には全国的に成立していたことを意味する。その国造制の成立の時期については、①『記』・『紀』の記載どおりに四世紀末~五世紀初め頃の成務期とする説2と、②五世紀末~六世紀代とする説3が代表的なものとしてあげられる。近年においては後者の説が有力になりつつある。さらに今日では『日本書紀』崇俊天皇二年(五八九)七月条に注目してこれを東日本における国造制の再編成が行われたことを示すと理解する説4、そして山陽・南海地方においては「凡直国造制(おおしのあたいこくぞうせい)」という形で六世紀後半に国造制が再編成されたという説5もある。