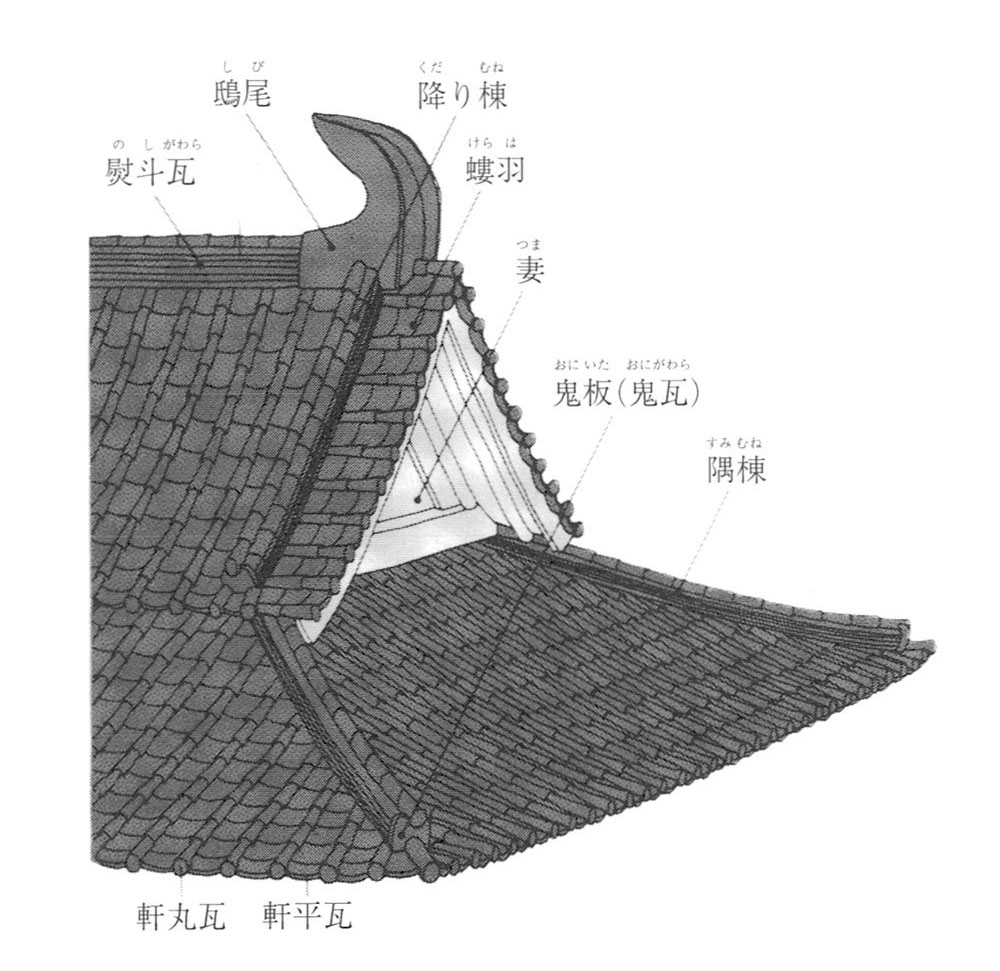東アジアでの瓦の起源は中国の西周時代まで遡(さかのぼ)る。我が国の瓦製作技術は、飛鳥時代に仏教文化とともに伝播(でんぱ)したものである。日本最初の瓦葺寺院は飛鳥寺である。朝鮮半島の百済から瓦博士を迎え、推古天皇四年(五九六)に完成された。我が国の瓦製作技術はこの六世紀末に朝鮮半島の百済から伝わったものである。仏教伝来を象徴する寺院建築において、火や水に対する耐久性に優れた瓦はなくてはならない存在であった。槍皮葺、柿葺き、板葺きなどの屋根もつくられたが、仏教建築の屋根は瓦葺が最も多い。七世紀後半から八世紀に全国各地に寺院、役所が建設されるに伴い、各地で瓦生産が盛んとなっていった。いうまでもなく屋根瓦は風雨を防ぐものである。屋根の発展の歴史は建物の雨漏り対処の歴史でもある。
筑前地方の瓦生産遺跡の一例としては、大宰府では来木、松倉地区の丘陵地帯で瓦窯が数基ずつ残っている。筑前国分寺東には瓦窯が二基残っている。観世音寺の瓦窯は不明である。しかし、『観世音寺資材帳』(延喜五年、九〇五)に「造瓦屋」という建築に使用する道具について記事がある。瓦工房の存在を示唆する文献史料である。
豊前地方では、旧築城郡の船迫(ふなさこ)窯跡群、旧仲津郡の福六(ふくろく)瓦窯跡、旧上毛郡の友枝(ともえだ)瓦窯跡、旧下毛郡伊藤田(いとうだ)窯跡群、旧宇佐郡虚空蔵寺(こくうぞうじ)窯跡群などが知られる。