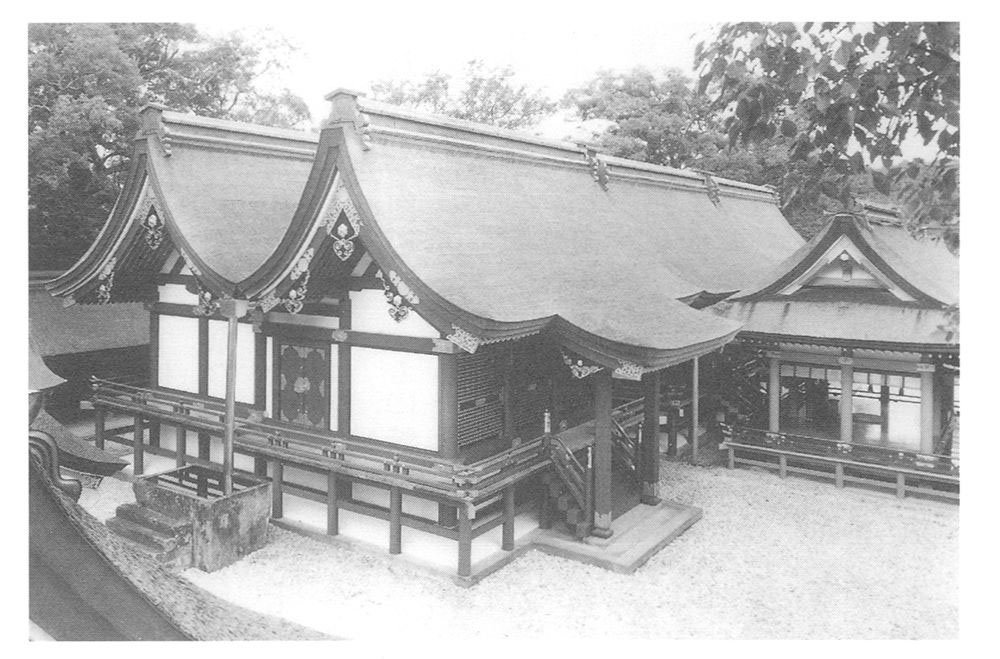背後の御許山(おもとさん)の山頂からやや下ったところに東面する三個の石体があり、中世以降八幡三所の神体に擬されて崇拝の対象となった。宇佐八幡の源流は御許山を神体山とする信仰であった。宇佐八幡は宇佐国造家が奉ずる原始宇佐信仰に、大和の大神(おおみわ)氏の庶流である宇佐の大神(おおが)氏、渡来系氏族で宇佐郡辛嶋郷を本貫とする辛嶋(からしま)氏らによって形成された。宇佐宮の初現期には宇佐八幡一柱(ひとはしら)であったが、のち二柱の神が加わって九世紀末頃までに三座の形態を整えたとする説もある。
また宇佐郡内には虚空蔵(こくぞう)寺(宇佐市駅川町山本)や法鏡寺(宇佐市法鏡寺)などの白鳳(はくほう)期仏教寺院も、宇佐宮にかかわる上記氏族たちによって建立され、はやくから神仏習合の実績をあげた。八幡大菩薩(だいぼさつ)の称号はそのことを示すものである。
筑紫の地方神であった宇佐八幡は、八世紀になると中央政権からの崇敬(すうぎょう)を受けるようになった。大和とのかかわりはさきの仏教寺院建立にさかのぼって始まっているが、歴史の表舞台に登場したのは養老四年(七二〇)の隼人(はやと)征討であった。宇佐宮への奉幣から、征討後には託宣(たくせん)を下して、合戦によって多くの殺生を行なったことの罪障消滅のため、放生会(ほうじょうえ)を創始した。このことは神仏習合の教説にも関係し、とくに新羅仏教とかかわって宇佐地方の初期仏教に伝えられたとする指摘もある。現在の地小倉山に神殿が造営されたのは神亀二年(七二五)である。つづいては天平一二年(七四〇)聖武天皇は盧舎那仏(るしゃなぶつ)の造立を発願した。ときに宇佐八幡は託宣を下して、天神地祇を率(ひき)い誘(さそ)いて大仏の造立を必ず成就(じょうじゅ)せしめるであろうという援助決意を表明して天皇を悦(よろこ)ばせた。これが東大寺大仏の造立として完成し、宇佐八幡の中央進出の直接的契機(けいき)ともなったのである。