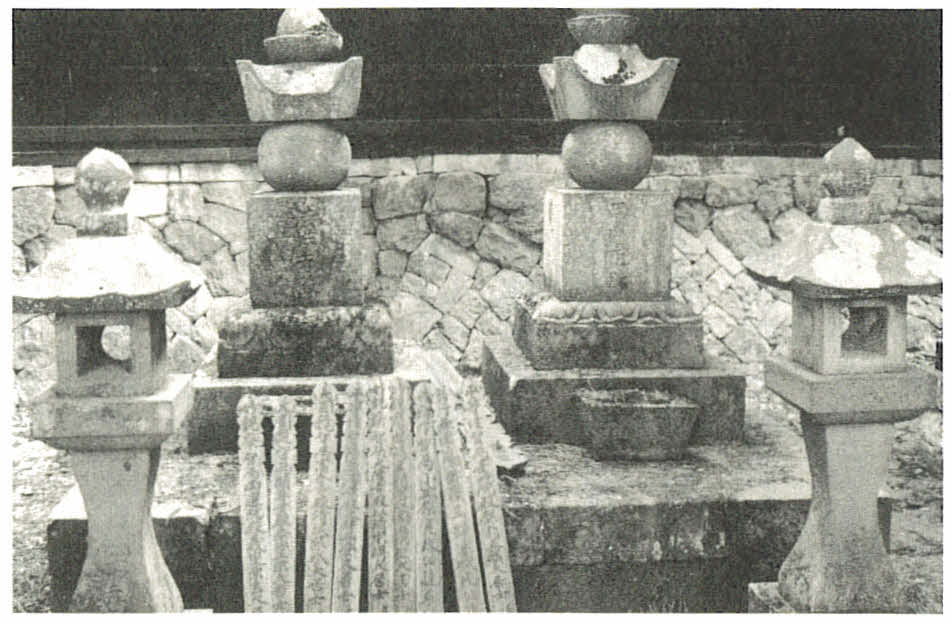慶長一九年(一六一四)、京都方広寺の鐘銘事件に端を発する、いわゆる大坂冬の陣では、小笠原忠脩(秀政嫡男)に出陣命令が下り、秀政と忠政(秀政次男)は松本にとどまって在城警備を命じられた。しかし、冬の陣では、出陣した忠脩が戦闘に加わる機会は一度もなかった。
翌慶長二〇年(七月一三日「元和」改元)に起きた、いわゆる大坂夏の陣では、秀政に出陣が命じられ、忠脩には在城警備が命じられた。忠脩は出陣許可を幕府に懇願したが許されず、ついには許しを得ないまま手勢を引き連れて出陣し、弟・忠政も同じように大坂へ向かった。命に背いたことで、将軍秀忠(忠脩・忠政にとっては大叔父)は両名に拝謁を許さなかったが、家康(忠脩・忠政曽祖父)のとりなしによって許されたという。
夏の陣は五月六日より戦闘が開始されるが、激戦の末、秀政・忠脩両名は戦死し、忠政も重傷を負うという、小笠原家にとってはまさに一大事の結末となった。