【二毛作】稲と麦そのほかの雑穀をくみあわせた二毛作は、室町時代になると全国的にひろまった。これは農民の努力の結果である。稲作も優良品種がつくられ、収穫量をますことになった。荘園領主は増収分を増徴したが、しかし農民の手に残る分もふえたはずである。
【別給村】蒲御厨でも寛正六年(一四六五)八月に別給(いまの市内飯田町)の公文(くもん)が東方代官にあてて「別給村麦米大豆定役算用注進状」(『東大寺文書』)を呈出している。そして米は年貢銭、麦などは現物納である。
【農業の進歩】平安時代や鎌倉時代の農村では、作付地と不作地が混在した粗放な状態のことが多い。しかし室町時代になると、作付けしない田畠は減少し、耕地の安定性がまし、利用の密度も高まってきた。経営の集約化と安定性は農業の着実な進歩である。
【近郊の農業 遠江茜】都市の近郊の農村では、稲作よりも収益の多い藍や瓜などの野菜を栽培し、幕府の禁令は無視されている。そして瓜は南山城(京都府南部)・大和(奈良県)・近江(滋賀県)・丹波(京都府北部)産が最上品として認められるようになった。茶・麻・苧(からむし)・荏胡麻(えごま)から駿河・遠江の茜(あかね)など各地の特産品ができ、これが消費地にでまわる。特産品と大消費地の京都などのむすびつきが強くなる。茜は古来から最も代表的な赤色の染料「緋(ひ)」色である。茜草の根をとって煮出した液汁を灰汁で赤く発色させる。灰の量を増加すると濃色になり茜色がでる。茜草は遠江地方に野生しており、現今でもいたるところで採集できる。『宗五大艸紙』に「一公方様御服と申は(中略)遠江あかねなどにて候」とある。
【遠州縞】榛(はん・矢車・波理・波牟乃木(はむのき))は灌木から喬木まで植物学上六種類ほどある。松かさに似た小さい実を矢車といい染料に使う。これに鉄分と灰汁を加え黒色に染める。遠州縞は矢車の煎汁に木錯酸鉄を媒染した黒染であった(平松実「遠江と植物染料について」 『遠州郷土読本』)。
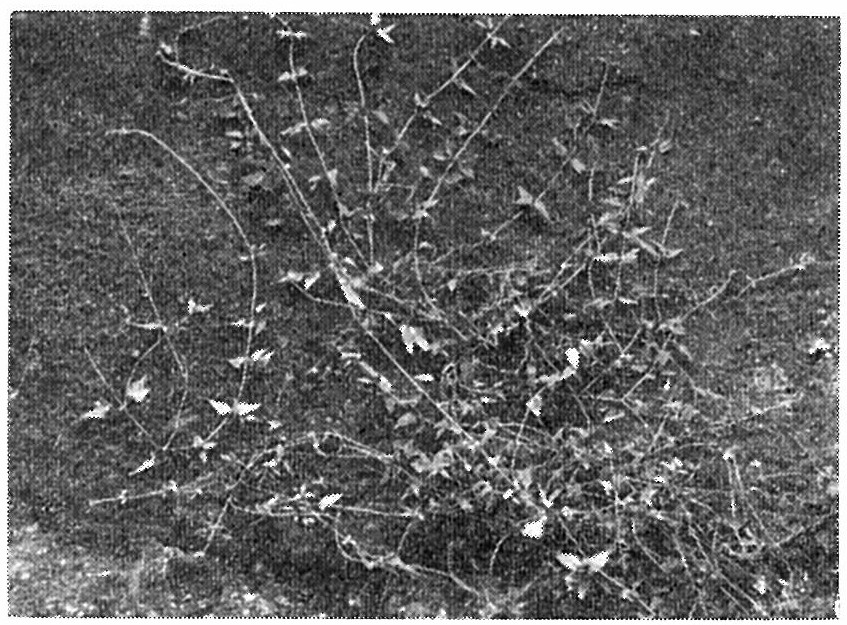
茜草
【肥料と入会】肥料は植物からとるのがふつうである。それは山野から刈りとるので、ここは農業のうえで大事な場所である。山野の境界や入会(いりあい)という共同利用の権利についても争われた。【用水】用水についても水を分配する技術面ではそれほど進歩しないが、農民の進んで参加したのが注目される。水車も能率の高いものが使用されだした。
【年貢】自作の農民は水田から年貢、畑・屋敷から雑穀を納めた。公事(くじ)という雑税、夫役(ぶやく)という労働奉仕は、貨幣が農村にゆきわたると、銭で代納することが多くなった。
【加地子】小作のような農民は名主に対し、加地子(かじし)(地代)を余分に納める。ある田地では地主、他の土地で小作人というばあいは、それぞれの立場で納税した。【百姓直納】室町時代には、百姓直納(ひゃくしょうじきのう)といい、領主・名主に本年貢と加地子をべつべつに納めるようになった。このほかに守護の段銭(たんせん)や夫役がある。
【枡】しかし荘官が年貢の収納のとき不正を働いたことは少なくない。また枡の制度が一定していなかった。同じ土地でも、荘園領主にだす年貢米をはかる枡と地主へだす地代をはかる枡とは、大きさがちがう。年貢米を納める枡は、荘園ごとにさまざまであり、領主が支払用の枡は年貢米用の枡より小さい。このほか不合理なことがながいあいだおこなわれていた。