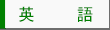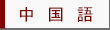沖田さんがずい道をほるかなり前にもこの考えはあったらしいのですが,中の峠は全山岩山で,とても無理ということになったそうです。それを,沖田さんは1人でやり始めたわけです。
私は,そのころ13歳くらいで手伝うことはせず,いたずら坊主だったので,時々ここへ遊びに来て沖田さんの様子を見ていただけなのですが…。
沖田さんは,南側の入り口の左手の山の中ふくに9尺(しゃく)2間(けん)の小屋を建て,そこで炊事もして作業を続けていました。時々おくさんがお弁当を届けていました。多分おいしい物があるときなど持ってきていたのでしょう。水は少し下に泉があり,そこから取っていたようです。何時ごろから何時ごろまで働いていたのかは,ずっといたわけではないので分かりませんでしたが,信心深い人だったので,朝起きてお経を上げたらすぐに取りかかっていたんでしょう。小屋のそばで火をたいて,のみも自分で作っていました。ほった土は,すぐに下に運んで田んぼを開いていたんです。今はすっかり草地になっていますけれど…。
沖田さんは,ふだんはとてもおもしろいおじいちゃんだったんですよ。気さくに話をしてくれる,いいおじいちゃんだったんですよ。ほっているときには,ほとんど話をしませんでしたが…。その調子で3年の間1人でほったわけですよ。とにかく沖田さんは,何か人の役に立つことをしたいという考えだったわけです。
村の人も時々見に来ていたんですが,3年たったときがちょうど日照りだったこともあって,1人で30メートルほどほっているのを見て,みんなが協力したらできるだろうということで手伝うことにしたわけです。とはいえ,せまいところなので,村から交代で2~3人くらいずつ人が出て,先頭を石工がほっていったんです。
石工さんは固いところはダイナマイトを使ったので,ずいぶん作業がはかどったというわけです。そのころには,レールをつけて,トロッコで土を運び出していました。
沖田さんはみんなが手伝い始めてからは石工さんの炊事の世話をしたり,小田山川からの水路をほったりもしたらしいです。このトンネルから少し上に50メートルくらいのトンネルがありますが,それを沖田さんが1人でほったんです。もっともその山は,中の峠とちがって岩山ではないので,ひかく的かんたんにほれたわけです。今もそのトンネルの中を水が流れているのですが,今はパイプを入れた丸いトンネルになっています。昔はずい道と同じ形だったですが,土が上から落ちてきて水路がふさがりやすかったので,私が水子総代だった時に西条町にたのんでパイプをうめてもらったんです。この水は,秋から春にかけて流すことにしているんですよ。深道池をいっぱいにしておくためのものですから。
ずい道の上の深道池への道は,今でこそあまり通る人もありませんが,当時は吉川にぬける道でした。深道池の左側回りで吉川に行ったんです。
ずい道の中は入り口よりかなりせまくなっていて,大人は通りにくいですよ。腹ばいにならないと無理ですね。特に中ほどはセメントで固めたところもあって,かなりせまいですね。でも,今でも年に一度10人ほどでもぐって行って掃除をしています。水路がつまったこともあって,私が入ったのですが,南側は水が多くてもぐれないので,深道池側から入ったんですよ。木や草などがたまっていたので,それを取りのぞいたら水がどっと流れて来てとてもこわい思いをしました。
沖田さんは,後年(こうねん)脳卒中(のうそっちゅう)でたおれたそうです。家は今の沖田さんの家の場所にあったんですが,建物は火事で焼けて今は残っていません。今もお盆のころに沖田さんの追悼(ついとう)の会を柏原地区で行っています。私たちは忘れてはいませんよ。でも,だんだんに忘れられていくことですから,学校でこのようなことを伝えてくれることをとてもありがたく思っています。
 |