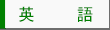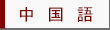三浦(みうら) 仙三郎(せんざぶろう)
東広島市西条は,酒づくりで全国的に有名なまちです。
日本酒といえば兵庫県の灘(なだ),京都府の伏見(ふしみ),広島県の西条といわれており,全国的に有名なお酒の産地の一つが,私たちの東広島市にあります。
西条の酒がこれほどまでに有名になるには,多くの人々の努力がありました。中でも,安芸津町(あきつちょう)三津(みつ)出身の三浦仙三郎は,よりおいしい酒をつくるため,新しい技術(ぎじゅつ)を生みだしました。
 酒蔵(さかぐら) |
 安芸津町三津の榊山八幡(さかきやまはちまん)神社にある三浦仙三郎の銅像(どうぞう) |
| 西条は,全国的にも有名な日本酒の産地なんだね。 |  |
<かさなるしっぱい>
1876年,仙三郎はおいしい酒をつくるため,酒づくりを始めます。しかし,なかなかよい酒はできません。いくらつくり方を工夫しても,せっかくつくった酒のほとんどがくさってしまいました。
「しっぱいするのは何か理由があるはずだ。」
生まれつき研究熱心な仙三郎は,投げ出すことなく原因を探っていきました。時には,酒づくりを行うリーダーである杜氏(とうじ)たちと,意見が合わないこともありました。
| どのようにして,新しい技術を生みだしたか調べてみよう。 日本酒のつくり方も調べてみるといいね。 | 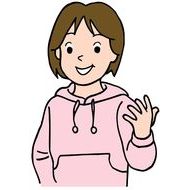 |
<新しい技術>
1893年,仙三郎は,「酒づくりの第一の問題は水である。水の質がちがうのに,同じつくり方でよい酒がつくれるわけがない。」と聞きました。さっそく三津の水を調べてみると,酒づくりにてきしていない軟水(なんすい)であることが分かったのです。
仙三郎は,軟水でもおいしい酒をつくれる方法を探って,実験や研究をくりかえしていきました。
こうして,1898年に『軟水醸造法(なんすいじょうぞうほう)』とよばれるお酒のつくり方を考えました。これまでの杜氏のうでやかんにたよる方法から,温度計を使い,酒蔵を清潔にし,低温でゆっくりつくる方法を生みだしたのです。その結果,味が変わり,くさりやすかった広島の酒をおいしい酒に変えることに成功しました。
仙三郎の苦労は,ようやく実を結びました。さらに,仙三郎はその方法をいっさいかくしませんでした。それどころか,文にまとめて他の酒屋に配ったり,自分の蔵の杜氏をよその蔵に教えに行かせたりして,地元に広める努力をしたのです。自分のりえきを求めるのではなく,ひたすら地元の酒づくりの技術(ぎじゅつ)の発展(はってん)を願ったのです。
| なぜ,新しい方法が広まっていったのだろう。 |  |
三浦仙三郎の考えた軟水醸造法 ○温度計を使う○酒蔵をせいけつにする ○低温でゆっくり発酵(はっこう)させる |
 文化福祉センター3階の安芸津郷土資料室。仙三郎の資料や酒づくりのれきしをみることができる。 |
| 三浦仙三郎のすばらしいところを話し合って,ノートにまとめよう。 |  |