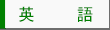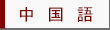北広島町は,広島県の北西にある自然豊かな町です。その自然を守る条例(じょうれい)が作られ,町全体で自然を守る取組が行われています。
※条例…県や市町村で決めるきまりのこと
 北広島町「高原の自然館(しぜんかん)」 学芸員(がくげいいん) 白川勝信(しらかわかつのぶ)さんのお話 北広島町「高原の自然館(しぜんかん)」 学芸員(がくげいいん) 白川勝信(しらかわかつのぶ)さんのお話 |
| わたしは,北広島町の自然のことを調べて,守りながらみんなに自然のすばらしさや大切さを伝えていく仕事をしています。 北広島町には,たくさんの種類の希少(きしょう)な生き物が集まっています。むかしから生き物の研究(けんきゅう)をする学者さんや大学生が北広島町に来て研究をしていました。 北広島町の人たちは,自分たちの町の自然を自分たちで守っていこうとしています。 町の条例ができたのも北広島町の人たちの自然を大切にする気持ちが大きかったからです。人間も自然の一部です。植物や動物を大切にすることは,わたしたち人間を大切にすることにもなるのです。 |
 |
| 北広島町では自然を守る取組がどのように進められているのか調べてみよう。 |  |
高原の自然館は,北広島町の自然をわかりやすく紹介(しょうかい)している学習しせつです。北広島町の自然を守る取組の一つとして作られました。
 高原の自然館 |
湿原(しつげん)を守る(北広島八幡(やわた)高原 霧ヶ谷(きりがたに)湿原)
八幡高原は1万年以上前まで湖でした。今は湖の水はなくなり,湖の底だったところに人々が田をつくってくらしています。とても雨の多い気候の八幡高原には大小20ほどの湿原があります。
湿原には他の場所では育たない数少ない植物や動物を見ることができます。
※湿原とは… 湿(しめ)った温度の低い場所にある草原 |
| 湿原(しつげん)を守る (北広島八幡(やわた)高原 霧ヶ谷(きりがたに)湿原)  |
| なぜ北広島の人は湿原を守ろうとしているのでしょうか。 |  |
八幡地域の気候(きこう)
平均気温10℃
8月の平均気温23℃
青森県と同じぐらいの気温で冬には1m以上の雪が積もる。
中国地方で最も降水量(こうすいりょう)が多い
霧ヶ谷湿原に見られる,希少な生き物
| ヒロシマサナエ | 昆虫 (こんちゅう)トンボ |
| ヒメシジミ | 昆虫 チョウ |
| ハッチョウトンボ | 昆虫 トンボ |
| (世界で一番小さなトンボ) | 2cmくらい |
| カキツバタ | 植物 |
| リュウキンカ | 植物 |
| ヒメザゼンソウ | 植物 |
| カスミサンショウウオ | 両生類(りょうせいるい) |
 ヒロシマサナエ |
 ヒメシジミ |
 ハッチョウトンボ |
 カキツバタ |
湿原を牧草地(ぼくそうち)に
数十年前,湿地(しっち)は人にとってあまり役に立たないものだと考えられていました。
40年くらい前,国や町は湿原を牛を飼う牧草地(ぼくそうち)に作りかえる計画を立て,はい水路(すいろ)をほって水がぬけやすくする工事を行いました。しかし,牧草も生えにくく,気温が低いためにうまくいきませんでした。かんそうが進んだ湿地は湿地ではなくなっていきました。
すると,もともと湿地にいた植物や動物が姿(すがた)を消していきました。湿原の生き物は全てつながりをもって生活をしているので八幡湿原全体の自然がこわされてしまったのです。また,湿地は自然のダムのやくわりを果たしていたので,水害(すいがい)もおこるようになりました。
 牧草地にしようとしていたころの様子 |
いなくなってしまった生き物 オオジシギ |
 ホオアカ |
牧草地を湿原にもどす
広島県や北広島町は平成16年に「八幡湿原(やわたしつげん)自然再生(しぜん)協議会(さいせいきょうぎかい)」をつくり,地域の人々も協力をして,湿原をもとにもどす取組を始めました。
まず,湿原には生えないはずの大きな木を切りました。次に,はい水路をせきとめて水がいきわたりやすいようにして,湿った土地にしていきました。そしてコンクリートで囲(かこ)まれた川をもとの川にもどし,木の道をつけて湿原になっているか観察を続けました。
人々の努力によって,湿原はしだいに元のすがたをとりもどし,湿原の美しい花を見に来る人がおとずれるようになりました。
もどってきた生き物 モリアオガエル |
 カスミサンショウウオ |
草原(そうげん)を守る(北広島町雲月山(うんげつさん)) |
消えていった草原と生き物
草原は明治(めいじ)時代までは日本全国にありました。それは,農作業などで一緒(いっしょ)に働いていた牛を放牧(ほうぼく)したり,牧草(ぼくそう)を育てたりしていたからです。しかし,農作業が機械(きかい)で行われるようになると,牛は飼(か)われなくなり,エサがいらなくなったために,草原はほとんど見られなくなりました。草原は人が春に山焼(やまや)きを行うことで木が育たず草だけが育ってできるものですから,山焼きが行われなくなって,日本中の草原が森にかわって行きました。
それと同時に,草原の生き物も住む場所がなくなり,どんどん消えていったのです。
| 明治時代は日本の国土の30%が草原でしたが,現在は1%以下にへっています。 |
 |
| なぜ北広島町の人は,草原をとりもどそうとしているのだろうか。 |  |
| 草原の生き物 |
 リンドウ |
 アキノキリンソウ |
 マルハナバチ |
 クマタカ |
草原をとりもどす
「高原の自然館」の白川さんのよびかけにこたえた北広島町の人たちや,草原をとりもどそうというボランティアの人たちで,雲月山(うんげつざん)の山焼きが行われるようになりました。
雲月山(うんげつざん)の山焼きは10年前(平成17年)から毎年春に行われています。地域の人はもちろん広島県内や遠くの県から来たボランティアの人たちが協力して行います。
地元の雲月小学校の子どもたちは,山焼きの説明(せつめい)をしたり,手伝いをしたりしています。また,草原を守る大切さをオペレッタにしていろいろな場所で発表をしています。
山焼きを始めて,雲月山では牛の放牧(ほうぼく)をする農家の人もあらわれました。また,ササユリやレンゲツツジなどの植物が増えてきました。雲月山では,野うさぎやクマタカが見られるようになり,休日はハイキングを楽しむ人たちも山におとずれています。
 |  |
| 山焼きの手順(てじゅん) |
| 火が広がらないための道(幅5~10m)を草をかって作る。 |
| ↓ |
| かった草を手作業で運ぶ。 |
| ↓ |
| 一気に火が広がらないように山頂から火をつける。 |
| ↓ |
| 3分の1燃えたら,下から火をつけ,中央で消えるようにする。(風下から燃やす) |
| ↓ |
| みんなで水を持って完全に消えるまでみはる。 |
 山焼きの説明をする雲月小学校の子どもたち |
 オペレッタ「雲月のたから」 |
 |
山焼きのボランティアに来た人たちの話
「たくさんの人となかよくなれて,協力することのすばらしさを感じた。」
「この山焼きは,いろいろな年代の人がいて,人と自然とのかかわりがよくわかるので何年も先まで続けてほしい。」
「雲月小学校の発表と歌に地域をほこりに思う心を感じた。」
北広島町の自然を守る歩み(年表)
| 八幡湿原での取組み | 雲月山での取組み | |||
| 年 | 内容 | 年 | 内容 | |
| 平成14年 | 植物の調査と,湿原を守っていくための話し合いがはじめて行われた。 | 平成15年 | 山焼きを再び始めるそうだんが始まった。 | |
| 平成15年 | サンショウウオ,昆虫,鳥,植物など,色々な生きもの調査が始まった。 | 平成17年 | 山焼きボランティアの募集(ぼしゅう)が始まった。 | |
| 「自然再生協議会」がつくられた。 | 雲月小学校が山焼きの学習を始めた。 | |||
| 地下水を調べる調査が始まった。 | 150人のボランティアが協力して,山焼きが再開した。 | |||
| 平成16年 | 牧場跡地に溝を掘って湿原再生の実験が始まった。 | 平成18年 | 小学校も山焼きの作業にさんかするようになった。 | |
| 平成19年 | 自然再生の工事が始まった。 | 雲月山の歌「I Love Uzutsuki」が作られた。 | ||
| 平成21年 | 工事が完了して,遊歩道がつけられた。 | オペレッタ「雲月のたから」が作られ,上演された。 | ||
| 平成22年 | 工事の効果(こうか)を調べる調査が始まった。 | 平成22年 | 写真集「雲月のたから」が発行された。 | |
| 北広島町の人々のいろいろな努力によって,たくさんの生物が守られているのだね。 |  |