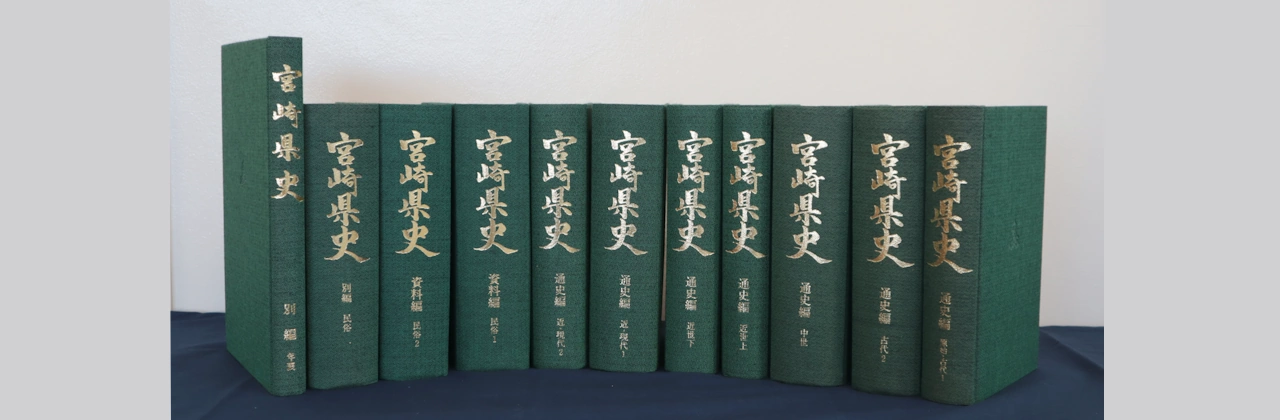公開にあたっての留意事項
今回の『宮崎県史』デジタル公開にあたっては、該当箇所を修正せずに本書の刊行当時のままにしています。今回の公開にあたり、補足すべき事項について下記にまとめました。
刊本画像のマスキング処理について
搭載した画像のうち、権利処理等ができない箇所(写真ほか)についてはマスキング処理を行っています。
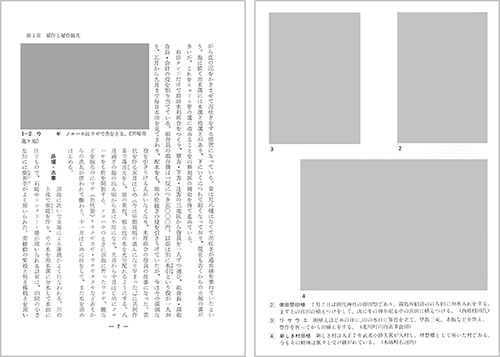 マスキング画像例
マスキング画像例
1『通史編 原始・古代1』
(1)平成12年(2000)に東北文化研究所の藤村新一氏による前・中期旧石器・遺跡捏造事件が明らかになりました。
<参考>前・中期旧石器問題調査研究特別委員会編 2003『前・中期旧石器問題の検証』、日本考古学協会
毎日新聞旧石器遺跡取材班著 2001『発掘捏造』毎日新聞社
※その後2003年に同タイトル、同著者で新潮社から文庫本として刊行
本書は、平成9年(1997)に刊行されました。同事件で捏造が発覚した宮城県座散乱木遺跡、馬場壇A遺跡、高森遺跡、上高森遺跡等についても引用していますが、下表のとおりそのまま公開しています。
- 1 この巻へのいざない
- ⅱ
- とくに西日本において最古とも考えられている後牟田遺跡(川南町)の紹介などは、全国的な視点に立っても注目されるものである。
- 2 第一章
- 界紙裏
- 旧石器時代の略年表 該当する事項及び主要遺跡 前期旧石器時代(日本) 上高森遺跡(宮城県)
- 3 第一章
- 第1節 p83 15行目~p84 3行目
-
第一章 旧石器文化の成立と県内の文化の幕開け
第一節 旧石器文化の概観と県内の特色
一 旧石器文化のはじまり
日本列島のヒトと痕跡
…旧石器文化の概観と県内の特色 日本列島のヒトの痕跡 (15行目から)最近、東北地方を中心にして原人や求人と同じ時代の遺跡が相次いで発見されている。とくに、平成五~六年(一九九三~九四)にかけての上高森遺跡(宮城県)の発掘調査で、東北旧石器文化研究所がみつけた古い石器が出土した地層を理化学的な方法で調べたところ、六〇万年頃の地層であることがわかった。六〇万年以上も前の地層から人類が使用した石器がみつかったことで、日本にも北京原人と同じころにすでに人類が暮らしていたことが証明された。 - 5 第一章
- 第1節 p85 16行目~17行目
-
旧石器時代は新しい学問
…その後、各地で旧石器文化の遺跡が相次いで発掘調査され、発見される遺跡の年代も五万年前、二〇万年前と年々さかのぼっている。 - 6 第一章
- 第1節 p87 6行目~7行目
-
旧石器時代と先土器時代
…しかし、最近では原人や旧人の時期の比較的古い石器時代の遺跡が相次ぎ発見されていることから、… - 7 第一章
- 第1節 p88 2行目~7行目
-
二 旧石器時代の時代区分
三つの時代区分
…そこで、日本では現在、およそ三万年前ごろを境に、それより古い時期を前期旧石器時代、新しい時期を後期旧石器時代とする時代区分がよく使われている。前期旧石器時代は、世界史で使われている前期旧石器時代と中期旧石器時代を含んでいる。左記に紹介した上高森遺跡(宮城県)が六〇万年前の遺跡としては、現在日本でもっとも古い遺跡である。また、十数万年前の遺跡として、座散乱木遺跡(同)や、馬場壇A遺跡(同)などがあるが、遺跡の数はまだ少ない。 - 8 第一章
- 第1節 p88 14行~15行
- …本巻でも、前期旧石器文化(~三万年前)・ナイフ形石器文化(三万~一万四〇〇〇年前)とする時代区分を用いそれぞれの時代の様相を展開する。
- 9 第一章
- 第1節 p88 16行~p89 13行
-
前期旧石器文化
上高森遺跡(宮城県)や馬場壇A遺跡(同)など数十万年前の遺跡で発見される石器のなかには、手のひらで握るのにちょうど良い大きさの大型の石器や指先でつまむのに適当な大きさの小型の石器が多く見られる。これらの石器は形や座漁の石(原石)はまちまちで、大型の石器も原石をある程度打ち欠いただけのものが多く、小型の石器も原石から一、二点の切片を剥ぎ取っただけの剥片(原石からはぎ取られた石片)を加工してつくられている。七万~八万前ごろになると、形やつくり方が似通った石器もみられるようになる。槍先に用いたと思われる斜軸尖頭器(先端が鋭く尖った石器)と呼ばれる石器は横に長い剥片の一か所を部分的に加工し、鋭い縁を選んで刃の部分にしている。さらに、四万~五万年前ごろには両面を加工した石斧、鋸刃状の石器、錐状の石器など石器の種類も増えてくる。 - 10 第一章
- 第1節 p90 2行~3行
- …しかし、最近、福岡県北九州市の遠賀川流域の辻田遺跡では、凝灰岩でつくられた尖頭器(斜軸尖頭器)や錐のような石器が数点見つかり、四万~九万年前の前期旧石器の石器として注目されている。
- 11 第一章
- 第1節 p97 2行~10行
-
三 県内の旧石器文化の特色
前期旧石器文化
前期旧石器文化においては、本県でもっとも古い人類の痕跡はいつごろのことかということが問題となる。確実に前期旧石器時代のものとして認定された遺跡はまだ現れていないが、後牟田遺跡(川南町)や出羽洞穴(日之影町)で前期旧石器時代と思われる石器がみつかっている。しかし、後牟田遺跡では、今から三万年代まではさかのぼると思われる石器群がみつかっているが、その時期を確定するテフラの正確な年代がわかっていないことから、石器群の時期もはっきりしていない。また、出羽洞穴でも四万年前ごろと思われる石器群がみつかっているが、洞穴遺跡であるため、出土した地層の年代決定が難しい状況である。いずれにしろ県内でもっとも古い人類の痕跡は、三万~四万年前ごろの前期旧石器時代の終わりごろになりそうである。 - 12 第一章
- 第1節 p100 図1-6 県内の旧石器時代石器の変遷
- 前期旧石器時代(?)
- 13 第一章
- 第2節 p101-106
-
第二節 県内の旧石器文化の展開
「一 最古の旧石器文化」の全文
(小項目名「後牟田遺跡の発見」「十枚の文化層」「出羽洞穴出土の石器」)
※日本に前期旧石器があるとの認識で書かれている。(宮崎県内の遺跡で前期旧石器と確実なものは無いとしている。) - 14 第一章
- 第3節 p133 11行から12行
-
二 道具と道具つくり
狩りをする道具
…尖頭器の仲間には、ナイフ形石器文化以前にみられた小型の尖頭器や、横長の剥片の一端を加工して尖らせた斜軸尖頭器、・・・
※この欄の「斜軸尖頭器」は前期旧石器を代表する石器として記載されている。 - 15 第一章
- 第4節 p141 15行
-
第四節 旧石器文化から縄文文化へ
二 新しい文化の芽生え
石槍から弓矢へ
…前期旧石器時代の尖頭器や、… - 16 後章
- p598 12行~16行
-
後章 本県の考古学上の諸問題と展望
第一節 本県の考古学研究の回顧と展望
一 旧石器時代
1はじめに
(1)旧石器文化研究五〇周年
…しかし、前期旧石器文化の存在については昭和五十年(一九七五)に宮城県で結成された石器文化談話会という民間の研究機関の活動が解決してくれた。昭和五十六年(一九八一)の座散乱木遺跡(宮城県)の第三次調査で見つかった石器は三万年よりさかのぼる石器として、学界でもおおむね認められた。その後も、石器文化談話会の調査で同じ宮城県内で十数万年前の馬場壇A遺跡や、五〇~六〇万年前の上高地遺跡などが見つかっている。これらの前期旧石器時代遺跡の年代判断にはさまざまなかたちで自然科学分野の分析が使われている。 - 17 後章
- p603 11行~16行
-
2本県の旧石器研究小史
(4)本格的調査の時期
…さらに、平成五年(一九九三)に調査された後牟田遺跡では三万年より古い前期旧石器時代と思われる石器が発見された。しかし、今のところ、霧島イワオコシ火山灰層(推定三万八〇〇〇年~七万年前)の値上の地層から発見された石器群は火山灰の正確な噴出年代が不明である。また、直下層から出土した人為的な化工石は石器の判断が分かれるところである。しかし、いずれにしろ前期旧石器文化を検討するには重要な資料であり、本県のみなら西日本地域での前期旧石器文化の存在を一度検討する契機となった。 - 18 後章
- p603 11行~16行
-
3今後の課題と展望
(2)将来への展望
…さらには後牟田遺跡の再検討も含め前期旧石器時代遺跡の確認など多くの問題点を抱えているが、いずれも現実味のある可能性を十分に残している。
(2)昭和32(1957)年に豊橋市内牛川町の採石場で発見された化石は当時人骨と鈴木尚氏(東京大学教授)により鑑定されていましたが、平成13(2001)年頃から動物の骨とする異説もあり、令和4(2024)年に東京大学総合研究博物館の諏訪元特任教授らの研究グループにより、ヒグマの可能性が高いと結論づけられています。今回は刊行当時のまま下記のとおり公開しています。
<参考>諏訪元・佐宗亜衣子・佐々木智彦・中村凱・遠藤秀紀・松浦秀治 2024「「牛川人骨」の部位・動物種別の特定と学史略考」『Anthropological
Science(Japanese Series)advpub(0)』日本人類学会
- 第一章
- 第1節 p84 4行目~5行目
- …さらに、旧人の時代の遺跡も馬場壇A遺跡(宮城県)、座散乱木遺跡(同)など東日本を中心に、十数か所で発見されており、愛知県の豊橋でみつかった牛川人骨は旧人の化石人骨と推測されている。
(3)p701の図後-11「魯国故城52号墳出土の玉壁」正確には「「魯国故城52号墳出土の玉壁の拓本」であり、またこの拓本の図を「山口県立美術館提供」とのみしていますが、正確には山東省文物事業管理局より提供された画像が掲載された図録『大黄河文明お流れ 山東省文物展』(西部美術館、朝日新聞社、1986年)から転載したものです。
2『宮崎県史 通史編 中世』
(1)p1055の写真5-31「遣明舟模型」は「広島県立博物館所蔵」とのみ記載していますが、正確には「広島県立博物館所蔵・画像提供」です。
3『宮崎県史 資料編 民俗2』
(1)口絵11の写真 銀鏡神楽(宿神三宝荒神)は、写真家 芥川仁氏の提供によるものです。