実名:光誠(みつしげ)
※昨今の研究成果により実名は「光誠」と判明しました。
挙誠(きよしげ)が家を継いだ直後、仁賀保地域の周辺の国は大混乱に陥っていましたが、挙誠は混乱に巻き込まれることなく、戦略的に行動しました。1588年には長年にわたって争いを続けていた矢島家との戦争を終結させ、敵を倒した後も無益な争いを避け、地域の平和を保とうとしました。さらに、関ヶ原の戦いでは徳川家康の側につき、重要な役割を果たすなど、冷静な判断力と強い責任感で歴史の大きな変動にも対応していきました。このように、挙誠は激しい戦乱の時代にあっても冷静さを失わず、地域と家族を守る武将でした。

にかほでの食生活や娯楽

詳細を見る
にかほ(仁賀保) という名字(地名)

詳細を見る

秋田県にかほ市の「にかほ」という地名の由来をご存じでしょうか。中世から近世にかけて、この地は「仁賀保郷(にかほごう)」と呼ばれ、領地名を名字とした武士の一族、仁賀保氏が治めていました。
鳥海山や日本海に囲まれた自然豊かな土地であるにかほ市を治めていた仁賀保氏は、地域の発展と統治に大きく貢献しました。彼らの歴史をたどることで、学校で学んだ歴史上の人物や出来事とも関連付けて理解を深めることができるでしょう。

遡ること、鎌倉時代。由利郡地域を治めた由利維久に代わり、信州の小笠原氏の分家である大井氏が地を支配するようになりました。
1467年、大井友挙(ともきよ)が仁賀保郷に移り住み、これが仁賀保氏の始まりです。息子、挙政(きよまさ)は姓を「大井」から「仁賀保」に改め、孫の挙久(きよひさ)の代には周辺の地域と戦いを繰り広げました。中でも長年のライバルとなる矢島氏との間で40年以上にわたる戦いが続きましたが、1576年に挙久は敗れて討たれました。彼の後を継いだ挙長(きよなが)も翌年に亡くなり、継ぐ重挙(しげきよ)は、争いの中で家臣に討たれました。重挙の後を継いだ挙晴(きよはる)もまた、1586年に家臣の裏切りで命を落としました。このような乱世の中、にかほ市を治める挙誠(きよしげ)が生まれました。

挙誠(きよしげ)が家督を継いだ1585年、隣国の出羽庄内地方は戦乱の渦中にありました。豊臣秀吉は私的な争いを禁じる「惣無事令」を発布し、配下の最上義光が庄内地方の戦を治めようとしました。最上義光は秀吉の権威を利用して支配を強めようとし、挙誠にも協力を求めましたが、挙誠はこれを無視しました。結果、最上義光は和議の仲介を他の勢力に頼ることになりました。最上義光は羽の諸侯や国人領主たちから完全な信頼を得るには至らず、最終的な勝利を収めることができませんでした。このように挙誠は知略を持って豊臣政権との関係を保ちつつ仁賀保地域を守っておりました。

挙誠(きよしげ)の最も大きな功績の一つは、矢島氏との長年にわたる戦いを終わらせ、矢島領を掌握したことです。1588年和平交渉が失敗した後も挙誠は矢島満安に対して軍事的勝利を収めました。他の由利衆の支援を得て戦った挙誠は、満安を討ち取り、矢島氏を滅亡に追い込みました。この勝利によって、仁賀保氏は矢島領を完全に支配下に置き、由利地方での影響力を大幅に拡大させました。挙誠の戦略的な判断力と軍事的リーダーシップが際立つ瞬間でした。
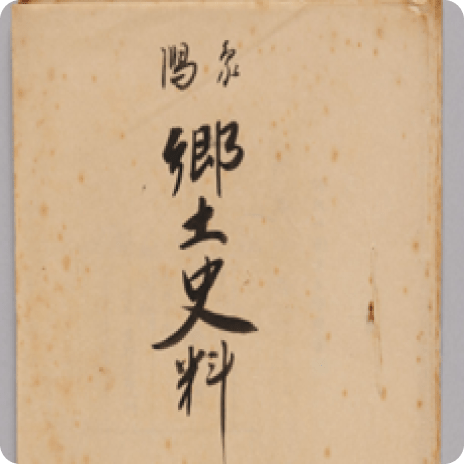
挙誠(きよしげ)は豊臣秀吉に仕え小田原征伐や奥羽仕置に参加しました。仁賀保氏は公式には3,716石の領地を持っているとされていますが、実際には1万石以上ではなかったかと考えられます。挙誠は広大な領地を管理し、秀吉政権下でも重要な役割を果たしました。しかし、関ヶ原の戦い後、彼は常陸武田(現在の茨城県)に移され、5000石の所領を与えられ、新領地で統治を続けました。晩年には旧領で一揆が発生し、仁賀保氏の影響力は縮小しましたが、挙誠の功績は歴史に刻まれています。
仁賀保郷復帰後は、現在の象潟町塩越の塩越城に居住し、象潟地区の基礎を作った人物でもあります。

発掘されたものや残された手紙から推察すると、「茶道」や「能楽」は人並みにたしなんでいたようです。次男誠政の義理の父親である桑山貞晴(くわやまさだはる)という武将兼茶人は、千利休の長男である千道安(せんのどうあん)や古田織部(ふるたおりべ)から茶の湯を学んだ人物です。また、茶道・能楽などのほか、鷹の献上や馬の献上の文書がみられることから、鷹狩や乗馬もこなしていたと推測されます。