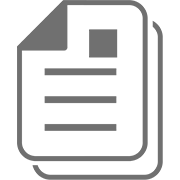
|
図書
|
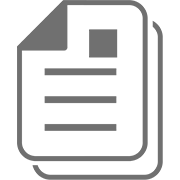
|
岡山ゆかりの図書(郷土の図書)を収録しています。手写本を含む江戸時代以降の古い書物もあります。儒教・仏教の書、歴史書、藩士帳などの人名録、岡山藩領や岡山市街の地誌、さまざまな観光案内、医学書、旅日記と日誌、漢詩・和歌・俳諧ほかの文学書、図書館とその蔵書についての書など多岐にわたります。燕々文庫、山田文庫、河本文庫等の特別文庫に含まれる図書資料はここからも探せます。一枚もののパンフレット類や、施設・建物の図面、見取図等もここに含まれます。
|
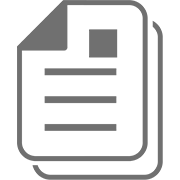
|
古文書
|
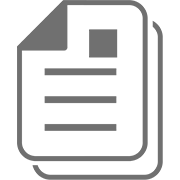
|
江戸時代の藩政下の社会を知るための文書記録が中心です。岡山城下町(町方)では国富家の文書(国富文庫)の大部分を、岡山藩領のその他の地域(在方)では藤原家と安井家の文書(藤原文庫と安井文庫)の一部を中心に、上道郡で村役人を務めた小西家と笠井家の文書のいくつかを収録しています。いずれも城下町や村々で役職に就き、地域の行政に携わった人々が残した事務の記録や帳簿類がおもな内容です。家ごとに収録しているため、引き続き行政に携わった場合等では明治期以降の文書も含んでいます。
|
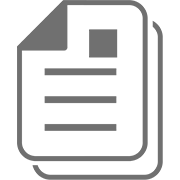
|
行政資料
|
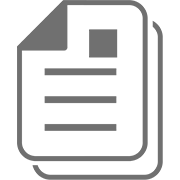
|
岡山市や岡山市と合併した近隣自治体からの引継文書を収録しています。中心は近代以降に役場等で作成された公文書(歴史公文書)で、時期は明治期の地方行政の創始期から第二次世界大戦後の復興期にわたっています。しかし、江戸時代に作成された古い文書で各地の役場が保管してきたものも多く、ここにはそれらも含めています。その内容は、土地台帳(検地帳等)や、紛争(水争いや境界画定等)における裁許状、契約書、権利書など、個々の行政事務よりも地域全体の利害に関わる証拠文書が多いようです。また、明治初期に各村で作成された村誌も収録しました。
|
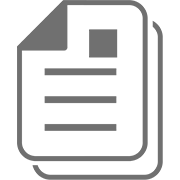
|
絵図・地図
|
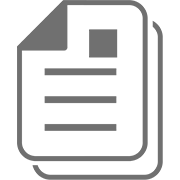
|
地域を空間の広がりの中で理解するのに不可欠なのが地図ですが、近代的な測量法の導入前に概念的に描かれたものは絵図と呼ばれ、ここにはそれらも近代以降の地図とあわせて収録しています。江戸期から明治期までしばしば作成された一村全体の絵図は、その多くが個々の耕作地を描き分けたもので、地租の徴収のため土地台帳と連動して使用されました。絵図はそのほかにも、河川・用水の管理や、村・漁場・猟場等の境界確定、災害時の被災状況の説明など、さまざまな目的のために作られました。こうした絵図は、各地の役場や村役人を勤めた人の家に伝わってきました。
|
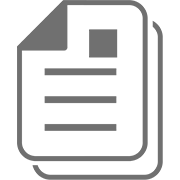
|
書画その他
|
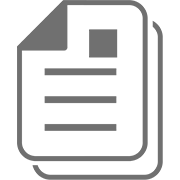
|
当館には、岡山ゆかりの人の書跡や絵画も多数所蔵されていますが、それらは河本家、木畑家、国富家などから文書とあわせて受け入れたものや、郷土史家の岡長平氏の収集品など、多くの方からの寄贈によっています。また、錦絵と正月用の引札からは、版画と印刷の高い技術を見ることができます。児童文学の分野で顕著な業績のあった文学者、坪田譲治氏の書や身辺の資料もここに含めています。奈良時代に作成された百万塔に収められていた陀羅尼経は、現存する中では年代が明確な世界最古の印刷物といわれ、そのひとつが昭和26年に吉田書店代表の吉田信一氏から当館へ寄贈されています。
|
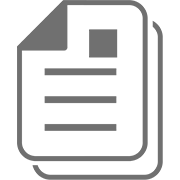
|
写真・絵葉書
|
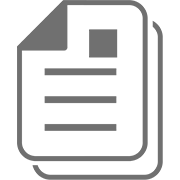
|
ここにはおもに、岡山の自然環境や動植物を撮影した写真家、内山峰人氏から寄贈された市内日応寺地区の自然の写真と、戦後の岡山市史の編纂を通じて撮影・収集され、高度経済成長期の昭和30年代から昭和40年代初頭にかけて急激に移り変わる市街の様子を捉えた写真の一部を収録しています。また、歴史家の木畑道夫氏が残した明治初期の岡山城その他の写真、および岡山県の土木技手として大正期の京橋架け替えに携わった小西隆氏(上道郡の大庄屋、小西家の子孫で、後に岡山市助役を勤める)が残した京橋竣工時の写真等も収録し、古い絵葉書の資料も含めています。
|
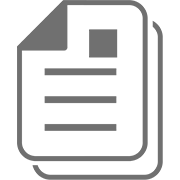
|
調べ方ガイド
|
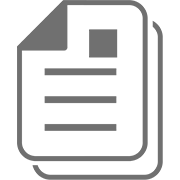
|
|