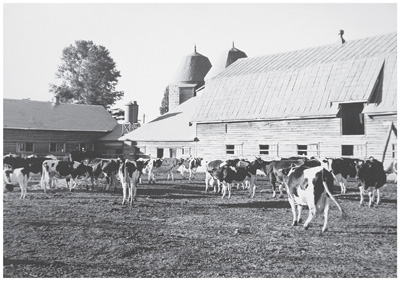戦時中の生活
〔勤労奉仕〕
私が生まれたところは庄野です。庄野の小学校に6年行って、高等科に2年間行きました。小学校の時に勤労奉仕で農家の手伝いとか茶摘みなんかをしました。先生が「どこどこの家に百姓の仕事を手伝いに行って下さい」って言うんで、サツマイモを植えたり、草取りをしたりしてました。兵隊に行ってみえる家は、手が少ないもんでそこに手伝いに行くんですね。みんな3,4人で分かれて行きましたね。毎日じゃなくて、「手伝いに行ったって」って言われた時だけ行くんです。学校から言われなくてもね、近くの家の方へは「手が少ないで手伝ってんか」って言われて手伝ってましたよ。亀山の女子師範学校にいた時には、接ぎ木をしにも行きましたよ。植林作業ですね。寄宿舎に泊って、そこから行ったんですよ。昭和16年か17年頃の話ですね。
〔出征〕
私の2つ違いの弟はね、兵隊に行って何年後かに、「特攻隊に行くでみんなに挨拶に来ました」ってお別れを言いに来たんですよ。悲しかったけどね、お国のためならしょうがないなって思いましたね。本当は行ってほしくなかったけどね、当時はみんなお国のために頑張ってるから「頑張って来てな」って言って別れました。終戦になって、弟は帰ってきました。特攻に行かなくて済んだんですね。その弟も2年くらい前に亡くなりました。
地域の方で出征された方の見送りにも行きました。なんやらさみしい気持ちでした。それでも、みんな国のためだからね、仕方ないって思ってたんでしょうね。でも、私はその時にめでたいって言って良いのか悪いのか迷いました。私らの友達やその下の弟達も、ようけ行ってるでね。周りの若い男の人はみんな行きましたよ。その人らも行かなあかんって覚悟があったんでしょうね。ようけ亡くなってますよ。その忠魂碑がね、庄野のお墓に建っとるでしょ。亡くなった方の名前が刻まれた石碑がね。あれを見ると、あの人も亡くなったよ、この人も亡くなったよって思って、すごく悲しかったですよ。慰霊碑の前で頭を深く下げました。お国のために尽くしてもらったんやでね。
〔国防婦人会〕
私は、勤めていたから国防婦人会には入りませんだけど、国防婦人会の方が出征兵士を送ったり、お百姓さんの忙しい家に行ったりしてました。私らも手伝いに行くけど、国防婦人会の人らも行っとったな。国防婦人会には、私からいうと年とった人や年配の人が1つの団体をつくっとったわけ。30代、40代、もっと年とった人もいましたね。ほとんどの女の方は自然と国防婦人会に入るわけですね。
当時は廃品回収をして婦人会の活動資金にしてたみたいです。主に新聞やら雑誌、衣類なんかも集めてきて、それを買うてくれる人らがおったんで、その人らに売ってね。
〔食べ物〕
家は農業をしていてね、1町くらい米を作ってましたね。百姓の家でしたから米はありました。でも、供出がありましたから、米を出さなあかんだで飯米は少なかったです。だから、ご飯にイモを入れて芋飯にしたり、えまし麦がいっぱい入った黒いご飯をよう食べさせられたね。それから、すいとんってあったんです。みそ汁の中に小麦粉をどろっと溶かしたものを落したものなんです。すいとんにすると、ただのみそ汁より量が増えるでしょ。それもよう食べましたに。この前もね、お友達と若い時の話をしとって「あのすいとんが食べたいな」って言ってたんです。昔のすいとんって今の人は知らないでしょ。おなかも膨れるしおいしいしね。そうやって昔はお腹を膨らませてたんですよ。
おやつも今のようなものはありませんよ。百姓の家はお米をついて、あられやかき餅にして食べました。それがおやつだったんです。今のようにガスがないですから、炭火をおこしてあられを炒ったり、かき餅を1枚づつ焼いたりしてたんですよ。イモの蒸したのもよう食べましたな。家の隣がお菓子屋さんで飴をようけ作ってましたから、時々その飴を貰うこともありましたね。黒砂糖で作った飴だったのかな、なんせ黒い色をしていたのは覚えてます。それはめずらしいしおいしかったですよ。
私も百姓の家やったから助かったんやな。貧しいっていうても、そこまで不自由はしなかったものねぇ。
度会での教員生活と敗戦
学校を卒業してね、私は度会郡南島町東宮、奈屋ってところにある鵜倉小学校に先生として就職したんですわ。志摩半島のところですから、B29が頭の上をずーっと飛んでいくんですよ。そうするとサイレンが鳴って、また飛んできたなって思って、みんなで防空壕に入って避難をするんです。防空壕から出てくるとラジオから「伊勢に焼夷弾を落とした。四日市に焼夷弾を落とした」って聞くんですよ。その時に「あぁ、これが本当の戦争なんやな」って実感したんですわ。東宮、奈屋はB29が飛んできただけで、そんなに被害はなかったけど、焼夷弾を落とされて家が焼けとるって言われると本当に怖いことやなって思った。それと同時に、伊勢や四日市の人は気の毒やなとも思いましたな。
鵜倉小学校にいた頃は、民家に下宿させてもらって2年半くらいそちらにいました。その後、転勤になって石薬師の小学校に移ってきたんですよ。
玉音放送は鈴鹿で聞いたんか、度会の方で聞いたんか、ちょっと覚えがないんですけど、隣の家のラジオで聞いたことは覚えてるんですよ。天皇の声を聞いた時にね、涙が出てきました。まさか日本が負けるとは思ってなかったしね。日本は神の国だから、いつかは勝つんだと信じてました。だから、敗戦を知った時は「それ本当?」って思いましたね。
終戦になってからは、鈴鹿の土地にも進駐軍の兵隊さんがようけみえて、その兵隊さんからチョコレートを貰った人がようけいましたに。私は正直喜んで良いのか悪いのかよくわかりませんだ。
買出し部隊
終戦後もみんな食べ物や着る物がなくて困りましたね。私の家は百姓だったからどうにか自給自足の生活をやっていけたけど、奈良や京都の人はたくさん買い出しに汽車に乗ってこちらまでやってきてました。私の家にもお米があると思って、自分ところの着物を、それもできるだけ着古したのじゃなくて大事に取ってあったのをね、それを持ってきてお米と替えっこしたんです。買い出しにみえた方がお米を背中にどっさりおいねて(背負って)帰っていかれるのを見て、大変だなって思いましたよ。
私の母親がね、その時に交換した着物を私が嫁に行く時に持たしてくれたのを今でも覚えています。私らには着物ってようけなかったから、母親が大切に残しといてくれたんですね。「あんたに何にも買えやんで、この着物を箪笥の中に入れといて、また着るやわ」って言うて持たせてくれたんです。着る物もほとんど買ってもらわんだからね。持たせてくれた着物は3枚か4枚くらいあったかな。それは着やへんだけどね、今でも大事に箪笥にしまってありますよ。親から貰ってきたもんやで大事にしとる。
当時は、服もね、私らはあんまり買ったりしなかったんですよ。私も勤めてましたからそんなに服もいらなかったしね。その内に毛糸の服が流行りだしたんですよ。お金持ちの家やと早いこと毛糸の服を着られるようになってましたけどね。
戦後の生活
私自身は、石薬師の小学校から庄野の小学校に移って、そこから加佐登の小学校に行って、最後に飯野の小学校に行ったんです。全部で26年間先生をしてました。辞めた時は45歳だったかな。主人が高山の方に転勤になったので、その時に辞めたんですよ。
戦後の鈴鹿市はね、工廠の後に店や住宅がたくさん出来て、中央道路は今の神戸よりにぎやかな町並みに変化していったでしょ。そうやって目に見えてにぎやかになっていく姿を見る事ができ
嬉しかったです。あぁこれで戦争のない平和な毎日が送れるのかなってそう思いましたね。