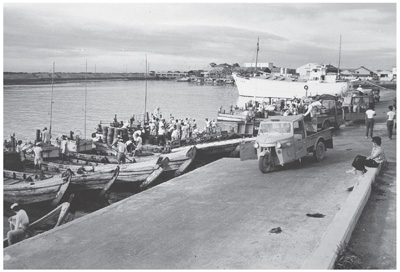神戸中学校時代の思い出
私は白子で生まれました。昭和12年4月神戸中学に入学、中学1年生になった年の7月7日盧溝橋事件が起きました。いわゆる日華事変ですね。
神戸中学校には、伝統的に「質実剛健」という学校の方針がありました。それが立派な神戸中学生だということです。ところが、校長によってこんなにも学校の空気が変わるのかということを私は実感しました。といいますのは、私が中学校にいた5年間に校長が4人変わってるんです、上のご都合でね。ある年、典型的な東大出の官僚が30代で校長としてやって来たんです。そうすると、その校長の息のかかった先生を全国から連れてくるんですよ。その中には自由主義的な先生もいましてね。当時は「サッカーなんて敵国の遊びだ(禁制)」と言ってる頃です。でも、その先生はサッカーが好きで、蹴球部を作るって言って、生徒と一緒に遊んでくれたんですね。そんな先生がその校長の時には何人か来ましたね。でも、そうすると前からいた先生と先生同士でぶつかりますよね。子供ながらにそういうのを見ています。その後、神宮皇学館出の校長がやって来たんですが、もう天地の差がありましたね。
他にも、ある校長でリベラル派、自由主義派の人がいて、その人がなんと芸者遊びをする人だったんです。神戸っていうのは当時遊郭があったんで上級生の中には、ませたのが遊郭に遊びに行きました。中学生っていったって5年制ですからね、今でいったら高校の2年生、3年生でませてますよ。
三重師範学校に進学
私の親父は、農業をやりながら白子町役場にも勤めていました。役場では、土地改良の方に携わってましてね。鈴鹿川の上流から水を引いて白江野用水っていうのを作りました。白子、江島、野町っていうんですけど、そこに跨る灌漑用水ですね。
ですから、一応親父はこの辺りのリーダー格でね。だから、普通であれば長男の私が跡を継ぐはずだったんですが、私は教員になりました。役場に行くのも嫌だったし、親父の兄弟の一番下がたまたま教員になっていましたからね、それの影響がなかったと言えば嘘になるんでしょうね。それとね、その当時、師範学校に行きますと兵役猶予があったわけです。だから、反戦という意志はなかったですけど、叔父が衛生兵で薬屋をしていたので軍隊の裏の話も教えてくれて、兵隊に行きたくなくて、三重師範学校に行ったんです。
三重師範学校には1部と2部がありました。私は三重師範学校の2部に入ったわけです。昔は全寮制ですから、私どもはみな寮に入ってました。寮生活が一つの教育の場でしたからね。寄宿舎は学校に併設してました。あの頃の寮生活は軍隊の小型版ですね。上下関係は非常に厳しかったですよ。特に1部というのは高等科から来てますから、1年生っていうのは中学の3年生にあたります。それで、私どもは中学5年を卒業してから入りますから、同じ年齢でも1部の方が師範学校の中では先輩になるわけですよ。だから、1部と2部は常に対立してましたね。昭和19年ぐらいになると、1部と2部が合併しましたけど、やっぱりしこりはとれなかったですね。
寄宿舎生活でも、1年生から5年生まで相部屋で1部も2部も混合でしたから、上級生が非常に権力をもってました。下級生を殴る蹴るでね。それから、寄宿舎から夜遊びに行くのは、当時「脱柵」といってました。あの時は自由じゃなかったから、外に行くことが楽しみなんです。津の阿漕の方の遊郭に行ったりね。外に遊びに行く者は心置きなく遊べるように民家の離れを借りて‘巣’をつくってましたね。
三重師範学校も本来は3年で卒業なんですが、当時は、いわゆる繰り上げで半年早い昭和19年の9月の卒業でした。その上、2年半の内の最後の半年は戦時体制で本当の勉強はしてない。学徒動員です。私どもは陸軍造兵廠楠工場に行きました。学校がどこに行くかを決めてましたから、どこに動員になるかわからないわけです。たまたま私は楠でしたから家から通いましたが、その中には木本(熊野)から来ていた同級生もいました。彼とは仲が良かったんで、10日間くらい家に泊めてやりました。その後も知り合いの家に下宿させたり、そんなことは自由にできました。
陸軍造兵廠楠工場では、対戦車砲の部品作りをしてましたね。そこで初めてボール盤とか旋盤とかの使い方を教わりました。それから、不合格品を「オシャカ」といいますね、そんな言葉も工員さんから教えてもらいましたね。初めの頃はオシャカばっかりでしたよ。
教員生活と軍隊生活
三重師範学校を卒業して、昭和19年の10月に赴任先の多気郡三瀬谷国民学校に行きました。多気郡で一番生徒数が多い学校でした。三瀬谷国民学校には社会主義の教員もおりましたし、カチンカチンの国粋主義の教員もおりましたよ。
ある時、教員が校長に対してストライキを起こしたことがあったんです。当時の校長が全体主義的で、教頭がそれに反対してましてね。日本人の悪い癖ですね、セクトっていうか、赴任すると校長派か教頭派かに分かれるんです。私も正義感からというか、若気の至りで教頭派に入りました。私以外にも教頭派には5,6人おりまして、(教頭が前に出るような人ではなかったので)そのリーダー格になったのが、教頭の下におった社会主義的な男の先生でした。校長の独断的なやり方に反対して校長を缶詰にしましてね、帰さなかった。私は、ストライキの後で長ケの分校に派遣されました。校長の差配でしょうね、要するに追い出されたわけです。
そうこうしているうちに、私にも赤紙が届きました。昭和20年の4月のことでした。実家の親父から連絡があって、それから10日間くらいして、現役の二等兵として久居の連隊に入りました。出征する時は、近所の人と家族や親類が来て、武運を祈るってことでお宮さんへ行ってね。それから駅のホームまで送ってくれるのは家族、親戚でした。そこで儀式というか、万歳くらいはしてもらったかな。その時に、親父が当時の市長と懇にしてましたんで、市長や役場の仲間、三瀬谷村国民学校の校長や職員などの名前を書いてもらった日の丸の旗を、肩に懸け結び、腹には千人針を巻いて入隊しました。
入隊して半月ぐらいは、久居で初年兵教育を受けました。そこで、内務班の洗礼を受けたわけです。入隊した日の夕食に赤飯が出てきたんですよ、やっぱり軍隊だなと思いました。あの頃は、軍隊も表向き新兵さまさまでした。でもね、良く見たらそれがバサバサのコウリャン飯だったんですよ。そのことはよう忘れません。その日の夜も、ベッドに入って休んでたら、夜中に古兵の「新兵起きよ!」と言う号令で起こされましてね。次に「靴を出せ」と言うんで、入隊した時に貰った編上靴を出しました。そうしたら、「靴の裏を見せよ」と言うんですよ。それで、編上靴をパッと見せる。まぁ、土が付いてますよ、そうすると編上靴を「首にかけよ」と言うんです。ということは、もう決まりきった文句ですけど、「この編上靴は天皇陛下から貰ったもんや。てめぇらは自分だけ安らかに眠っとるけども、土が付いたままで靴が泣いとる」と、そう言うてね。それで、その次に新兵同士を向き合わせるんです。要するに連帯責任ですね、1人が何かミスしたら全員の責任やっていう教育です。それで、罰で「相手を思いっきり殴れ」って言われるわけです。でも、戦友ですから思いっきり殴れんのですよ。それで、私は手を抜いたわけです。そしたら、それを見ていた古兵に名指しで呼ばれまして、今度は尾錠のついた革のスリッパでバァンと殴られましてね。その傷で、私はしばらく飯が食えなかったですよ。まぁ、とにかく理屈が通らん社会です。私どもも、志願すると幹部候補生になりますから、学歴のあった者はよく狙われました。対抗ビンタといいました。
軍隊では員数ってのがありまして、靴でも服でもなんでも、入隊した時に員数1っていうて貰うわけですよ。ところが、服などは洗濯しておいたらよく盗まれるんです。というのは、なかにはなくす者もおります。しかし、ボロでもなんでもその数だけはきっちり揃えとかなくてはならない。まさに形式主義の典型ですね。そうすると、全体数は決まってますから、なくなれば必ず足らなくなります。それを古兵に言うたら殴られて「おまえらどこかで盗ってこい!」と言われるんで、古兵に言われて新兵が盗むわけですね。
飯にしても、炊事場へ新兵が盛りつけに行くんですけど、古兵には分量をようけにして、新兵はみんな遠慮するんです。私らはしませんでしたけど、恨んだ古兵の飯には唾を吐きかけたりする者もおりました。
その後、国鉄阿漕浦駅から行き先も告げられず列車に乗せられて、着いた静岡の二俣という地で幹部候補生の戦闘訓練を受けました。そこには、三重県と岐阜県から兵が集まって、小学校の校舎を連隊の中心として訓練を受けたんです。その頃の思い出というと、清水からリヤカーで物資を運搬中に、アメリカのグラマン戦闘機が飛んで来て、小型爆弾を投下されたり、機関砲の掃射を受けたりしたことがありましたね。幸い、もの陰に隠れて助かりましたけど、機銃掃射っていうのは怖いですな、砂煙がパパパパパッと舞ってね。
訓練では、爆薬の模型を抱いてタコ壷という穴に入って、そこで身を潜めてこちらに向かってくる戦車のキャタピラに爆薬の模型を投げつけるってのもやりましたね。そんな訓練は回数が少なかったですけど、忘れられないです。
終戦になったら、打ちひしがれるという感じではなくて、むしろ解放感がありましたよ。やっとこれで帰れるなと思いましてね。解散式の時に、儀式として連隊旗を焼きました。「海行かば」を歌ってね。新兵はその場ではしなかったですけど、後でみんな鍋をたたいて「バンザイ」と叫んで喜んでましたね。そしたら、上官に「日本が負けたのに何が嬉しいんや!」と怒られましたね。もちろん反発もありました。
帰って来る時は、いろんな物を分けてもらったもんですよ。えらいやつは軍馬に荷物をつけて帰っていきました。私は、敗戦後に一度軍隊から黙って家まで帰ったことがありました。そうしたら1,2日後に軍の後輩が来ましてね。「残務処理が残っとる」と言うんで、また連れ戻されて、書類などの処理をしてました。だから、結局帰ってくるのがちょっと遅くて、その年の10月でしたね。私らは復職するのもすぐにはできなくて、レッドパージっていうか。審査を受けて12月にやっと復職して、前任校の三瀬谷国民学校に戻りました。その後、12月末に白子小学校へ転任することになりました。その頃の学校教育っていうのは戦争時とはころっと変わってましたけど、中にはまだ軍隊教育を良しとしてものすごく子供に厳しくやってる者もいました。
その後、鈴鹿市内の小・中学校を10校ほど転々として昭和61年3月、旭が丘小学校長を最後に退職しました。