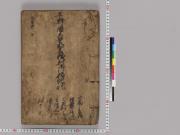人とモノのタイムラインで見る桜川市
原始
| 時代 | 年代(西暦)※ | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 旧石器時代 | 前3万6千年~前1万4千年 | 日本列島に人類が住み始める |
桜川市域で人々が生活を始める |
| 縄文時代(草創期) | 前1万4千年~前9500年 | 土器が使われはじめる |
|
| 縄文時代(早期) | 前9500年~前5000年 | 氷期が終わり、人々が定住し始める |
市内出土縄文土器深鉢金谷遺跡出土石器松田古墳群出土石棒北田遺跡出土竪穴住居 |
| 縄文時代(前期) | 前5000年~前3500年 | 気候が温暖になり、海面が上昇する(縄文海進) 土器の数や種類が増加する |
|
| 縄文時代(中期) | 前3500年~前2400年 | 気温が寒冷化し始める 土器が大型化し、装飾や文様が多様化する |
桜川市域でも集落が見られるようになる(北田遺跡、松田古墳群など) |
| 縄文時代(後期) | 前2400年~前1200年 | 寒冷化と温暖化が緩やかに繰り返される 土偶など、呪術・信仰遺物が増加 |
|
| 縄文時代(晩期) | 前1200年~前400年 | 気温低下が大きくなり、遺跡数が急減する |
集落の数が少なくなり、様相が分からなくなる |
| 弥生時代(早期) | 前400年~前300年 | 西日本で弥生文化がはじまる |
|
| 弥生時代(前期) | 前300年~前200年 | 西日本で甕棺墓、方形周溝墓などが普及 |
|
| 弥生時代(中期) | 前200年~30年 | 東日本にも農耕文化が伝播しはじめる |
市内でも集落が見られるようになる(青木北原遺跡など) |
| 弥生時代(後期) | 30年~250年 | 集落跡が多くなってくる 紡錘車(糸つくりの道具)が普及し、機織が盛んとなる |
|
| 57年 | 倭奴国王が後漢に使者を派遣し、光武帝により金印を与えられた |
||
| 239年 | 邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使者を派遣し、魏明帝から金印を与えられた |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。
古代
| 時代 | 年代(西暦)※ | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 古墳時代 前期 | 250年~380年 | 古墳が築造されはじめる |
県内最古級の狐塚古墳が築造される |
| 古墳時代 中期 | 380年~500年 | 巨大な前方後円墳が多くつくられる このころ各地に国が設置されたか |
桜川流域最大の前方後円墳、長辺寺山古墳が築造される |
| 421~478年 | 倭国の五人の王(讃・珍・済・興・武)が相次いで中国大陸の王朝に遣使 |
||
| 5世紀末ごろ | 雄略天皇(倭王武か)の子、清寧天皇ために白髪部(白壁)という名の集団を設置する(白壁郡の起源) |
||
| 古墳時代 後期 | 500年~7世紀 | 各地に小規模な古墳が密集してつくられるようになる(群集墳) |
市内でも数多くの古墳が築造される(花園古墳群3号墳、上谷貝八幡山古墳、山ノ入古墳群、松田古墳群など) |
| 5世紀中頃 | このころ朝鮮半島を経由して仏教が伝わる(仏教公伝は538年、552年など複数説あり) |
||
| 6世紀末~710年 | |||
| 飛鳥時代 | 645 | 大化の改新 これ以後、全国を国・評・里に分ける。のちに評は郡、里は郷に名称を変更する |
桜川市域は新治郡(評)となる。その後、南部が分立して白壁郡が成立する |
| 奈良時代 | 710 | 平城京遷都 |
|
| 785 | 全国の白壁(白髪部)を真壁(真髪部)に改称する |
白壁郡が真壁郡に改称される このころ谷貝廃寺が建立され、堀之内古窯跡群では須恵器が焼かれるようになる |
|
| 平安時代 | 794 | 平安京遷都 |
市内各地に集落が栄える(辰海道遺跡、犬田神社前遺跡、金谷遺跡など) |
| 935~940 | 平将門の乱 |
平将門、伯父・平良兼の真壁郡服織宿(真壁町羽鳥)を焼き、弓袋山(湯袋峠)で対陣する |
|
| 1164 | 後白河上皇、平清盛に命じて蓮華王院(三十三間堂)を建立する |
この頃、市北部の岩瀬地区は新治郡から分かれて中郡と呼ばれており、中郡が蓮華王院に寄進される |
|
| 1171~1175 | このころ常陸平氏一族の平長幹が真壁郡に入部し、真壁を名乗るという(真壁氏の誕生) |
||
| 1189 | 源頼朝、奥州藤原氏を攻める(奥州合戦) |
真壁長幹、千葉常胤・八田知家に属し奥州合戦に従軍する |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。
中世
| 時代 | 年代(西暦)※ | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 鎌倉時代 | 1192 | 源頼朝、征夷大将軍に任ぜられる |
|
| 1263 | 法身性西(真壁平四郎)、松島円福寺を中興する(後の松島瑞巌寺)。のち真壁に帰還し、照明寺(後の伝正寺)を開基すると伝わる 
法身性西 |
||
| 1333 | 鎌倉幕府滅亡 |
真壁長岡古宇田文書 |
|
| 室町時代 | 1338 | 足利尊氏、征夷大将軍に任ぜられる |
|
| 1336 | 足利尊氏が光明天皇を擁立したのに対抗して後醍醐天皇が京都から吉野へ移る(南北朝時代) |
||
| 1392 | 南北両朝が合一する |
||
| 1423 | 真壁氏、鎌倉公方足利持氏方に攻められ没落する |
||
| 1456 | 真壁氏庶子家の真壁朝幹、所領の一部を回復する |
||
| 1465 | 多賀谷朝経、富谷山小山寺三重塔を建立する |
||
| 1467~1477 | 応仁の乱 |
真壁朝幹、置文(遺言状のようなもの)により城の重要性を子孫に説く。 このころ真壁城が築城され始める 
真壁文書 |
|
| 1569 | 真壁氏、佐竹氏方の太田氏らと連携して手這坂合戦で小田氏を破る |
||
| 安土桃山時代 | 1573 | 織田信長、室町将軍足利義昭を京都から放逐する |
|
| 1590 | 豊臣秀吉が天下を統一する |
||
| 1592~98 | 文禄・慶長の役 |
真壁氏幹、肥前名護屋城(現佐賀県唐津市・玄海町)へ出陣する |
|
| 1600 | 関ケ原の合戦 |
||
| 1602 | 佐竹氏、秋田へ移封となる |
真壁氏、佐竹氏に従い秋田へ移る |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。
近世
| 時代 | 年代(西暦)※ | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 江戸時代 | 1603 | 徳川家康、征夷大将軍に任ぜられる |
|
| 1606 | 浅野長政、真壁藩主となる |
||
| 1614~1615 | 大坂の陣 |
||
| 1622 | 浅野長重、笠間へ移る。真壁藩は廃藩、以後真壁を含む市域の多くは笠間藩領となる |
||
| 1645 | 浅野長直、播州赤穂に移封される |
||
| 1703 | 赤穂浪士、吉良邸討入 |
真壁藩時代の家臣の子孫である勝田新左衛門、潮田又之丞、赤穂浪士四十七士の一員として吉良邸討ち入りに参加する |
|
| 1833 | 天保の飢饉 |
館野勘右衛門たちの嘆願により、二宮尊徳が青木村復興の仕法を実施、青木堰を普請する |
|
| 1867 | 大政奉還 |
||
| 1868 | 鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争開戦) |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。
近代
| 時代 | 年代(西暦) | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 明治(1868~1912) | 1871 | 廃藩置県 |
廃藩置県により、桜川市域は笠間県、結城県、若森県などに分割される |
| 1875 | 現在の茨城県が誕生する |
||
| 1884 | 加波山事件(自由民権運動) |
||
| 1889 | 水戸線開通 |
岩瀬駅設置。以後、市域で石材業が興隆する 
町の加工場(『石とくらし』より) |
|
| 1894 | 日清戦争 |
||
| 1898 | 常磐線開通 |
||
| 1904 | 日露戦争 |
||
| 1906 | 小山寺三重塔(小山寺蔵)、重要文化財に指定される |
||
| 1911 | 木造観世音菩薩立像(楽法寺蔵)、重要文化財に指定される |
||
| 大正(1912~1926) | 1914 | 第一次世界大戦 |
|
| 1918 | 筑波鉄道全線開通(岩瀬-土浦) |
||
| 1923 | 関東大震災 |
||
| 1924 | 桜川(サクラ)、国名勝に指定される 
名勝桜川(サクラ)参道付近 |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。
現代
| 時代 | 年代(西暦) | 全国のできごと | 桜川市のできごと |
|---|---|---|---|
| 昭和(1926~1989) | 1939 | 第二次世界大戦 |
|
| 1945 | 第二次世界大戦終戦 |
||
| 1957 | 網代笈(月山寺蔵)、重要文化財に指定される |
||
| 1964 | 東京オリンピック開催 |
||
| 1974 | 桜川のサクラ。国天然記念物に指定される |
||
| 1985 | 筑波・科学万博開催 |
||
| 1986 | 五所駒滝神社の祭事(真壁祇園祭)、国の記録作成等の措置を講ずべき無形・民俗文化財に選択される 
真壁祇園祭 |
||
| 1987 | 筑波鉄道廃線 |
||
| 平成(1989~2024) | 1994 | 真壁城跡、国史跡に指定される |
|
| 1999 | 潮田家住宅見世蔵ほか4件、市域初の登録有形文化財(建造物)となる 
潮田家 |
||
| 2000 | 北関東のササガミ習俗、国の記録作成等の措置を講ずべき無形・民俗文化財に選択される |
||
| 2005 | 旧岩瀬町、大和村、真壁町が合併、新制・桜川市が誕生する |
||
| 2006 | 市域の登録有形文化財(建造物)が全国第3位の104件となる |
||
| 2009 | 桜川市伝統的建造物群保存地区の都市計画を決定する |
||
| 2010 | 真壁の町並みが重要伝統的建造物群保存地区に選定される |
||
| 2011 | 東日本大震災 |
東日本大震災により、市域も大きな被害を受ける |
|
真壁伝承館開館 
真壁伝承館 |
※各時代の時代区分については諸説あり、一例を記載しています。



 >
>