
ヒメウ

ウミウ
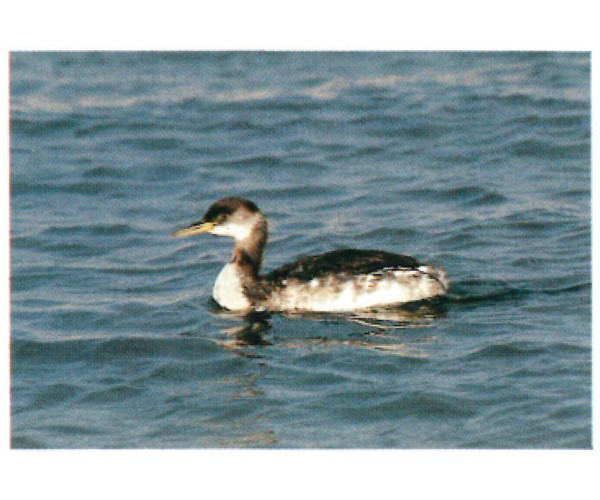
アカエリカイツブリ

コクガン

アオサギ

ダイサギ
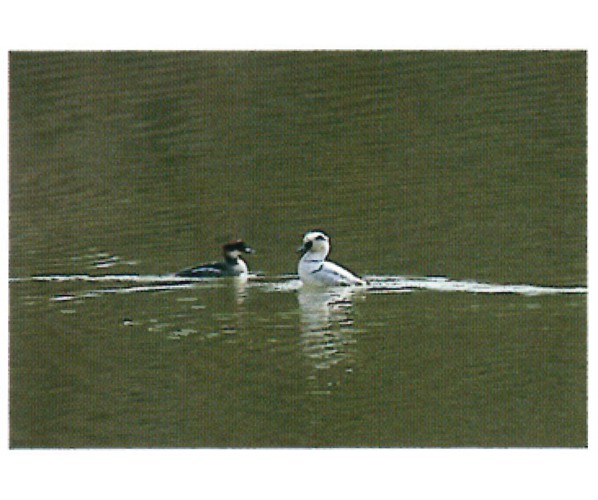
ミコアイサ

クロガモ

カルガモ

クマタカ

オジロワシ

ウミアイサ

コウライキジ

ハヤブサ

シロハヤブサ

タシギ

キアシシギ

トウネン

セグロカモメ

オオジシギ

ユリカモメ

ケイマフリ

ウミネコ

オオセグロカモメ

クマゲラ
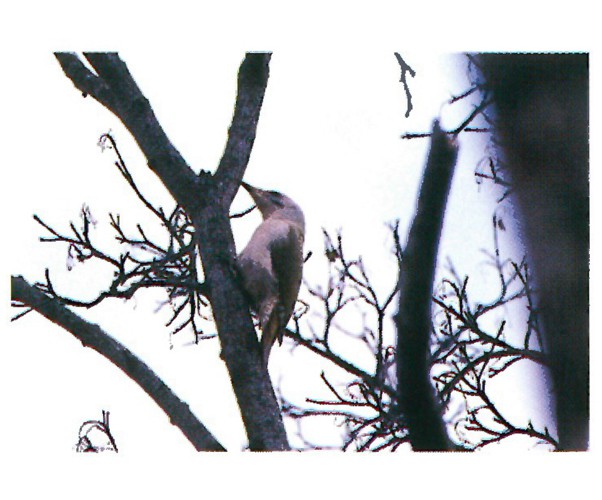
ヤマゲラ

キジバト

アオジ

オオルリ
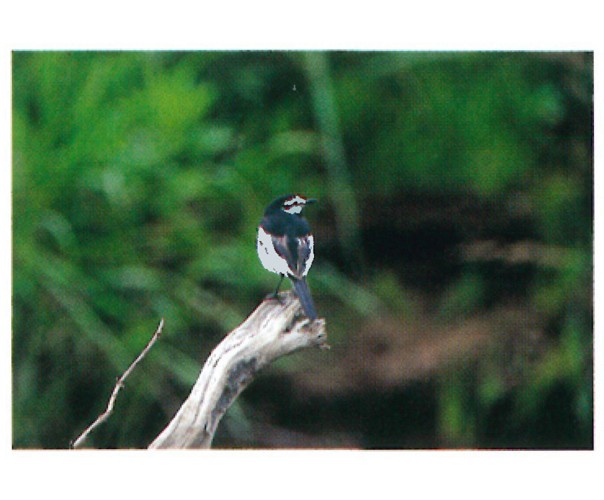
ハクセキレイ
世界地図を開くと、太平洋を挟んで東に南北アメリカ大陸、西にユーラシアからヨーロッパ、アフリカまでが見渡せる。そのユーラシア大陸に沿って中部太平洋の少し北、北太平洋に架けて赤く日本列島が記されている。北海道、本州、四国、九州の大きな島、そしてその列島の北にはさらに北方四島が記されている。一方南に目を移すと、九州から延びて東シナ海へと南西諸島が続いている。これが日本の国土なのである。
この国土は、鳥類の世界分布からいうと、日本は旧北区に属し、南は東洋区と接している。そして、なお南にはオーストラリア区、ニユージーランド区と繋がっている。このことが日本産鳥類が渡り鳥を含め550種以上という種数を数える所以である。
また、日本列島を縦断する脊稜山脈は2000メートルを越す山々を擁し中には3000メートルを越す山もある。このため河川は太平洋、日本海に近く、急流をなし一気に流れ下っているが、中流域から下流域、海岸近くでは良く扇状地や三角洲を発達させ平野を形成し沃野を呈している。扇状地、三角洲には湖沼を従えた湿地や湿原もある。このことは一方で日本の自然が野生動植物の生育にも貢献している。なお、脊稜山脈には火山も多く、特に有史前、後の火山活動はカルデラ湖や堰止湖を造成した。これらの自然現象は優れた自然景観だけでなく生物の多様性を保全し続けることとなっている。
日本は、温帯降雨林帯に属し、人手によって開かれた土地であっても放置すると、植生は回復し森林が復活する。森林は国土の7割りを占めている。
北海道は、氷河期、間宮海峡が結氷しサハリンが大陸と陸続きとなり、そのうえ宗谷海峡が流氷で埋め尽くされたため大陸の大型動物をはじめ鳥獣の往来があったものと推測される。しかし、津軽海峡では、水深が深く結氷も動物の移動を容易にすることはなかったと見られる。このため、北海道と本州の氷河期を含め野生動物の生息に顕著な違いを残すこととなった。このことについて、トーマス・W・ブラキストンは、北海道と本州で採集した鳥獣を比較し、北海道の野鳥が大きく大陸的であることに気付き、津軽海峡は動物分布境界線であることを明らかにしこれを発表した。すなわちこれがブラキストンラインである。
恵山町は、津軽海峡の東口に存し、このブラキストンラインの直ぐ北に接する位置にある。
北海道の自然は、北海道の屋根といわれる大雪山があり、南北に繋がる山脈と、石狩川、十勝川、天塩川の大河川のほか、多くの中小河川がその河川が作った湿原や原野を抱えて平野が発達している。
鳥たちは、氷河期にもユーラシア大陸沿いに南北に移動していたことは想像に難くなく、その際北海道の北、北極圏からサハリンを経て、北海道、本州へと移動していったグループと、同じく北極圏の太平洋側、アリューシャン列島から、カムチャツカ半島、千島列島を経て北海道を通過していったグループの2グループがあったことは否めない。その氷河期のDNAをもつ鳥たちは、春から初夏にかけて繁殖のため南のニュージーランド区、オーストラリア区、東洋区を経て日本に渡来し、或いは旧北区、北極圏へと通過して行った。
繁殖を終えたこれらの鳥たちは、越冬のため再び同じコースを逆に辿って旧北区、北極圏を含む繁殖地から、越冬地に向けて大旅行をするわけである。この行動を渡りといい、この鳥たちを渡り鳥と呼んでいる。