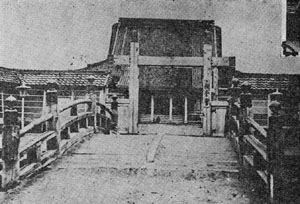
明治初年ころの願乗寺
乗経は南部下北郡川内の願乗寺に生れ、はじめ法恵と言い、のち乗経と改めた。天保12(1841)年17歳で蝦夷地に渡り、西本願寺の寺院が1か寺もないのを憂えて、本山に開教の策を進言、ついに小樽と箱館に寺院の建立を見るに至った。本山は初め但馬国専福寺の僧入真房大虫を派遣して、奉行所から貸与された濁川の土地55万坪の開拓を進めていたが、安政6年大虫が死去したので、乗経をその後任にあて、但馬・加賀・越前などから信者370余人を入植させた。ここにも願乗寺休泊所を設け、宣法庵と称したが、明治11年江差に移り江差別院となった。乗経の業績の最も大きなものは、箱館市中を縦断する堀川の掘割で、詳細は本章第9節に記したので省略するが、この功により願乗寺は幕府から墓地のほかに、1万2,118坪の土地を与えられた。また乗経はこの掘割を京の堀川とからみ合せて、自らの姓を「堀川」とした。