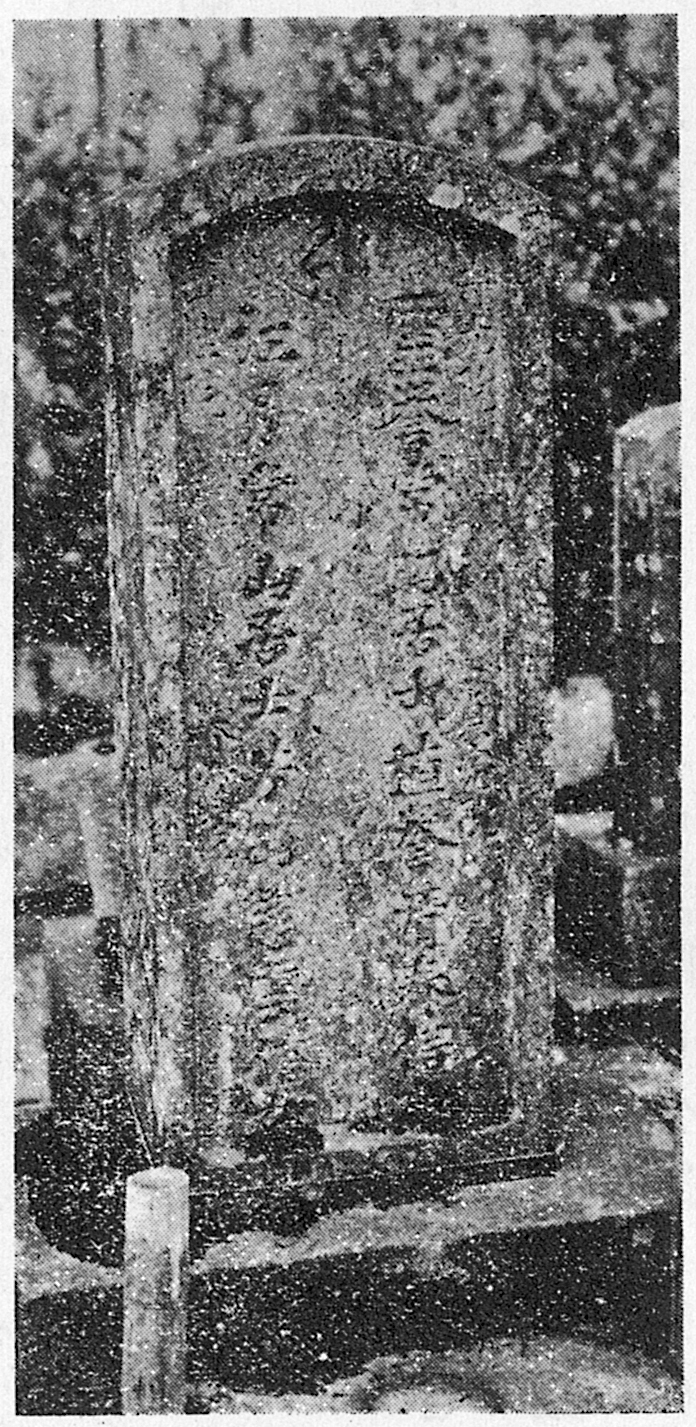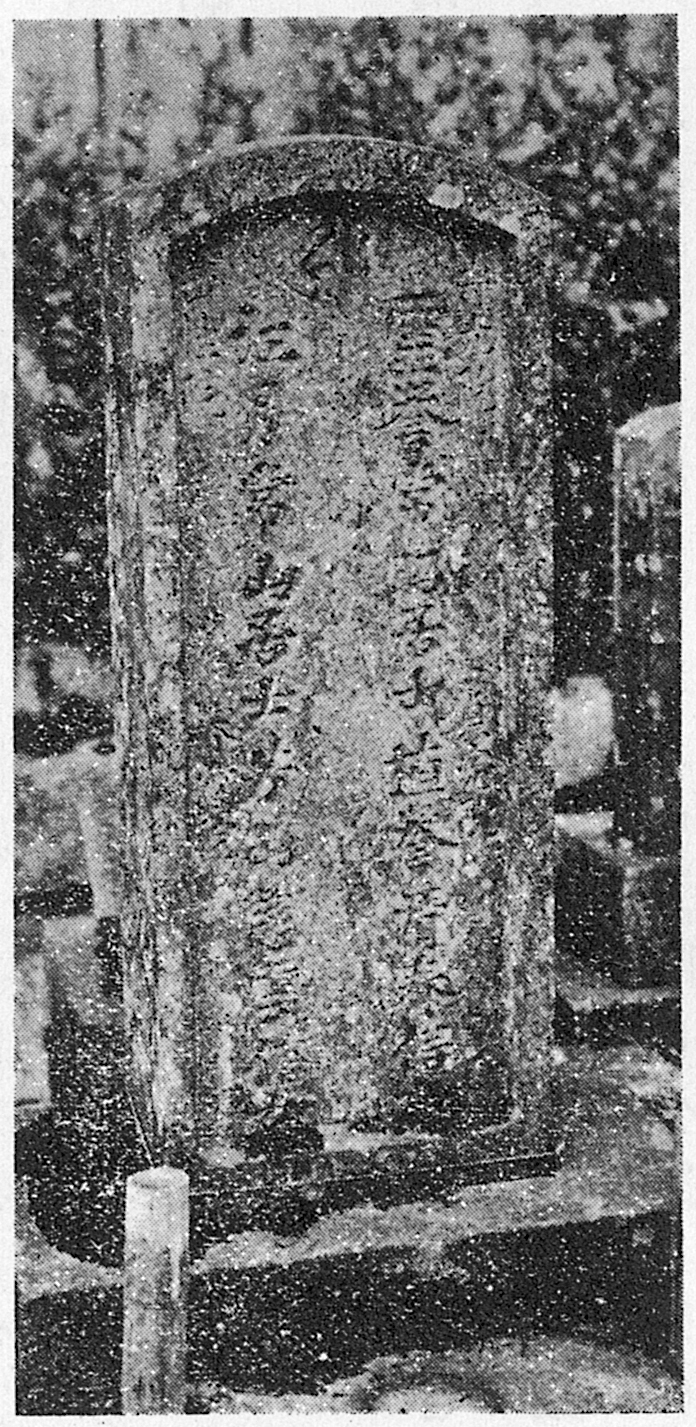【光則の男】
土佐光起は光則の男、童名藤滿丸、元和三年十月出生した。父祖の業を繼いで畫所預となり、承應三年三月從五位下左近衞將監に任ぜられた。(好古類纂)光起年二十二、父を喪つたが此時適々堺に在り、祖父光吉の門人に畫法を習ひ、又先代の名蹟を追慕し、兼て和漢諸名家の筆蹟を硏究し蘊奧を極めた。畫く所は殿堂、樓閣、山水、人物、花卉、果實、禽獸、蟲魚に至るまで筆致鮮麗溫雅、悉く妙趣に入つた。(抹桑畫人傳、鑒定便覽)【鶉を畫くに長ず】殊に李安忠の圖に倣つて鶉を畫くに長じ、嘗て猫兒の躍りかかつた事があつたと云はれ、子孫亦之を巧にした。(輪翁畫談所引橘窻自語)【土佐派中興】光起は光長、光信と倶に土佐三筆の名があり、是より先き土佐派の畫格漸く衰へたところへ光起の出生を見たので、世に土佐派の中興と稱してゐる。(畫乘要略卷一)當時狩野家に探幽あり、
土佐家に光起あり、畫壇の二大家と稱せられた。延寶九(天和元)年五月薙髮して法橋に敍せられ常昭と號した。【常昭の號法眼に敍せらる】貞享二年四月法眼に敍せられ(好古類纂)元祿四年九月二十五日享年七十五を以て歿した。(養德錦顯文鈔)【墓所】京都百萬遍知恩寺に葬つた。(平安名家墓所一覽)【
寶樹寺の靈位】堺市中之町東三丁
寶樹寺の靈位には、壽光院靈譽常昭居士靈位、元祿四年辛未九月二十五日光起と記されて居る。【堺現存の二大作品】堺市現在の光起遣品中著名なものが二つある。一は
開口神社所藏、元祿三年十月十五日に成つた
大寺再興緣起で奧書に土佐左近衞將監光起入道、行年七十四法眼常昭筆と署せられ、先に國寶に編入せられてゐる。一は
寶樹寺須彌壇背後の釋迦、文殊、普賢の三尊佛の繪で、これ亦晚年元祿二年四月八日釋尊降誕會に揮毫するところ、土佐將監入道常昭の落款がある。【著名の作品】堺以外著名の作品には、日光三十六歌仙額、新圖百鬼夜行、酒顚童子繪卷物、黃帝三幅、田村麿延鎭、行叡居士、鶉の圖、一本松、一本櫻等がある。【子孫】光起の後
光成嗣ぎ、以下光祐、光芳、光淳、光貞、光孚相嗣いで、それ〴〵歷世畫所預となつた。(圖畫考)
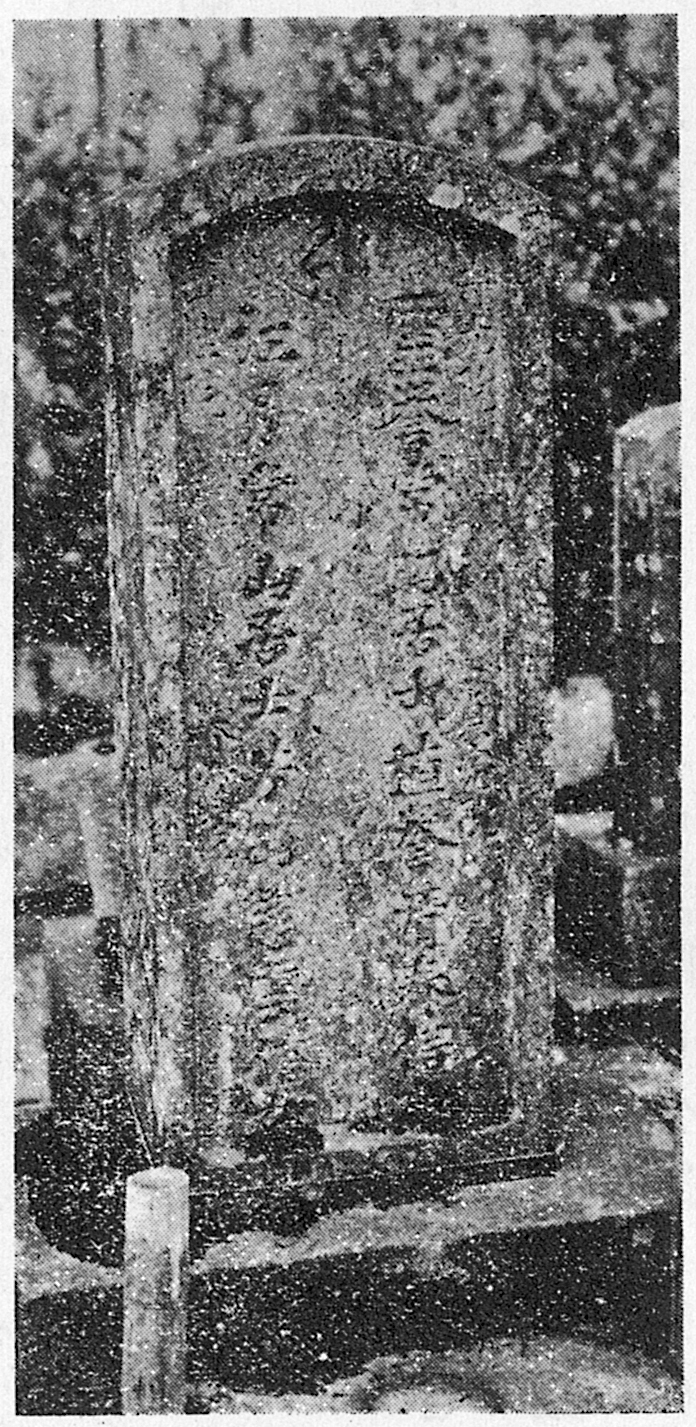
第七十圖版 土佐光起墓表