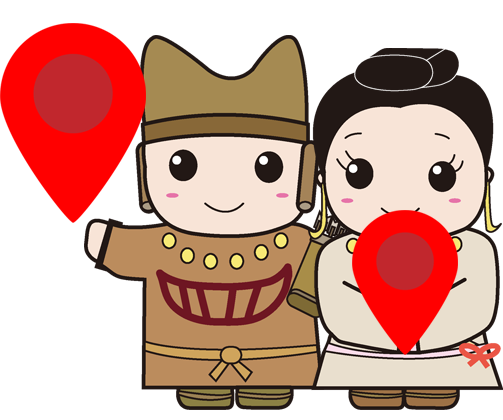
戸田市史ある記マップ
新曽コース
- スタート
- 中央図書館 郷土博物館
- ゴール
- 観音寺
- 距離
- 約4.8km
中央図書館・郷土博物館を起点に市内中央部、新曽地区を巡るコース。博物館ではかつて荒川下流域の伝統漁撈に使用された漁撈用具や貴重な文化財を間近で見ることができる。市内では新曽氷川神社だけに見られる市指定天然記念物の「夫婦柿」や、多くの石仏がまつられている新曽下町石仏群などの文化財を巡る。
- 1.中央図書館 郷土博物館
-
- 1.5km
- 2.妙顕寺
-
- 0.4km
- 3.新曽氷川神社
-
- 0.1km
- 4.金剛院
-
- 0.9km
- 5.新曽下町石仏群(新曽下町会館)
-
- 0.6km
- 6.浅間社
-
- 1.3km
- 7.観音寺
1中央図書館 郷土博物館
市内図書館の中央館である。読書活動や生涯学習を支援している。3階に郷土博物館、2階にアーカイブズ・センターがあり、郷土の歴史を知ることが出来る。
2妙顕寺

長誓山安立院と号す。創建は鎌倉時代とされ、日蓮上人の高弟日向上人を招請して開山したと伝えられる。埼玉県指定文化財の「日蓮上人墨跡」や日向上人の筆録「日向記」、市指定文化財の「妙顕寺絵馬群」や「慶長の板碑」がある。(*「慶長の板碑」は、郷土博物館に常設展示中)
パスファインダー

調べ方案内・戸田
子供向けしらべかたガイド
3新曽氷川神社
4金剛院
新義真言宗智山派に属し、観音寺の末寺。新龍山大聖寺と号している。本尊は不動明王。武州足立百不動尊42番となっている。



