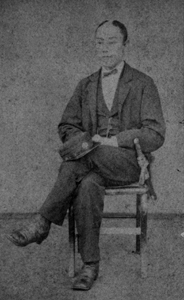
志賀浦太郎
箱館には、安政5年9月末以来ロシア領事ゴシケヴィッチとその一行が居留していた。当初の来箱メンバーには通訳の存在はなかったようで、恐らくかなりヨーロッパの言語に通じていたといわれる領事自身が、通訳たちと話をしたものと思われる。ただし、ゴシケヴィッチはオランダ語には通じていなかったらしく、同6年に江戸へ赴いた際、提出した書類は米国公使館の通訳官ヒュースケンに依頼して、オランダ語にしてもらっている(『幕外』25-73)。したがって箱館の通訳とは英語で交渉をしていたようだが、しかしロシア軍艦の乗員たちが続々と上陸してくるようになると、やはりロシア語通訳の養成は急務であった。そこに登場するのが、志賀浦太郎である。志賀は長崎の人で、安政5年以来、長崎に上陸するロシア人士官たちからロシア語を学んでいた。そして、文久元年に対馬がロシアの軍艦に占拠されるという事件の際に、ゴシケヴィッチと出会ったとされている(沢田和彦「志賀親朋略伝」『共同研究日本とロシア』)。ともあれ、志賀は文久元年春に、ロシア領事館付きの通訳として雇われて箱館にやって来たのである。箱館奉行は、翌年志賀と領事の契約満了を契機に、4月から志賀を雇ってロシア語通訳と教授を依頼し、志賀も承知したため、とりあえず1か年の約束で、通弁御用を命じたのである(「御手当元済」道文蔵)。千葉弓雄、藤本辰次郎、杉山次郎太郎、合田民蔵、若山弁次郎、山梨鶴蔵、といったところが志賀について措古をしたと思われる(「訳官黜陟録)。いずれも足軽や、役人の子弟、厄介という身分のものたちである。なお山梨鶴蔵は、前述のロシアヘの留学生派遣の際、予定の志賀浦太郎がはずされたため、代わりとしてロシア領事に推薦されたが、叶わなかった。
またニコライが箱館に来たのは1861(文久元)年の6月2日(『日本正教伝道誌』)であるが、このニコライにも志願してロシア語を習った人々がいる。学校という表現が用いられ、文久2年の「各国書翰留 魯亜」(道文蔵)には、生徒の名前も18人ほどがあげられており、その中には千葉弓雄、若山弁次郎を始め、土屋泰次郎、富田友吉、飯田善太郎、木村重次郎という名前があった。また、長崎から派遣されていたオランダ通詞、西六馬も顔を出していたのは興味深い。こうして徐々に力を付けた生徒のうちから、「魯語通弁」として採用されるものも出てきた。まず文久3年に千葉弓雄が任命され、続いて慶応元年に若山弁次郎、2年に鈴木甚太郎(合田民蔵のこと)が任命されている(前出「御手当元済」)。