そして「決死隊の漁夫を募ったところ、生命知らずの荒武者が五十余人も応募して来た」(『幸一郎伝』)という。この漁夫の氏素性について『幸一郎伝』では何も書いていないが、外交史料館が所蔵する資料(「樺太島ニ於ケル漁業渡航者取締一件」)から一端を明らかにすることができた。以下にまずその顛末を記してみる。
小熊の所有船がサハリン島へ密航したらしいといううわさが報告され、続いて亀田警察分署長が次のような報告をしている(かっこ内は著者)。
…渡島国亀田郡銭亀沢村字古川尻松田市蔵ナル者漁夫数十名ヲ引率シ本年(明治三十七)四月十二日松前郡吉岡ニ至ルト称シ汽船東洋丸ニ乗込ミ函館出帆後、同地ニ上陸セスシテ他船ニ乗換、露領薩哈嗹(サハリン)島へ漁業ノ目的ニテ密航…
密漁船が出航したのは四月十二日で、それに乗り組んだ「生命知らずの荒武者」には、銭亀沢村の人びとがいたのである。さらに分署長の報告の続きをみてみよう。
…該一件中ノ一人ナル松田亀太郎ナル者ヨリ、同村同字二番地漁業木村 元次郎ナル者ニ宛テタル書簡ニ拠レハ、「吾々共六十三名ハ露国ペルミ市ニ不残健康無事ニ居ル」トノ旨ヲ報知シ来リ…以上ノ通信ニ拠レハ該一行ノ密航ハ事実ニシテ目下俘慮トナリ居ルモノナラント…
これによれば、銭亀沢村の木村元次郎あてに、ロシアから手紙が届いていた。差出人は、小熊の船で出漁した同村の松田亀太郎であった。この手紙(三十七年の八月に発送され、十月に到着)はロシア語で書かれていたというが、船の拿捕、そして捕虜になったという内容に村の人びとは驚いただろう。それでも、無事でいることを知って安堵したに違いない。
後に帰国した漁夫の口述によると、船は暴風雨のため、サハリン島西海岸の「ウソロフ」に漂着したのであった。数人が飲料水を求めて上陸したところをロシア兵に抑留され、船は逃げようとしたが、逃げ切れず拿捕されたとのことであった。
そして六月九日、船は曳航されてアムール川河口のニコラエフスクに到着、ここで一行は船から降り、あとは手荷物を持ってハバロフスク、トムスクとシベリアを進み、八月初頭にペルミ市(ウラル地方の西部にある)に着いた。手紙はここで書かれたのである。
さて、手紙がついた時点で、住所と氏名が判明したのは次のとおりであった。
①亀田郡銭亀沢村字古川尻
松田市蔵(慶応元年八月生)
②同
松田作蔵(慶応三年八月生)
③同
松田亀太郎(明治八年三月生)
④同郡同村亀尾村字野広場
栗谷川仁太郎(万延元年八月生)
⑤同
菊地晋八(明治十八年十一月生)
⑥同郡同村大字石崎
小林嘉一郎(当三十壱年)
⑦同
森山鶴蔵(明治十二年七月生)
⑧同
菊地寅吉(当二十六年)
先の分署長の報告では、松田市蔵が漁夫数十名を引率したとあり、この人物がリーダー格のようにも思われる。引率された漁夫がみんな銭亀沢村の人だったのかどうかはわからない。報告書に氏名や住所の記載があるのは、ここにあげた八名だけであるが、漁夫は全部で五四名いたと記されている。
古川町に住んでいる松田作蔵の孫鶴吉は、幼いころにこの話を聞いたという。そして最近まで祖父がもたらした、ヨーロッパの風景が印刷された絵はがきをもっていたそうだ。しかし知っているのはそれだけで、ほかは全くわからないということであった。詳細は後述するが、松田家は敗戦で引き揚げるまで、樺太の真岡の南にある「手井」[ポリヤコーヴォ]漁場を経営しており、樺太とは代々深く結び付いてきたのである。
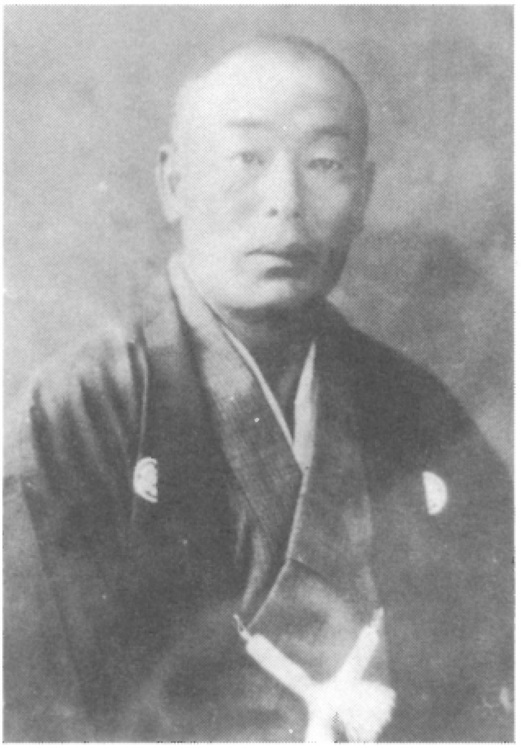
松田作蔵(松田鶴吉提供)
ところで、作蔵らの密出航には、いったいどういう背景があったのだろうか。おそらく彼らは、「愛国心から」やみくもに応募したのではないだろう。何も知らない土地へ出漁するとは考えられず、すでに何度もサハリンに出稼ぎにいって、現地の事情に詳しかったに違いない。そして毎年あてにしていた出漁が戦争で中止になり、困惑しているところにこの話がきた、と考えるのが妥当ではないだろうか。
それにしても戦時中の密出航であるから、相当の覚悟で行ったには違いない。松田という姓は、先の工藤福松の縁者と同一であるが、これは単なる偶然であろうか。いずれにしろ、この一件は銭亀沢からサハリンへの出稼ぎを裏付ける有力なてがかりである。
さて、捕虜となった一行が帰国するまでの足跡も興味深いので、ここに紹介しておこう。
八月初頭にペルミ市に着いたが、これは函館港を出てから四か月後であった。それから一行はほかの避難日本人らとともに、アメリカの公使代理に引き渡され、ロシアを出てドイツに到着、十月二十五日、ブレーメンから避難民送還船の「ウィルハット号」に乗り込んだ。船は十二月七日に長崎に寄港し、十二日に横浜港に着いた。
横浜には函館選出の衆議院議員内山吉太が避難民を待ち受けていた(明治三十七年十二月十四日付「函新」)。内山自身が有力な樺太漁業家であり、小熊幸一郎とは姻戚関係にあった。新聞には、避難民のために一〇〇円を寄贈したという以上のことは書かれていないが、おそらく内山が出迎えたのは、小熊の船の乗組員たちの安否を気遣ってのことだと思われる。
『幸一郎伝』には「…一行は、捕虜としての優遇を受け、翌年戦争が終ってから、ドイツを廻って思いがけぬ欧州見物をし、魚の代りに絵葉書や欧州土産を持ち、ドンザの代りに、背広服を着て、きまり悪そうに帰還したのであった」と書かれている。小熊はこれで財産の半分を失ったというが、凱旋部隊でも迎えるように厚くねぎらったという。