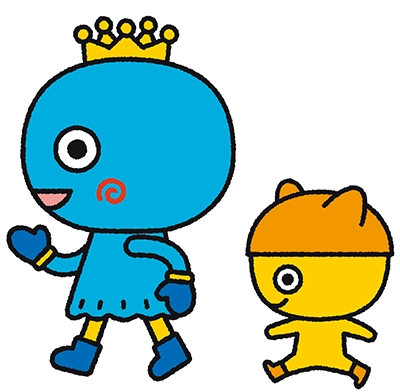西宮でなぜ酒づくりが発展していったのだろう?
<まとめ>西宮で酒づくりが発展したポイント

これまでの話を整理してみましょう。

最初に、西宮町と今津村のちがいが酒づくりに影響を及ぼしていたことを確認したね。

都市部の西宮町と、農村部の今津村では、酒づくりを始めるタイミングがずれていて、最初は都市部だけだったのが、農村部でもできるようになったんだよね。

そうですね。西宮町や今津村の地域がすべて同じように発展してきたわけではないことがわかりましたね。
その次に確認したのが、酒づくりに必要な環境についてでしたね。4つのポイントを覚えていますか?
その次に確認したのが、酒づくりに必要な環境についてでしたね。4つのポイントを覚えていますか?

1つめは、「宮水」だよね。西宮の限られた場所でとられる大事な水で、酒づくりにぴったりな水だったね。

2つめは、「水車での精米」だったね。水車の力を使って、酒づくりには欠かせない酒米が大量生産できるようになったのはおどろいたよ。

3つめは、「六甲おろし」だね。冬の寒い時期に六甲山から吹く「六甲おろし」は酒蔵にとっては必要だったんだよね。酒づくりは寒かったんだろうなあ。

4つめは、「丹波杜氏(とうじ)」だよね。酒づくりのすごい技術をもっていたから、西宮のおいしいお酒ができたんだったよね。

お二人とも大正解。よく覚えていましたね。西宮のおいしいお酒ができるのは、これらの理由のおかげでしょう。
最後に、西宮のお酒はどこに運ばれたのか、のお話は覚えていますか?
最後に、西宮のお酒はどこに運ばれたのか、のお話は覚えていますか?

最初は馬が江戸まで運んでたんだよね。重たかったと思うなあ。そのあと、船に代わったね。

お酒を運ぶ専用の船があったなんて、たくさん江戸に運ぶ必要があったんだよね。西宮のお酒はとってもおいしいんだろうなあ。

お二人ともよく理解できていますね。西宮の酒づくりは、ただお酒をつくる環境が整っていただけではなくて、江戸に運ばれて、たくさん飲んでくれる人がいたから、発展していったようすがよくわかったかと思います。
これで西宮の酒づくりについてはかんぺきですね。
これで西宮の酒づくりについてはかんぺきですね。