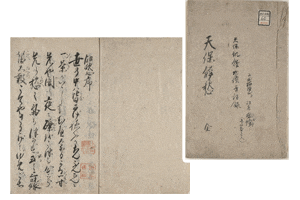
東御市文化財保護審議会 寺島隆史
江戸時代後期、天保年間に起こった天保の大飢饉についての手記です。凶作により高騰した上田や江戸ほかの穀物相場も記されています。序文によると、筆者は上田海野町の住人松原晋蜂。表紙に付記された「(東山堂主人)」が正しいとすると、松原晋蜂は上田宿の「松屋伝八郎・東山堂」として「脇本陣代」を務めていた旅篭で、かつ手広く薬種商を営んでいた商家の主人であったとみられます。大災害も年月を経ると忘れられていく中で、自身の見聞を後人の一助ともなるように書きつづったとしています。天保の飢饉は冷害によるもので、天保4年(1833年、巳年)に始まり同7年の被害が最大でした。一年だけの凶作ではなかったために惨状を呈することにもなったのですが、本書ではその経過も記しています。
まず、天保4年(巳年)は長雨で秋の実りが悪く飢饉となりました。翌5年(午年)は気候も順調で秋作も十分でしたが、同6年(未年)は夏中雨降りで風も吹き不作でした。けれども、特別の凶作というほどでもなかったとあります。しかし、この年の冬は寒気は強かったが雪は一向に降らず「からしみ」でした。そのため蒔いた麦の種が浮いてしまい、翌7年(申年)の麦のできは半作でした。そして、この7年5月頃からは冷気、降雨続きで、田植えが大変遅れてしまいました。雨はその後も降り続き晴れの日はごくわずかで、遅れて出た穂もほとんど実りがなく前代未聞の深刻な凶作・飢饉となったとしています。
4年間に3年の凶作でもあり、飢饉に備えていた者も貯えが尽き、ましてや貧しい者は飢えを免れることができませんでした。命をつなぐため、山に登って葛・蕨の根を掘り、木の実を拾い、食べられると聞けばどんなものでも刈取り、野も山も焼け野の如く取荒らしてしまったとあります。草木の毒にあたって死んだ人もあり、また、辺鄙な地では犬猫までも食いつくし、ついには命を失った人が多かったと聞いたとしています。
冷害による凶作はこの天保7年で終わったのですが、翌8年春になり暖かくなったところで、「時疫」と称する疫病が大流行しました。数年来の凶作で栄養不良になっていた人が多い中での伝染病であり、折角飢饉をしのいだにもかかわらず、これで命を落とした人が多かったと言っています。例えば上州吾妻郡大笹村(現嬬恋村)では、110軒程の所で死者167人と聞いたとあります。
現代日本では、食糧自給率が大変低いにもかかわらず、大量の食品が廃棄されています。その一方で、アフリカなどでは飢餓が原因で命を落としている大勢の子どもたちがいるという現実があります。飽食日本と対極的な江戸時代の飢饉についての信州の先人の体験記ですが、現在の食糧問題について、改めて考えさせられる史料とも言えましょう。
なお、本書は序文の冒頭に、「世の中は皆かげろうかちんぷんかん」という句を掲げ、
一茶の作としています。真偽のほどはともかく、一茶辞世の句として知られる「盥から盥
へ移るちんぷんかん」の原型なのでしょう。一茶没後間もない時期でも、既にその知名度
が高かった様子もうかがわれ、興味深いものがあります。