
様々なひとが暮らす街。
ひとりひとりの日々の暮らしからそれぞれの物語が紡がれ、街の歴史を織りなしていく…
そんな物語の軌跡を区民インタビュアーがたどります。
2 福祉窓口で続く孤独な闘い
「千川子どもの家」から「王子第二養護学校」へ
娘さんの退院から1年経った頃、幼稚園探しが始まった。3歳半になったものの、一般の幼稚園に通園は出来ない。新宿区の東京都障害者センターへ相談に行くと、「豊島区にはいいところがあるのではないですか」と言われ、礒﨑さんはハッとする。豊島区に住みながら何も知らない自分に気づいたという。学齢期前の障害児のための通所施設「千川子どもの家(※5)」を紹介されたものの、入園時に発作の起こる子どもは受け入れられないと言われる。「多分、前例がなくてわからないから預かることが怖いっていうことだったのでしょうね」と当時を振り返る。「発作が起きたら、なんとしてでも迎えに来ますから!」と熱心な交渉を続け、ようやく入園することが出来た。だが娘さんの発作は毎日のように起こり、呼び出しの日々が続く。慌てて、自転車で駆け付ける。しかし着いた時は、娘さんは回復して元気にしている。その繰り返しである。発作といっても少し意識を失うという状態で、礒﨑さん自身も発作の扱いに慣れていき、「そんなに焦らなくてももう大丈夫かな」と思えるようになったという。

昭和54(1979)年、娘さんは北区の東京都立王子第二養護学校(※6)へ入学。養護学校教育が義務教育になったばかりの頃で、いろいろな子どもが通っていたが、ここでも娘さんの発作が引っ掛かったという。常にヘッドギアをかぶっていたが、結局、発作があると脱げてしまうので、かぶらなくても同じことだった。また、頭の中に、シャントという水圧を調節するポンプを入れていて、脳の中の水を腸に排出するための管を体の中に通していた。これも、「職員がすごく怖がるんですよ。全然怖くないんですけどね」と今でこそ言えるが、前例がないため様々なハードルと向き合う日々は続いた。
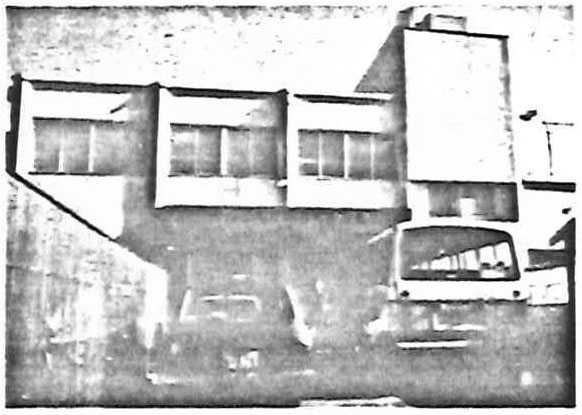
(広報としま1974年1月1日号より)

入学前、豊島区の学区には高島養護学校(※7)があり、スクールバスも高島養護学校には循還していた。王子第二養護学校へは豊島区から通っている人はいなかった。そこで、豊島区の福祉課へ「スクールバスを回して入学させてほしい」と日参したが、「王子第二養護学校は都立のため都が決めること」と言われてしまった。役所と礒﨑さんの孤独な闘いが続く。「ダメと言われても、王子からバスを回してほしいと大騒ぎしました。もう無理やりですよ」と笑った。闘いの末、礒﨑さんの学年から文京区の一部と豊島区の東側が王子第二養護学校に入学できるようになったという。
「その時はまだ、誰かと一緒にやろうとか、全然考えられなかった。自分の子どもをどうにかしなくてはという思いで、単独でも平気でした。仲間を作るとか、考えられなかったし、知らなかった」と、孤軍奮闘の日々を振り返る。

