
様々なひとが暮らす街。
ひとりひとりの日々の暮らしからそれぞれの物語が紡がれ、街の歴史を織りなしていく…
そんな物語の軌跡を区民インタビュアーがたどります。
2 子どもたちを通して、「大人の責任」を痛感
プレーパークの代表になり当初は戸惑った栗林さんだが、そこで出会った子どもたちを通して、早くも問題意識が芽生えていく。
「何をやればいいんだろうって思いながら、とにかく自分の子どもと一緒に現場に行ってたんです。そしたら、ご飯食べてないって言ってくる子どもに会うようになって。でも、地域の方に相談しても『それは親の責任なんだからしょうがないわよ』って言われる。イベントのときにも、『何々さんちのお孫さん』『近所の何々ちゃん』とか、知っている子には『いっぱい食べなさいね』って言うんだけど、知らない子が――本当にお腹を空かせてる子が何度もおかわりしていると、なんとなく『あの子、何回目よ、分けなくていいわよ』みたいな空気になっちゃう。それから、そういう子たちのことを行政に伝えても、子ども家庭支援センターにつないでくださいとかいわれる。しかし、つないでもお腹空いたって言ってくる子の様子は変わらないわけで」

行政につなぐことも大事だけれど、日常的に関わり話を受け止めるだけでも、1回でも食事をともにしたりするだけでも、成長したときに、少しだけ何かが変わるかもしれない――栗林さんがそう考えるようになったのは、子どもたちと言葉を交わすうちにあることに気づいたからだった。
「5年目くらいから『遊び場でもあるけど〈居場所〉なんだな』って思うようになりましたね。例えば、平日のプレーパークには、いつも友だちと来るんだけれども、日曜だけは1人でやってくる6年生の子がいた。他の子は土日に少年サッカーとか少年野球に行くから、その子は行くところがなくて日曜の朝から夕方までいるんです。『俺だって中学校に入ったら野球するんだ、お母さんがユニホーム買ってくれるって言ってるから。俺もやるんだ……』とか言いながら。
当時は雨が降ると現場を閉めなきゃいけなくて、帰ろうとすると、泣きそうな顔で『本当にやめちゃうの……?』って言ってくる子もいました。その子は以前、車の中で暮らしていたそうで、来ても私と遊ぶわけでもないけど、現場にいるんです。だから本当に〈居場所〉なんですね。当時は私、子どもが施設に保護されることなど全然知らなかったんです。そういう仕組みとか、我が子を虐待してしまう親がいることも、知らなかった。

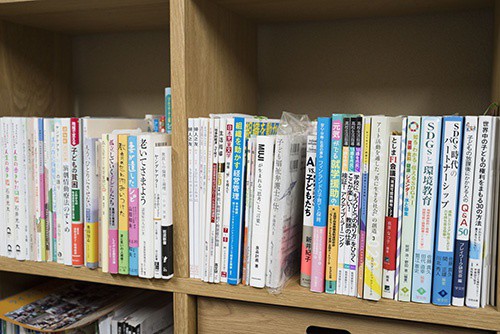
折しも、リーマンショックによる深刻な不況に見舞われ、「年越し派遣村」「ワーキングプア」などの社会問題がさかんに報じられていた時期だ。栗林さんは、身近でも見聞きするようになった事例から貧困問題に関心を持ち、講座などで学ぶようになる。男女の賃金格差やシングルマザーの貧困といったジェンダーの問題、そこから子どもたちに波及する問題、ホームレスの増加――さまざまなことを知るうちに新たな出会いもあり、その後の活動やネットワークにつながっていく。
一方、池袋本町小学校建設のためにプレーパークが閉鎖されることになり、栗林さんは地域の有志とともに、存続をめざして動き始めた。

