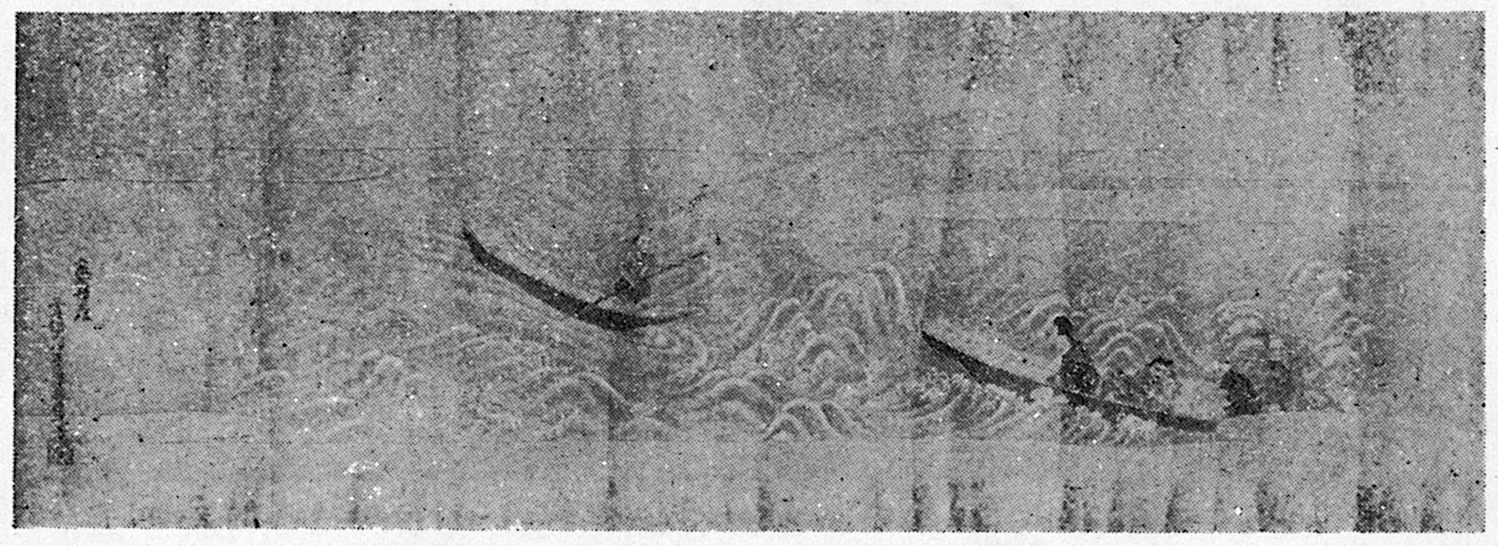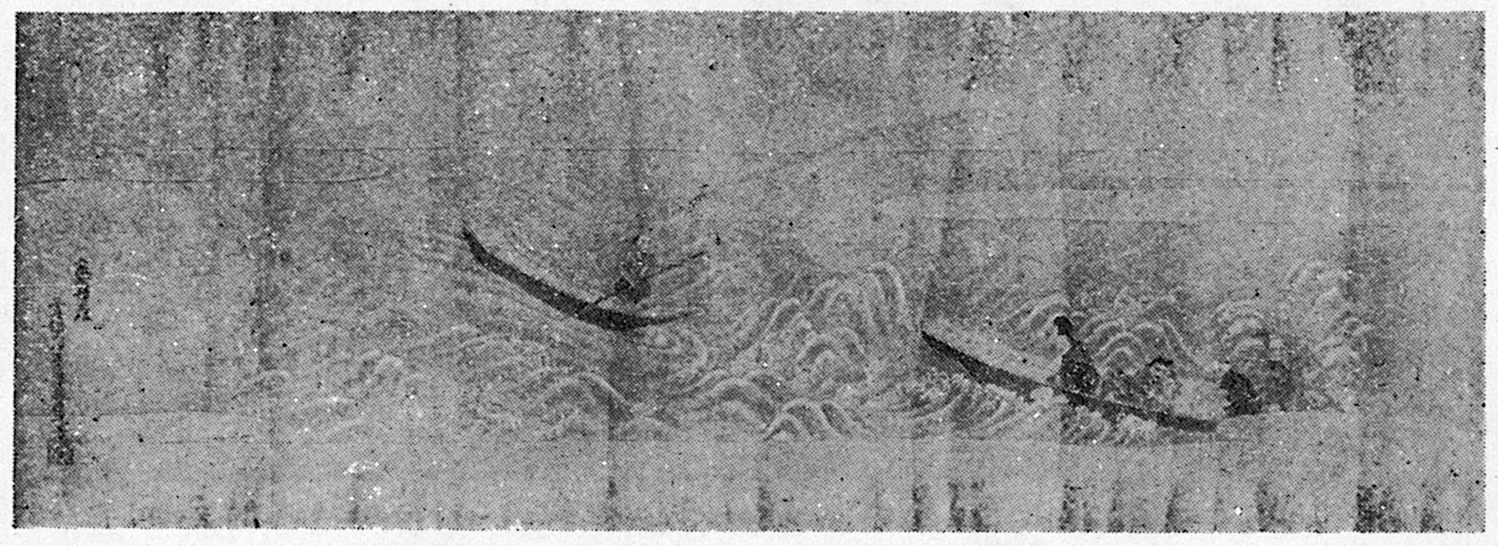鹽穴寺は
光明山と號し、一名
實相院、【位置】新在家町東四丁字寺町にあり、【沿革】眞言宗御室派仁和寺派で、寺格三等格院、
元明天皇の勅願所、僧
行基の開創と傳へ(
光明山鹽穴寺緣起、
堺鑑中)慶雲四年
行基堺浦に來り、漁夫の爲に彌勒の土像を作り、假堂に安置し、滅罪修善の道場とした。和銅元年春邑長
高畠左京之進宗與、一日漁夫と共に蘆原の海中に十一面觀世音菩薩の尊像を獲、之を彌勒堂に安置して崇敬した。【本尊】同年八月天皇
行基に勅して彼の十一面觀世音を遷して本尊とし、寺を
勅願寺とせしめ給ふた。【舊位置】其境地は鹽穴下條の地にあり、
常樂寺と號し、又寺地に因んで
鹽穴寺とも稱した。【舊僧房】僧坊には實相、安養、寶藏、北の坊、東の坊、地藏、普門、多門、文殊等の諸院があつた。然るに應仁の亂
實相院を殘して荒敗したので、本尊を
實相院に安置した。(
光明山鹽穴寺緣起)【堂宇】現境内三百六十八坪(社寺明細帳)本堂、庫裏、客室、門の外に歡喜天堂がある。斯して當寺は市内有數の名刹ではあるが、將に廢絶に歸せんとして居る。【
實相庵移轉】又
千利休の茶室
實相庵があつたが、
南宗寺に移轉せられた。【舊梵鐘】梵鐘はもと阿波勝浦莊古上鄕神光寺のもので、元德三年の鑄造である、が何時の頃にか當寺に移され、明治維新の際所在を失し、後播磨の明石に遷されたと言はれるが明かでない。(攝、河、泉金石文)
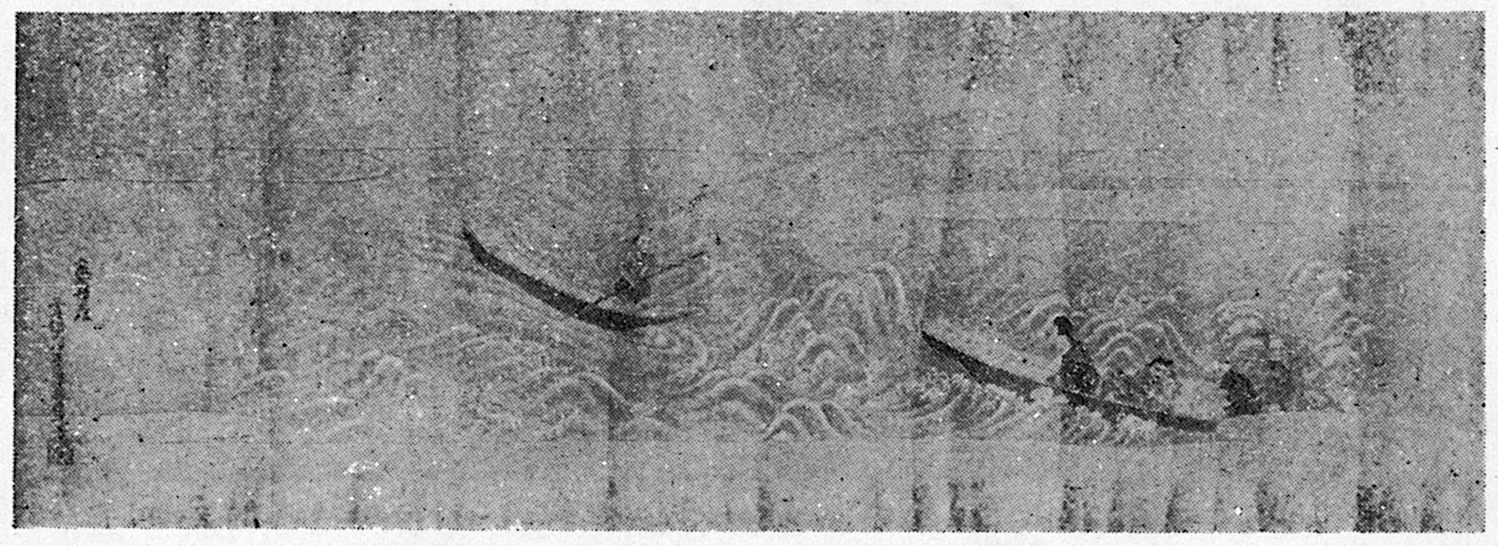
第九十圖版 鹽穴寺緣起(部分)