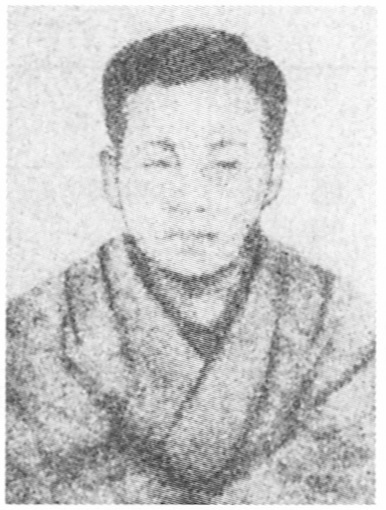
写真15 山田県令
山田県令はまず次のように述べている。
秀典赴任以来ノ県治上実施セシ事業并后来施行スヘキ目途ノ概略ヲ挙クルニ先(さきだ)チ、本県ノ一大不幸ナル所以ヲ陳セントス、明治四年十一月、新ニ青森県ヲ置カレテヨリ明治九年八月秀典ノ赴任マテ凡ソ六ヶ年ノ間、長官ノ代ルコト七回、其間各ノ意見・趣向自ラ多少ノ異ナルアリ、随テ治務上存廃改撫終始ヲ全貫スルモノ甚タ多カラス、或昨令今改トナリ人民ニ其影響ヲ及ホシ、事業ノ興衰、方向ノ異同等関係アルコト蓋シ尠ナカラス、其間接・直接於テ実ニ言フヘカラサル不幸アリ、秀典ノ任ニ就クヤ百般ノ事務未タ整ハス殆ト新置県ノ想アリ、之レ各旧官ノ其職ヲ尽サルニ非ス、席暖カナルニ至ラスシテ交代ス、焉ソ勢ヒ然ラサルコトヲ得ンヤ、其後漸々順ヲ追ヒ叙ヲ押シ以テ整理ヲ謀ルト雖トモ、日尚浅ク未タ期スル所ニ及ハサルモノ多シ、(中略)
(資料近・現代1No.一八六)
山田県令着任以前の青森県令は、在任期間が短く、十分な施策が展開できなかったというのである。山田県令は、明治九年(一八七六)の着任以後、多くの施策を手がけたとして、その功績を列挙しているが、それらのうちで、殖産興業、士族授産にかかわり、かつ、弘前を含む津軽地域に関係があるものは次のものである。
・津軽各郡内の稲虫駆除
津軽各郡では稲虫が蔓延し、その被害が大きかったので、明治十年(一八七七)から対策を講じ、その効果が現れた。
・旧弘前藩の士族授産のため、開牧資金の拝借を内務省へ申立て、許可を得た。このため、開牧社の設立が可能になった。
・県内では馬耕が行われていなかったので、その導入を図った。明治十一年(一八七八)に肥後(熊本県)から農業技術者を招いてその導入を開始し、また、同年から西洋馬耕の技術導入も行った。
・各種作物栽培の開始
従来、農事関係で未発達の側面があったので、各地から新たな耕作法や作物の品種を導入し、その普及を図った。明治十一年以来、米については九州の西南農法、作物としては麻を栃木県から導入し、教師を招いてその栽培法を伝習したほか、藍を徳島県から、また、煙草を鹿児島県から導入した。さらに楮、三又(三椏)のほか、甘薯、岡稲、生姜、芦粟(ろぞく)を導入した。このうち、芦粟は、米国産や清国産の植物で砂糖の原料となるもので、明治十年代に全国に普及した。県が特に奨励したのは芦粟であり、明治十三年に開催された綿糖共進会には県内から五斤(一斤=六〇〇グラム)以上の出品者が四人あった。このほか、養蚕、製糸業も奨励した。
・救荒備窮制度の整備
旧弘前藩時代に、民間に貯蓄制があった。この制度が廃藩置県以後機能が十分でなくなったので、明治十年十二月に整理に着手し、その拡充を目指した。
・地力の増進
地力を尽くすため、田畑で必要植物を改良増進し、原野では必要動物を育養、蓄息し、山林では必要用材を植樹養成すべきであり、その事業を興そうとしている。
・山林の養成
植樹を行い、原野中に点々と樹林を植立て、根拠をつくる。
・道路の改善
道路を改善し、運輸の便をよくする。地租改正以来、民費の負担が多く、財政的余裕がなかったが、明治十二年に至り、経済状態が変化して民に余力が生じたため、改善に着手できるようになった。
このほか、漁業振興や水利の充実についても触れている。