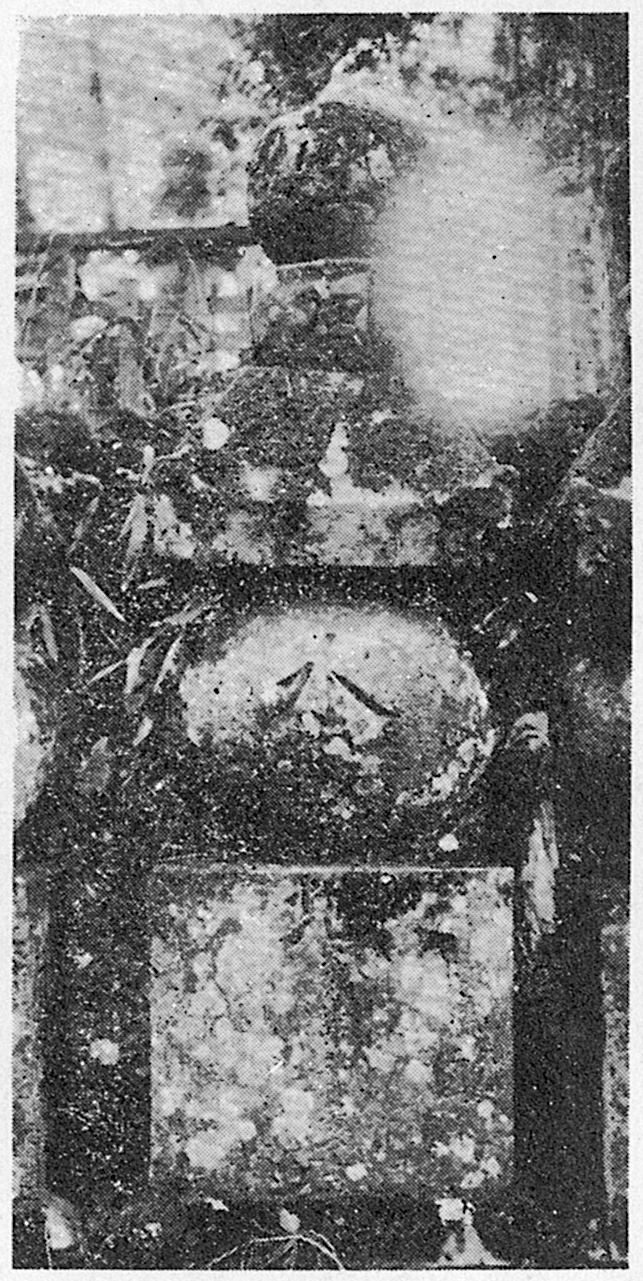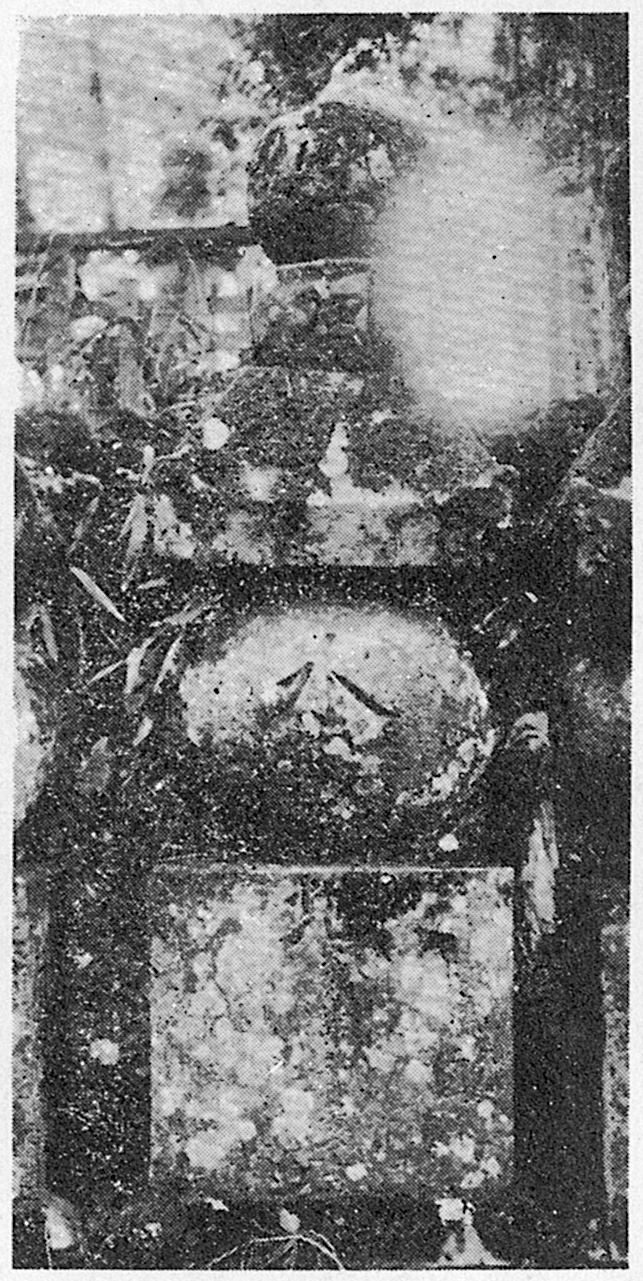【家系】
今井宗久名は兼員、始めの名は久秀、通稱彦八郞、後
彦右衞門と稱した。
昨夢庵壽林と號し、薙髮後は宗久と云つた。出羽守
宗慶の三男で、刑部左衞門秀光の弟に當つてゐる。近江佐々木氏の後裔で、祖高宮三河守信盛の弟、相模守信經は近江高島郡今井市城を領した。因つて氏を今井と改めた。宗久は大和の今井に住したが、故あつて堺に徙り、(
養壽寺今井家系圖)納屋宗次の家に寓居し(數寄者名匠集)【
紹鷗の女婿】
茶湯を
武野紹鷗に學び、遂に女婿となり、家財茶器を悉く讓られた。(
紹鷗傳來道具譯書寫)始め
茶湯を以て足利義昭に仕へ、法印に敍せられ、
大藏卿と稱した。(
今井氏七石碑銘幷系圖、寬政重修諸家譜卷第二百二十四)宗久は將軍近侍の爲め、淀川を頻繁に上下したから飯川山城守に命じて乘用の船を作らしめた。淀、伏見では之を
今井船と稱した。(今井家由緖書、數寄者名匠集)後、信長に仕へ、攝津住吉郡の内に於て二千二百石の釆地を與へられた。(
養壽寺今井家系圖、寬政重修諸家譜卷第二百二十四、今井家先祖書)天正七年信長來堺の際には宗久の茶亭に臨んだ。(茶人系傳全集、
全堺詳志卷之下)後、
豐臣秀吉に仕へ、同十三年北野の茶會には宗久所藏の茶器は第四位を占めた(
堺鑑下)【三名匠の一人】當時
千利休及び
津田宗及と共に茶家三宗匠の名があつた。(茶人系傳全集)文祿二年八月五日享年七十四歳を以て歿した。法號大府卿法印壽林宗久居士。(桃青寺過去帳、
今井宗久茶湯日記)墓碑は其菩提所たる堺
向泉寺に建てられ、又(桃青寺過去帳、今井家先祖書)
高野山には其男宗薰の建てた供養塔がある。嫡宗薰家を嗣ぎ、次男宗汐は出でゝ
谷家を嗣いだ。(
祥雲寺略記)宗久天正十年六月信長薨去に際し、十三級の石塔婆を建て、中に佛舍利を安置して、一代の武德を表顯し、翌年一周忌には、三丈三級の塔婆を建てゝ其英靈を弔した。又
茶湯の師
紹鷗の二十五囘忌、天正七年六月二十九日には鹽穴
常樂寺内に五層の塔を建てゝ冥福を祈つた。銘文は何れも
玉仲宗琇に囑して、選述せしめたものである。(
玉仲遺文)【當時の茶人】宗久と時を同じうして交遊した堺の茶人に、網干屋道珠、宗好、納屋宗春、松江隆仙、塗師屋宗和、宗叱、
道叱、宗折、宗可、宗巴、道是、松屋源三郞、宗仁等がある。(
今井宗久茶湯書)
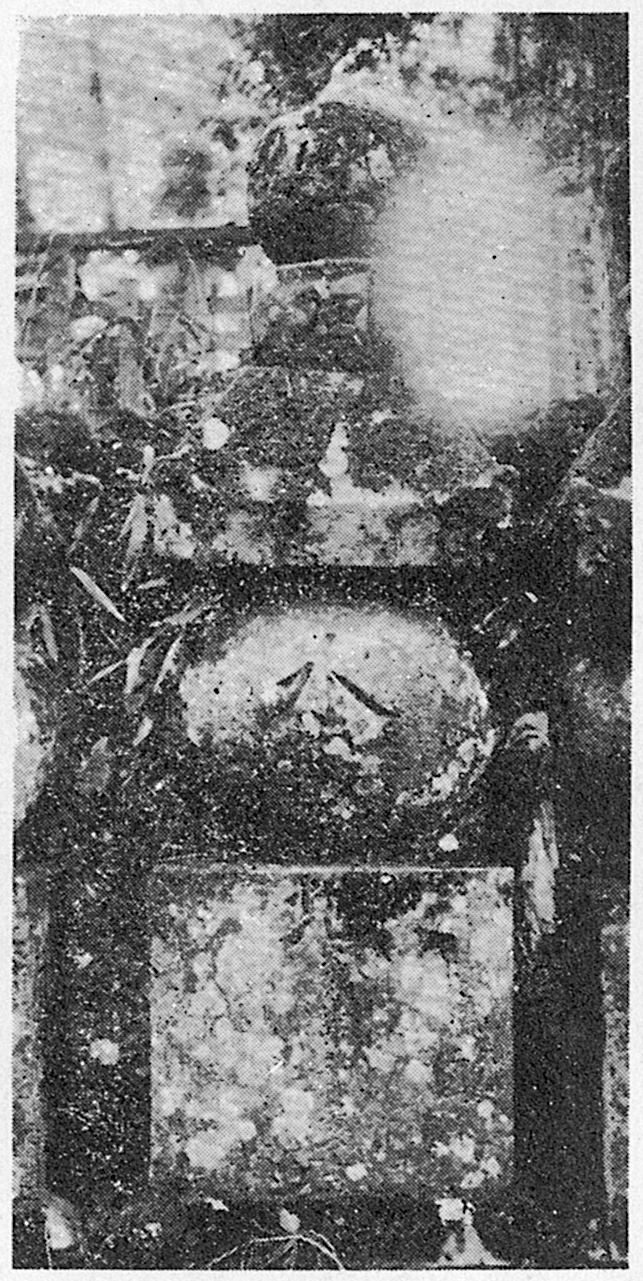
第三十圖版 今井宗久塔(高野山奧ノ院墓所)