「志記」(寛政二年十二月序)は、士君子の任務は経世済民にあるとの信念のもと、「官職」「関市」「戸籍」「田賦」等々について、その大体とあるべき姿とを論じた著述である。この「志記」を特徴づけているのは制度への多大な関心である。しかもその制度とは徂徠学でいうところの「礼楽」制度を意味し、その言い回しも徂徠学に特有のそれであり、徂徠学的発想に基づいていることがわかる。
宜応は「聖人、人情に依て道を立て」たとし、徂徠の説に倣って聖人を道の制作者と捉(とら)える。そして中興の英主と仰がれた四代藩主信政をこの「聖人」に見立て、この治世で当藩において文物制度が備わったとみる。しかし、その制度も時を経るにつれて衰微してゆくのはやむをえないことである。これは誰の罪というのでもない。強いていえば「年を経るの罪」であり、制度疲労はおのずからのことである。したがって肝要なのは「時」と「勢」を勘案して、制度を新たに立て直してゆくことである。「礼楽制度は時として革(あらたま)る物」なのである。そしてまさに「今や革命の時」に当たると宜応は考え、礼楽制度のあるべき姿を書き綴ってゆくのである。この宜応の考え方の背景に、徂徠のいう「先王制作」説が控えていることは明らかである。徂徠のいわゆる〈作為〉の論理は行政官僚としての武士の制度変革構想に少なからず影響を及ぼしていたのである。
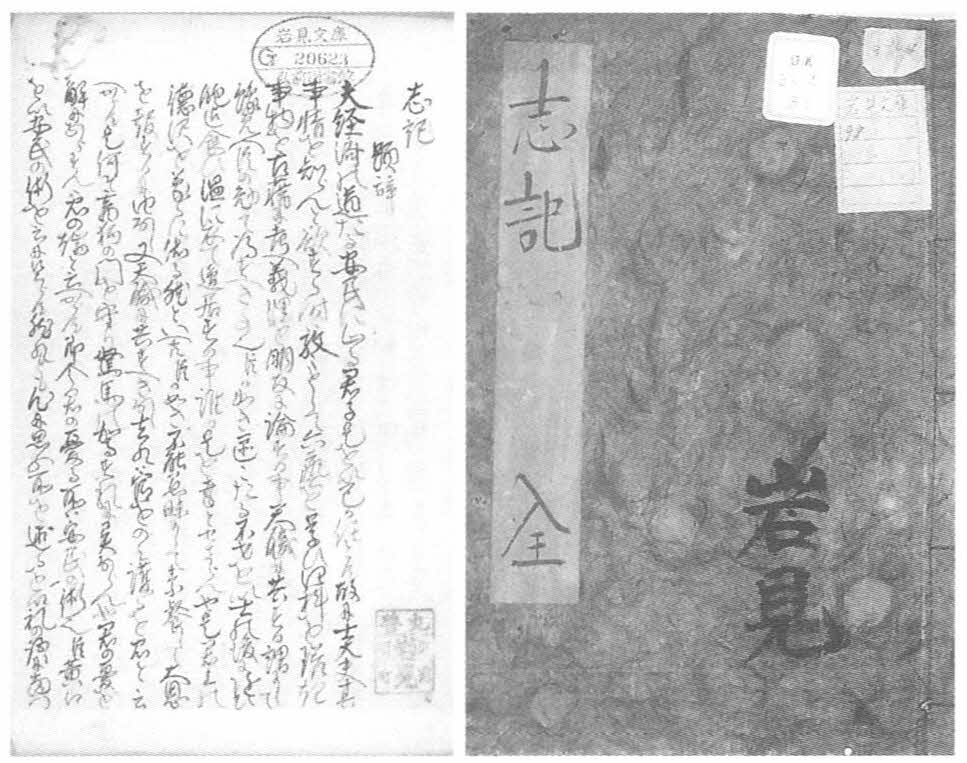
図171.志記
目録を見る 精細画像で見る
「秘書 毛内宜応存寄書」は天明の大飢饉で荒廃した藩政を打開すべく、人材登用と藩士の農村土着を提言したもので、天明四年(一七八四)九月、八代藩主津軽信明に提出された。宜応のこの農村土着策は、徂徠の著である『政談』と『鈐録(けんろく)』が引かれているように、明らかに徂徠から学んだものである。『政談』のいわば弘前版ともいえるが、要点は以下のとおりである。
富が町人に流れ武士は困窮し、「風俗花美」となり、貨幣経済が農村を侵食し、「農商打混し百姓共茂自ラ町人心ニ罷成リ、今日之利潤ニ走リ」、廃田は増えるばかりである。この状況の根本原因は藩士の城下集住にある。したがってこの現状を打開するには武士を帰農させる以外によい方策はない。宜応はその利点を二一ヵ条にわたって列挙しているが、要は、①武士が農業に従事すれば農業人口が相当分確保され、その結果藩財政の負担が軽減される、②武士が農村に「充満」することによって、「悪徒」の発生、寄り付きを防止することができる、③愚かな農民の計画性のない耕作指導や生活指導ができる、④日々耕作に勤(いそ)しめば「商家之風体を見習」うことなく「万事素朴」となる、⑤耕作体験を持つことによって「下之情に通し、三民之艱難を知」り、「農之時」を弁え「民ニ苦しミを不懸常(かけずつね)ニ農事に心懸(こころか)」けさせる役人を輩出できる、等々である。『政談』で指摘されている土着策の効用を基本的に踏まえたものである。
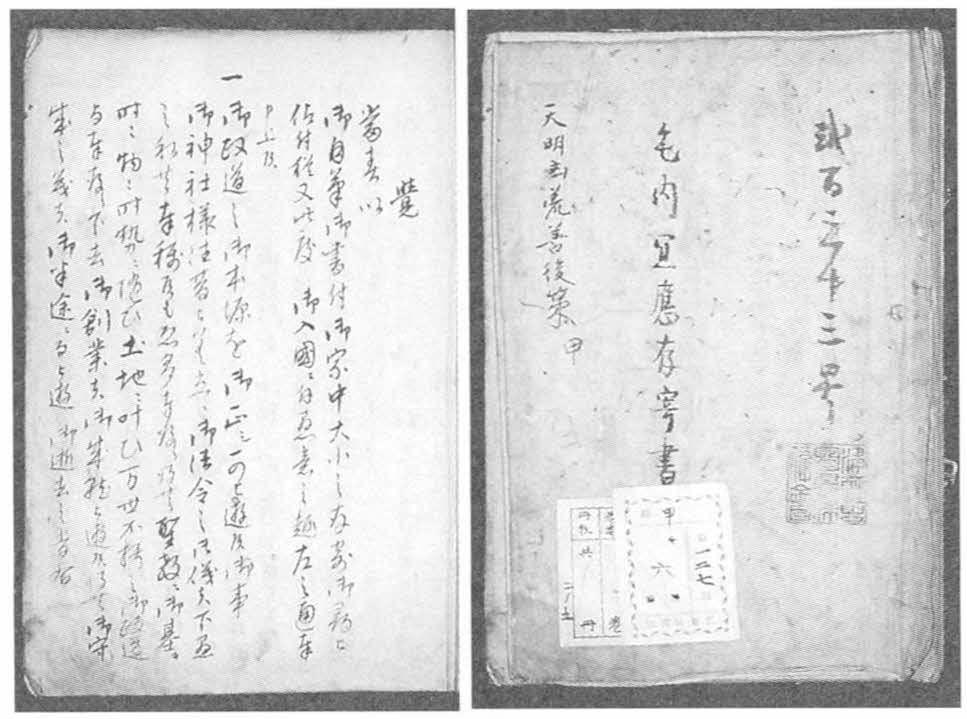
図170.毛内宜応存寄書
八代藩主信明は「存寄書」に理解を示した。彼は安永四年(一七七五)、江戸表で徂徠晩年の弟子宇佐美灊水(しんすい)を聘し師事しているが、灊水はその著『事務談』(宝暦・明和年間成立)で、幼君教育に関して、世子は江戸の「浮華ノ風俗」を避けて、国元における「質素」の生活に「染習(せんしゅう)」させるべきだとの持論を持っており、灊水のこういった教えが、信明が武士帰農策を受け入れる下地になっていたと考えられる。土着令は、寛政二年(一七九〇)、四年と発布され、武士達は弘前城下から各村々へ散っていった。しかし結果は失敗に終わり、寛政十年五月二十七日に廃止された。